空威張りビヘイビア

学園の敷地の只中に巨大なバケモノが屹立している。
先程まで辺りを覆っていたもやもやとした淀みは中空にまで立ちのぼって広がり、まるでバケモノがその淀みを纏っているかのようだ。
それにしてもやけに静かだ、とツカサは思った。
念のため、耳に手をやる。ヘッドフォンは外れたままだ。今は自分が外界を遮断しているわけではない。
けれど周囲に音もなく。
異形の威容を湛えながら、しん、としている。
時間の流れが、重い。空気が張り詰め、徐々に凍っていくような錯覚を受ける。
物陰からもう一度、バケモノの姿を確認する。
奴はまだそこにいた。間違いない。ただ、こちらを見失っている様子は見て取れた。
それから見回す。
逃げ遅れの生徒たちは、ぐったりとうなだれて地面に倒れている。
眠っているのか、気を失っているのか。
今のところ目立って傷ついた者はいないようで、ツカサは少しほっとする。
関係ない連中を巻き込みたくはなかった。
と、咆吼が聞こえた。
「厳厳厳罰罰罰則則則規規規――」
巨大な吠え声。あのバケモノの叫びか。
軋むような不協和音に思わず顔をしかめ、ヘッドフォンを被ろうと手を伸ばす。
その手がうまく動かない。
さっき一発、腹にバケモノの攻撃を貰ったのが響く。鎖の遠隔攻撃。あれはなかなか強烈な一撃で、不覚を取った。
不測の事態だ……。
バケモノの足下――いや、厳密には足はなく、物騒な刃物や得物をぞろぞろとぶら下げながら浮いているのだが――ともかく下には、その姿を小さく切って縮めたような子分共がうろうろと蠢いていた。
奴らは探索している。
同じ場所に隠れていては、そのうち見つかってしまうだろう。
ツカサは考える。
俺が率先して狙われるのは当たり前だ、俺が自分で蒔いた種なのだから。
だが、このままでは何も解決しない。ただあの『タテマエ』のバケモノが暴れることを看過できない。
どうする。
そこへ足音が近づいてきた。場に駆け寄ってきたのはあの、風紀委員の娘だった。
バケモノを見上げ、驚愕している。
無理もない。こんな怪物には誰も心当たりがないだろう。俺以外は。
けれどツカサのすべきことは決まっている。
「勿論、戦うさ」
隠れることをやめ、姿を現し、前に出る。苦痛を払って笑う。
その決意さえあれば、すぐにも行動できる。
ツカサは敵たるバケモノを見据えた。
だがさて、どう戦う。
そう……奴と戦う方法は確実にある。しかし、ひとりでは戦えない。
協力者と手続きが必要であり、また、手順を踏むには、思い出す必要があった。
あの『タテマエ』のバケモノの由来が何なのか。そして何故ここに現れたのかを。
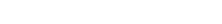
普通の空。いつもの朝。
朝はまだ眠い。眠気を象徴するかのような、ぼんやりとした淀みが学校を囲んで漂っている。
ここに転校してきて何日、何ヶ月が経っただろう?
馴染みの連中はいるが、友人らしい友人は出来ずにいる。だがツカサにとっては、そのほうが幸いだった。
周囲から距離を置き、自分の領域を守って、過ごせればいい。
自分は迷惑な存在なのだから。
登校する先が変わっても、ツカサの日常は意外と代わり映えしないものだ。当初こそ物珍しさが手伝って注目を集め、クラスメイトから色々と世話を焼かれたりしたものだが、時間と共にそれは自然と薄れた。
それは単にツカサも周囲の皆も、慣れた、ということかもしれない。
特に努力することなく勝ち取った、好奇から惰性への変化だった。
それでいい。ヘッドフォンをつけて、何も気にしないように振る舞っていれば、ツカサにとっても周囲にとっても、安全が保たれる。
ただ初日から変化せずにある状況が、ひとつだけある。
これだけは、慣れなかった。
日々、風紀委員の娘ひとりが妙に自分を目の敵にして、説教してくるのである。
相手のほうもよく飽きないものだな……とツカサは呆れる。
やれ、ネクタイを着用するのが男子制服の規定だの、シャツの裾が乱れているだの、マフラーが長すぎてなおかつ色が良くないだの、毎日毎日同じような内容ばかりを語彙を尽くして喋れることには感服するが。
互いに実害もないのに、わざわざ一方的に指図をするというのは、余計なお節介ではないか。
そもそも服装規定の話をするならば、
「俺は規定外の人間だ」
ツカサは委員の娘に、そう言ってやったことがある。そうしたら、次の日からさらに言及が厳しくなった。何故だ。
「あなたは人の話を聞いているのですか? そうですね、聞こえていないですよね、その格好。耳に蓋をして」
「蓋じゃない。ヘッドフォンだ」
「そんなことはわかっています。校則違反です」
「どこにも書いてない」
「生徒手帳に書いてなくても決まりです。違反者が多すぎて規則の改正が追いつかないのです。耳を覆うものは禁止です」
何を理由に、そんなルールを。
決まりですから。
くだらない。
決まりを守れない人は学生とは言えません。
あんたがそう思ってるだけじゃないのか……?
規則を破ってばかりの人の言い分なんて、聞く耳ありません。
――頑固者と長々と話し合いをする気はないし、相手にしても言い分をぶつけたいだけなのだ。交渉しようにも成り立たないだろう。ツカサは、本当に耳に蓋が出来るならしたいと思う。
しかし、どうしてこの女はこんなにしつこいのか。慣れるということを知らないのか。
そのうちに登校時の校門チェックだけでなく、校内で会うたびに何かと風紀女から言われるようになった。
「またネクタイをしていない! ちゃんとしてください! それに髪を染めるのは禁止です!」
悪かったな、この金の髪は地毛だ。ネクタイは家に忘れた。
「廊下は走らない! 右側を壁に沿って歩くのです」
走ってない。右だろうが左だろうが、他人とぶつからなけりゃあいいだろう。
「そんな下品な食べ方をしてはいけません」
他人のやることを、そこまで見ているのか?
「皆さん! 先生の講話があります、静かに! 騒がない! そこのあなた、静かにしてください!」
お前が一番、くちうるさい。

『無闇にヘッドフォンを外すな』
これは誰の忠言だっただろう?
ツカサは、咄嗟には思い出せなかった。
外したとしても直ちに問題があるわけじゃない。用心してさえいればいい。常に気を配るのは、疲れるから嫌だが。
『自分の殻を作って閉じこもっていなければならない。言葉を聞かないようにしていなければならない。そうしなければ何かが起こる』
何か、ってなんだっただろうか?
ぼんやりとしているが、すべてを忘れているわけではなかった。だからこそヘッドフォンが欠かせない。
それにしても中途半端に品のある学校だな、と今更思う。転入する前には知らなかったが、この学園はそれなりに名門らしい。
もっとも知ったところで、何かが変わるわけでもなかった。
身も心も清潔な高級感をもって画一化された生徒たちは、ぞろぞろと、黙々、学舎へと続く通学路を行く。
いつも通りの登校風景……のはずだった。
けれど、今朝は電車が遅れた。
ツカサの登校時間にしては、周囲に他の生徒が多かった。
学舎の天辺の鐘が鳴る。
風紀委員たちの手により、がらがらと重たい校門が閉じていく。
ツカサは苦笑する。俺はともかく、普段と同じように出かけたこいつらも遅刻確定か。理不尽だな。
門前に閉め出されて、ざわめく一般生徒たち。そこに例の委員の女が進み出て言う。
「皆さんが間に合わなかった理由はわかりましたが、門を開けるわけにはいきません。私たち学生は日頃より不測の事態に備えて行動せねばなりません」
無茶苦茶な論拠だ。
「これより全員に違反切符を切ります。手続きが終わった人からひとりずつ、門の隣の通用口に向かって頂きます」
ブーイングが飛びながらも、皆はやがて、整列し始めた。どうしてこういうときに整然と並ぶことが出来るのか。ルールに従った、訓練の賜物か。
指示が聞こえないフリをして、ツカサは列から離れる。
「また、そうやってあなたは!」
そこにつかつかと早歩きで迫ってきたのはやはり、あの委員だった。
「何故並ばないのです……」
「ん?」
「何故! 並ばないのですか!!」
「別に最後でいい」
「あとから最後尾につくなど怠慢です、今のうちから並んで誠意を」
何に対する誠意だ?
「皆さんもう並んでいるのですよ、自分だけ失礼だと思わないのですか」
何に対する失礼だ。
「ともかく、聞こえないようなそぶりはおやめなさい――」
風紀委員娘は、ツカサのヘッドフォンへと右手を伸ばした。左耳のイヤキャップ。それを取ろうというのか。取ったところで何も変わらない。聞きたくない文句は、意識していれば頭に入ってくることはない。
そもそも、がっちりと両耳を抑えこんだそれは、彼女の細腕一本でそう簡単に外れる代物ではなかった。
なかったのだが……
「あ」
唐突に彼女が転んだ。右手をツカサの左耳へ向けたまま。いや、その手が掴んだ。イヤキャップがずれ、バンドがずれて、ヘッドフォンは両耳から剥がれた。
不意打ちだった。
「――ご、ごめんなさい。乱暴するつもりは」
彼女は謝ったが、ツカサにこんなアクシデントへの心構えはない。
だから言葉はダイレクトに頭に入ってくる。しばし、外れたヘッドフォンを首からかけた格好のまま、ツカサは呆然とする。
「つもりはなかったけれど……こほん、それとこれとは話が別です。この学舎に通う者として、決まりは決まりとして、守ってください」
それでも委員の言葉はじゅうぶん聞こえている。
「……並ぶよ」
そう答えるのが今のツカサの精一杯だ。視界の端々で淀みが渦を巻いている。
「よろしい。ええと、その。私も少々狼藉をしてしまったので、あなたの累積の違反は減免します。が、今後も不備あれば先生には報告しますからね」
「どうぞご自由に。とにかく、列にはつく」
「ええ、わかればいいんです。わ か れ う゛ぁ」
歩み去ろうとしている委員娘のまっすぐな歩調が、既に歪んで見えている。足音が撓んでいる。
渦を経て、集まった淀みが影を成す。
良くない兆候だな、とツカサは思った。
その刹那、
「違反責任怠慢校則義務禁止自粛秩序命令束縛節度制服規約――」
何者かが呻いた。
「誰だ?」
思わずツカサは訊く。
「――厳罰」
相手は答えたが、それがそいつの名前や挨拶ではないだろう。続いてツカサ目がけて飛んできたのは、言葉を束ねた赤黒い鎖だった。
大量の、何かを縛っていたらしい鎖。辺りを埋め尽くす勢いで広がる。
その鎖の一本、鋭く素早い一撃がツカサを打った。腹に当たったか、ツカサはつんのめり、片膝をつく。
鎖の擦れる、ざらざら、ざらざらと耳障りな痛々しい音が反響する。
鎖と共にぼんやりとした淀みが漂い、空気を曲げて見せている。
振り返るといつの間にか、校門がない。消失している。
門前の列は乱れている。異様な事態だが、生徒の皆は動けず、声を失っている。そして何かを見上げている。
ツカサもその視線の先を見る。
広がって蛇のように動く鎖の集約点に何かの姿が立ち上がっていく。
最初は何かの影法師かと考えた。それは虚空から釣り下げられた照る照る坊主のようでもあった。
しかしそいつは禍々しき鈎爪を有していた。そして、巨大だった。
人型のようでもあり、顔らしきものがあり、視覚があるのかはわからないが、ともかくそいつは、ツカサを見た。
目があった、かも知れない。
いや、見つかった。
ツカサは思った。思い出した。この異形がどうして生まれたか。
ああ、やっぱりな。俺のせいだ。
いつも通りに用心していれば起こらなかったはずの何かが、ここで起こってしまった。
誰だかわからないけど忠告ありがとう。俺はあの女の説教を介してこのよくわからないバケモノを生み、そして襲われる運命のようだ。


