空威張りビヘイビア

-
突如学園を覆い尽くす、極彩色のサイケデリック。
歪んだコラージュに塗れた教室には、絶え間なくノイズが響く。
流行歌の歌詞の断片と、何か古めかしい訓話を切り貼りしたような意味不明の言葉とが、周辺を取り巻くノイズにちりばめられていた。
ノイズ――耳障りな、雑音。
壊れたラジオの音声のようであり、うごめく関節の擦れる音でもある。
教室の只中にたたずんでいる、大柄なタテマエのバケモノは絡新婦――女郎蜘蛛。
蜘蛛は見かけの硬質なデザインこそコスメティック、だが材質の実態は洋菓子のようで、全身に生クリームを塗りたくられ、光沢を放っていた。
今のところ、蜘蛛からツカサへの目立った攻撃の気配はない。
ターゲットを見失ったらしく、探している素振りが感じられる。
その女郎蜘蛛からは、異様な匂いがした。
一瞬、頭痛がしそうなほどの甘ったるい香りが漂う。だがすぐそれが腐臭に変わり、ツカサは顔をしかめる。
生誕と死、そして再生。出来たてのおいしそうなスイーツがあっという間に腐敗してカビていく……その様子が巨大蜘蛛の体表で目まぐるしく、繰り返されているようだった。「バケモノの由来者はなかなか良い趣味の持ち主……いや、やっぱり悪趣味か」
この女郎蜘蛛の出現を、ツカサは数日前から予見していた。
ここで戦いになることも想定通りだ。
けれどこのままでは、決着をつけようにも、つけられない。
「で、肝心の由来者は何処だ?」
蜘蛛の挙動を窺いつつも、ツカサは目で探す。
あの女郎蜘蛛――タテマエのバケモノを退治するには、タテマエ出現のきっかけとなった由来者の協力が不可欠だ。
しかし、先日あれほどツカサにまとわりついてきた『彼女』の姿は、今はない。
いったい何処に行ってしまったのか?
勿論、こんなバケモノを前にすれば、逃げるのが当然だろう。
事情を説明されても、混乱が広がるばかりに違いない。
けれどそれでも、どうにか『彼女』を説得すべきだった、とツカサは舌打ちする。
由来者を通し、タテマエに対抗できるホンネの妖怪の力を引き出し、操ること。
それが言ノ葉使いであるツカサの戦いの本領だが、それ以外では為すすべがないとも言えた。
「あいつ……鈴乃音、とか言ったな。名前」
女郎蜘蛛はその巨体と怪力で、教室の座席をはじき飛ばし、教卓をねじ曲げ、黒板をひっかきながら、室内に居座る。
「いや、たとえ鈴乃音の協力がなくとも……俺は、戦ってみせるさ」
ツカサは大きくひとつ、深呼吸をする。
蜘蛛はただそこに居るだけだ。だが目標と目的を一時失い、徐々に癇癪を起こしつつあった。
ツカサは考える。
何故こうなったのか。これから、何が起こるのか。
この蜘蛛の気配を最初に感じ取った時のことを思い出す。
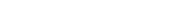
-
反復される日常。
季節を問わず、分厚いマフラーとヘッドフォンとで身を固めていても、さしたる注意を受けるわけでもない。
ツカサは、もはや物珍しい転入生としては扱われなくなっていた。
時折朝の校門での風紀チェックに引っ掛かりながらも、取り立てて言うべきことも少ない、平穏な学園生活が続く。
名門の風格を漂わせるこの学園において、ツカサはどちらかと言えば出来も素行も悪い部類に入るのだろうが……ひとまず、日々に大きな問題はない。
ただこの頃、少し気になることがツカサにある。
同じことを同じように気にしている人物が、ツカサに近づいてくる。「今日もネクタイつけていませんね、校則違反です。ダメですよ、ツカサさん」
「おはよう鹿乃川。違反切符、切るのか?」
「いえ。切符を委員室に忘れましたので」
「あんた、割と適当だな……」
毎朝、ツカサの服装を厳密に見るのは風紀委員の鹿乃川律の役目だ。側につきっきりで説教をしてみせるその姿は周囲の公認、律はツカサの専属担当といって良い。
「失礼。こほん。あまり近くに並んで歩いていると、あらぬ誤解を受けますので」
「?」
校門を過ぎ、律はツカサと少し距離を保ちながらも、一緒に昇降口へと歩く。
「ええと……ツカサさん。最近、三鹿ナルキが授業に出ていないようなのですが」
「ああ、それか。俺も理由が知りたい。あいつ、どうかしたのか」
「私に訊かれても」
「餓鬼ちゃんのほうは、無事でいるのか?」
「はい。餓鬼ちゃんとは毎日のように、家で会ってます。でも、家に置いてきているわけではないのです。連れてきているのです、けど……」
「けど、校内には現れない。そういや餓鬼ちゃんの顔もしばらく見てないな、俺」
「今ここで、呼んでみますか?」
「そうまではしなくてもいいが」
「……餓鬼ちゃんのお菓子、いつの間にか私のポケットに入ってることがあります。でも餓鬼ちゃん自身は、学校では姿を見せてくれない。何故でしょう」
「ふむ」
ふと立ち止まって、ツカサは辺りを見回した。
少しヘッドフォンをずらして、あえて聞き耳を立てる。ツカサが外界の音を無闇に聞くのは危険だが、心構えをもって耳を澄ませば、通常では聞こえないはずの何かを聞くかも知れなかった。
律も同じように耳を立ててみる。
明確に何かを聞き取ったわけではない。登校時の学生たちのざわめきに、かき消される。
だが、ツカサにはわかった。
以前に学園を覆っていた霧や空気の淀みとはまた違った、怪しげなモノを感じる。
ツカサはヘッドフォンを被り直し、律に向き合う。
「あるな。気配が」
「気配……」
「あるいは、雑音としか言えないが。普通には、ありえない音だ」
そう。この気配をあえて表現するなら……それは音だった。
音量は決して大きくないが存在が確かな、ノイズ。
「ナルキや餓鬼ちゃんみたいな妖怪が活動しにくい状況が、この周辺で起こりつつある」
「何やら不穏ですね。大丈夫なのですか?」
「心配ない。今のところ、害はない。餓鬼ちゃんが苦しめられるようなことはないさ」
「はい、でも……」
「俺、少し調べてみるよ」
ツカサは足早に昇降口を過ぎ、靴を履き替えて室内に向かった。
何が起こるのかは、わからない。ただ、予兆は確実にある。
それは誰かのタテマエのバケモノが出現する予兆だ。
しかし、まだ目には視えなかった。
その場に残された律は、自分の風紀委員腕章をたぐり「そういえば服装チェックの途中でした」と呟きつつ、校門へと戻っていった。ツカサの姿を、校舎の端からじっと見つめている目があった。
最初はまるで関心がなさそうに。
けれどそのうちに、好奇に満ちた視線で。
「そぅねぇ☆ じゃあ今度はあぃつにー、ぃたずらー、しよっかな……」
彼女は独り、笑った。
それから退屈そうな表情を作ってみせ、いつもの『取り巻き』の男共に声を掛ける。
「今朝もあっついよねー、みんな?」
彼女は制服の胸元をやや広げ、ばたばたと大袈裟に仰ぐ。男共が前のめりになって、彼女に近寄ってくる。
「んじゃ、朝の散歩。連れてってよ?」
そして校舎から渡り廊下に出た彼女と男共は、始業前の喧噪を割るように、乱れた行進をする。わざとらしく往来の中心を埋め、占拠するような、その歩き方。
「あ☆ ごめんねー」
故意に彼女は、人にぶつかる。
痛くない程度に、誰も彼もに、身体をすり寄せ、そして離れていく。
彼女に触れられて喜ぶ男子もいれば、あからさまに嫌悪を示す女子もいた。
いつしかこの行進は、日々の恒例となる。
とにかく好評悪評問わず、目立つ存在となること。
それが彼女、鈴乃音舞の目的だった 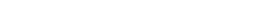
-
やがて現れるであろう、次なるタテマエのバケモノの予兆。
それは微弱な雑音として、校内に響いていた。
こいつはデタラメなノイズではなく、何か意味があるはずだ。
ツカサはヘッドフォンに手を掛け、わずかにずらし、雑音の正体を聞き取ろうとする。
他人の表面的な言葉からその内心を感じ取り、バケモノ出現を誘発する『言ノ葉』能力を持つツカサだ。あまり自分の耳を使えば、リスクを伴うが……。
しかし以前、鹿乃川律のタテマエ・コトワレが出現した際、それが暴れ出すまでツカサは気づくことができず、被害を周辺に広げる羽目になった。
次の未知のタテマエも、強い力を持っているかもしれない。
ならばタテマエの気配が育ちきってからではなく、早い段階で対策を試みたい。
危険は、未然に防いでおきたかった。
「……何を言ってるかまでは、わからないか」
耳をそばだてるのをやめ、ツカサはヘッドフォンを被った。
幸い、ツカサが年中身につけ続けているマフラーが、ツカサの言ノ葉能力の暴走を抑えていた。このマフラーは特殊な蔦状植物の繊維で編み込まれたもので、季節の寒暖に関わらず一定の温度でツカサを守り、悪性の霊力が身体に蓄積することを防いでくれる。ノイズの発生源を特定できないまま、始業のベルが鳴る。ツカサは自分の教室に戻った。その後、授業が開始されて1時間、2時間が経ち……。
わずかながらノイズが大きくなっている、とツカサは感じていた。ごく自分に近いところから出ていることは、わかっている。
雑音には波のような振れ幅と指向性があり、時折「この音は、自分に向けられているのではないか?」とも、ツカサは察していた。
誰だかわからないが、俺のことを『視て』いる奴が、その身にタテマエを隠し持ち、予兆のノイズを放っている、と。
しかしクラスメイトや知り合いに、発生源らしき心当たりはない。
では、誰なのか。
決定的な手掛かりはまだ何も無く、目標を絞り込むには至っていなかった。そのうちに昼休みになった。
ツカサが渡り廊下を歩いていると、妙な集団に出くわす。
「やっぱり今日、お昼になっても、あっつぃよねー?」
中核にいるのは校則違反の常習らしい派手目な印象の女子学生だった。彼女は胸元をばたばたと仰ぎ、短いスカートを翻しながら歩く。目元が浮きそうなほどの化粧をして、そこはかとなくフレグランスの香りを漂わせている。
その周囲には何故か、少々情けない感じの男共しかいない。男共は女の機嫌を伺うかのように低姿勢で付き従っていて、異質な雰囲気を醸していた。
この派手な女は、いったい何者なのか。ツカサは少し前、旧校舎の不良の輩たち経由で聞いたことがあった。
確か、名を『スズノネ』という。
私学にはありがちなことだが……どうやら、学園に大きな寄付を行っている保護者を持つ娘で、そのために違反を目こぼしされているらしい。ツカサが最近まで彼女の存在を知らず、律の口から彼女の存在を聞いたことがなかったのも、恐らくそのせいだろう。
スズノネは学内に敵が多く、特に同性からは嫌われている。だが注目を集めるための弁舌と色目使いが巧みで、男たちの一部はむしろ彼女に味方しているという。
――ひとまず、関わり合いになりたくない相手だな、とツカサは思う。「あ☆ ターゲット、発見」
いきなり、女は取り巻きの男共をその場に留め、ツカサに向かって猛然と歩いてくる。
へこんだ上履きの足音を響かせながら、何かに挑戦するような目つきで、何かを企んでいるような薄笑いを浮かべて。
何のつもりだ?
そこでツカサは、唐突に思い出した。
やや釣り目がちな、大きい瞳。
こいつは……今日、自分の別クラスとの合同授業にも顔を出していたはずだ。特別教室では、自分の斜め後ろの席にいた。ツカサの横顔を、彼女は何気ないフリをして、その時限中、ずっと『視て』いた……。「舞さん、急にどうしたんですか」「舞さん、そいつにいったい何の用が」「舞さん、よしてください」――。
男共がざわめく。
舞さん、と男共に呼ばれた彼女がさらに接近してくる。
既にツカサの目と鼻の先。
彼女の手がおもむろに、ツカサへと伸びる。言葉にならない雑音が、ツカサのヘッドフォン越しに大きくなる。


