空威張りビヘイビア

-
「ねぇねぇ金髪君ー、ワタシのこと知ってるー?」
「は?」
金髪君というのは、俺のことか。ツカサは辟易して顔を背け、渡り廊下を逆向きに歩き始めた。馴れ馴れしく付きまとってくる相手は、好きではない。
しかし彼女はツカサに追従、横へと回り込んでくる。
「鈴乃音だょ、鈴乃音舞。あれ、初対面だっけ?」
「知らないが」
実際、ツカサに事前の面識はなかった。けれど彼女、鈴乃音舞は、わざわざツカサの顔もとにかがみ込み、上目遣いをして語りかける。
「じゃあこれから仲良くしよう☆ よろしくぅー☆ はぃ、握手ー☆」
「何の脈絡もない、強引な奴だな……」
舞が差し出してきた手を、ツカサは取らなかった。舞は大袈裟な膨れ面になる。
「まーたそんな態度取っちゃって☆ わかるょ、キミ冷たいフリしてるんでしょー」
……また? フリ?
自分が忘れていただけだったのか、何か彼女と接点があったか、とツカサは一瞬考えさせられてしまう。
しかし心当たりは皆無。確信したのは唯一、例の『スズノネ』は間違いなくこの女だ、ということだけだ。
「それよりもさ」ぱっと明るい表情を作り直して、舞は続ける。「昨日のテレビの『アレ』、最後どぅなったっけー? 見逃しちゃって」
「なんのことだ」
「テレビ見なぃの?」
「そうじゃなくて……」
「『アレ』流行ってるらしいし、キミなら詳しいかなとか思って」
「わからないな。他の奴に聞いてくれ」
彼女の言う『アレ』が何なのか、ツカサにはわからない。
ツカサが『アレ』を知るわけがない。何故なら彼女は、何も示していない。
奇妙な空虚さを、彼女は漂わせていた。
「そぅ言わずにさぁー、その……ワタシだって、まだ金髪君とどぅいぅ話したらいいかわかんなぃから、変な話してるとは思うけど」
舞は自分の指を自分でいじりながら、ツカサへの上目遣いを継続する。
「でも、キミに興味があるんだょ……だからなんでも、いぃからお話、させて」
「興味か」
「うん」
「あいにく、俺のほうはあんたに興味がない」ツカサは言い放った。
「え、ねぇちょっと」
「…………」
この派手な女子、鈴乃音舞と名乗ったそれにツカサは構わないようにしようと思った。顔をうつむけてマフラーで表情を隠し、ヘッドフォンを深く掛け直して、スマホをいじるフリでもしておこうと思った。
普通の相手ならば、それで遮断できる。
元々、ツカサは普段から――鹿乃川律から執拗な説教を受けるようになるよりも前の頃は――そうやって、外界と自分の間を断ってきた。
自分に対して、興味を持たれる必要はなく。関心のない相手と、わざわざ話すことはない。
だが、
「えー、ちょっとぉ、なになにー?」
口角を緩めて甘えた猫撫で声を作りながらも顔はまるで笑わず、ただでさえ釣り目がちな目つきを据わらせて、舞はツカサに食い下がる。
「聞こぇてなぃフリしてても、ダメだぞぉ金髪君☆」
言いながら、ツカサにまとわりつく。そして、
「当てずっぽだけど、当ててあげようか?」
「何?」
突然、舞が指を立ててくるくると回し、ツカサに向けながら言い出したため、ツカサは返事をしてしまう。
ツカサには少しばかり後悔がよぎったが、舞は意に介さず、どんどん近づいて、手を伸ばしてくる。
「金髪君のそのヘッドフォン、何も聞いてないでしょ」
「……何故わかる」
「だからテキトーだょ。っていうか音楽聴くためにつけてなくて何か別のモノが聞こえちゃうとか? どれどれー☆」
「あ」
舞はまったく自然に、その指先でツカサのヘッドフォンをずらして、ツカサに密着するくらいに顔を近づける。
それからヘッドフォンへと耳を寄せて「ふむふむ」と呟く。
「あれ? やっぱり。なんも聞こえてこなぃ」
「…………」
「マジでなんも聞いてないのぉ!?」
「だから……何だよ」
「てことはファッション? DJ?」
「全然違う」
「でもヘッドフォンってつまり耳の蓋だょね、まぁ、わかる。つまり聞こえなぃけど人の話は聞きたくなぃ『アレ』だね、『アレ』」
ヘッドフォンを元に戻しながら、舞は勝手に頷いている。
彼女の言う『アレ』がなんなのか、やはりツカサにはわからない。それでも舞がわかったような顔で気怠くニヤニヤしているのが、いささか、ツカサの癪には障る。
さらには、舞が言ってのける。「閉じ籠もってないで、ワタシと遊ぼうょ」
……自分の言ノ葉能力は、他人に迷惑を掛ける。意図しないバケモノを生み出す、能力。
だから、とツカサは意識的に人を遠ざけてはいたが、自分を閉じているつもりはなかった。
なかったのだが……変に、この舞の言葉が、心に刺さる。
こいつはわかったようなことばかりを言う……いや、本当は本当に、わかっているのではないのか?
あまりに、思わせぶりの過ぎる奴だ。どこまで本気なんだか、わからない。「ワタシと……遊びましょう?」
舞がもう一度、ツカサへとささやきかけた。「遊ばない。俺は、お前と遊ぶつもりは、ない」
確かに言葉は刺さったが、気持ちが揺れたわけではなかった。やたらと身を寄せてくる舞に、ツカサは毅然と告げた。
「なんでよぉ!」
予想外の返答だったのか、舞は怯んだ。そして少し離れた、が、今度はツカサのマフラーの端を指先でいじり始める。
舞と一緒に来ていた男共は、距離を保ったまま、ツカサと舞のやりとりを固唾を呑んで見ていた。嫉妬か期待か、彼らのよくわからない感情が辺りに渦を巻いている。
本当に、いったいなんなのか。
俺は見世物じゃない。ゆっくりと深いため息を、ツカサはつく。それから舞へと目を向けた。
目が合って、舞がまばたきをする。
「このマフラー、変なの。触るとひんやりしてる。あ、このへん、ちょっとほつれてるんだけど」
「……触らないでくれないか?」
「えっと、その、そうだね。あははは。まぁまぁ、金髪君……怒った?」
「別に。怒ってるならお前の方だろう」
「え、ワタシが? 怒る? なんで?」
「物事が思い通りにならなくて、イライラしている」
「違うって」
「勘違いするな。俺は、お前に興味はない」
「別に勘違いはしてないって!!」――ワ タ シ ハ――、
ワタシは勘違いしない。
間違えない。
ワタシがすべきことは決まってるし。
とにかく人にウケなきゃ、意味がない。
みんなにウケてるものが、みんなは好きなんでしょ?
だったらワタシは自分のことより、他人にサービスしなくちゃ、甲斐がない。
他人に認めてもらわなければ、ワタシの存在価値がない。
だからみんなでワタシの相手をして。答えて。振り向いて。返事をして。
「なんだ? 突然、何を言ってる?」
一瞬、漂う微少な雑音の中に明瞭な言葉が混じったのが聞こえた。思わず、ツカサは舞に訊ねる。
「え? あ、あれ……ワタシは、何も……?」
問われて舞は瞬間、真顔になった。マフラーから慌てたように、手を離す。
途端。
――みしり、と今度は明確に音を立てて、周辺の空気がひび割れた。
時間の流れが変わり、色が変わり、淀んでいく。
ツカサは、ノイズの発生源を確定した。
それは、今まさに『ここ』の『こいつ』だ。
聞こえたのは、鈴乃音の声だった。
気づくと同時に、タテマエのバケモノはその場で生まれつつあった。
舞の足元の影を割って、徐々にむくむくと、実体をあらわす。
闇から出ずる、過剰な色彩の悪夢。
鏡状の目が光る。金属質とエナメル、スポンジケーキ、クッキーにプレッツェル……滅茶苦茶な取り合わせが渾然一体となって、身体となり、脚を生やして現れる。
蜘蛛から放たれた化粧とスイーツの匂いが入り交じり、場に一種異様な妖気を漂わせた。
「ば、ばけもの……!」
驚いた舞の口から率直な感想がもたらされた。
「な、なのに! なんで学校のみんなは気づいてないの!?」
周囲には、タテマエによる空間操作能力が発生していた。
目が痛くなるような、おかしな極彩色で空気が染まっていく。時の流れは緩慢になり、居合わせた人の認識力を下げていく。
タテマエのバケモノによる行動阻害を受けないのは、一部の妖怪と、ツカサのような言ノ葉使い、そしてそのバケモノのきっかけとなった人間、つまり由来者だけだ。
由来者となった舞が立ち尽くす。
そのバケモノは胴体だけでも丈2メートル、幅4メートルほどはあるだろうか。かつてのコトワレの、校庭にそびえ立つほどの巨体に比べればまるで小さいが、それでも渡り廊下の只中に出現した姿は、溢れんばかりの威圧的な大きさを誇っている。
8本ある長い脚をかさつかせながら、バケモノはうごめく。舞は総毛立った。
「ほんとになんなの、これ!」
「見ての通りのバケモノだ」
「クモ!! ジョロウグモっぽい!? でかいよ!!」
「絡新婦――女郎蜘蛛。お前はあれをそう呼ぶか」
蜘蛛を見てクモだと舞は言った。まるで捻りのないネーミングだが、その名付けでも特段、ツカサは困ることはない。
タテマエの名前がわかれば、言ノ葉使いは対抗手段を講じることが可能になる。
「ならば敵をこれより女郎蜘蛛と称す。これはタテマエ、いびつなる言ノ葉……ともあれ、現れたなら退治するさ」
「退治ぃ!? な、なんでもいいから! さっさとやっちゃってよ!!」
「無論だ。倒してやる。だが、この廊下は狭いな……他人を巻き込みやすい。場所を移るぞ。来い」
ツカサは扇子を取り出し、敵タテマエの視線を誘導するため、目前にかざして振る。振りながら、ゆっくりとゆっくりと、確実に蜘蛛を誘いながら廊下を後退する。
旧校舎の空き部屋におびき寄せれば、いくらでも戦いようはあるはずだ、とツカサは考える。
しかし蜘蛛の霊力干渉のせいだろうか、廊下に居合わせた鈴乃音舞の取り巻きの男共は恍惚の表情を浮かべつつ、ぐったりとその場に倒れ込んでいく。
それを見て、舞はあたふたと交互に男共と蜘蛛とを指差した。
「ちょ、待ってょ! 金髪君!! 倒すって言っても、どうやって! それにみんなは、あれ……あれ!?」
「他に構っている場合か」
「これって苦しいの? それとも気持ちいいの? この倒れたみんなは、いったい何がどうなって」
「お前、少しは人の話を聞け。あと『金髪君』呼ばわりはよせ」
「あっ……はい」
舞のテンションがおかしいのは、由来者がタテマエを発現させたときに特有の一時的な症状だと、ツカサは知っている。知っているから、わざわざ落ち着けなどとは言わないのだが、どうにも相手をしづらかった。 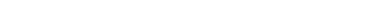
-
「あの、金髪君、じゃなくて。名前」
「葛葉ツカサ」
「葛葉君! あのバケモノ蜘蛛を退治って、でも、どうするつもり……」
「案ずるな。戦うのは俺だ。だが、お前の協力が必要だ」
「なんで!?」
出現したタテマエのバケモノ・女郎蜘蛛を旧校舎へと誘導する間、ツカサは鈴乃音舞へと手短に説明する。
ツカサ自身の言ノ葉能力を通して、舞の潜在的に持っていたトラウマなりジレンマなり責務なりが具現化した怪異が、タテマエであること。タテマエに対抗しうるのは、タテマエと同じ由来者の願望から生じる、ホンネの妖怪であること。言ノ葉使いであるツカサは、ホンネの妖怪を使役して戦うことができる、ということ――。
「妖怪とか言われても、いきなりわけわかんないし」
「まあ、そうだろうな普通は」
「あの蜘蛛、何処行ったの?」
「ん?」
少し目を離した隙に、女郎蜘蛛はツカサの意図に関係なく自ら勝手に旧校舎に入り、部屋のひとつを目指して進んでいく。
「巣作りでもするつもりか……」
蜘蛛は、他から隔離された場所を選んでいるようだった。これから人目を避けて戦いを行うのだからツカサにも好都合ではあったが、そこで蜘蛛の持つ別の問題にツカサは気づいた。
「……子持ちだ、あいつ」
大きな女郎蜘蛛の胴の下に、小さな大量の個体がしがみついている。
つけまつげをした真珠の目玉。その目から直接脚を生やしたような子蜘蛛の群れだ。
大蜘蛛が歩いていくその後ろに、ぼろぼろと子蜘蛛がこぼれていく。
慌てて大蜘蛛を追い掛けて元の腹に戻ろうとする子蜘蛛たちの姿は何かユーモラスでもあったが、がさがさとした異音と小刻みな動きが、気に障る。
「うわっキモッ! こういうのダメなんだけどワタシ……」
舞は首を小刻みに振っておののき、飛びずさる。
タテマエを生み出したばかりで不安定な心境の舞とはいえ、つい先程までの積極性はどこかに消し飛んでしまったかのような気弱ぶりだった。
「ダメなら尚更とっとと倒すしかないだろ」
ツカサは舞に呆れつつ、額の汗を抑えながら、女郎蜘蛛の動向を睨んだ。
気配が育ちきる前にタテマエを出現させたところまでは、思惑通りだった。
今のうちならば、打倒は難しくないはずだ。
早々に次の手を打ちたい。
そのためにも、ホンネの妖怪を呼び出さなければ……。「あと、よろしく……」
と、顔色を悪くした舞がとツカサへと力なく手を振りつつ、後ずさり、後ずさりして、新校舎側へ去ろうとしている。
「どこへ行く、鈴乃音」
「ワタシ戦いとかムリだし!」
「お前に戦えとは誰も言ってない」
「でもこれから言うんでしょ」
「言わない」
「うそ!」
「嘘じゃない……おい、待ってくれよ」
ツカサは困惑した。タテマエのバケモノを討つには由来者の協力が不可欠だ。
しかしバケモノを前にして、舞が逃げたいのは当たり前と言えば当たり前だ。
逃げずにいてくれ、と舞を説得しようにも果たして何をどう言えばいいのか。
「そのホンネの妖怪とかが、マジで戦いに必要なの? か、勝手にやっててよ」
一応……舞は踏みとどまる。女郎蜘蛛に激しい嫌悪を示しながらも、いかにも怖いモノ見たさ、といった風情で物陰から覗いていた。
蜘蛛は旧校舎一階の一角、今は使われていない臨時教室の机の並びの上に陣取って動かない。ここを当面の居場所と決めたようだ。
「鈴乃音、勝手にやれと言ったな?」
「い、言ったけど」
「ではお前のその言葉を許諾の意味と解釈する」
ツカサは言ノ葉使いだ。人の言葉を、意志を示す力に変換できる。由来者の舞があのような投げやりな態度と口調では、ホンネの妖怪がうまく働かない可能性があったが、しかし、敵であるタテマエを相手にするには手続きが必要だ。
扇子を構え、ツカサはホンネ召喚の祝詞を試みる。
「あやかしにはあやかしを、言には言を。タテマエ由来の代言者として命ずる。そこなチャラ女の、眠れるホンネ姿現せ――」
「ワタシ、チャラ女じゃないし!」
「黙っていろ」
ダメで元々、やってみると何かが現れる気配がした。
「な……何この感じ……やだ、ワタシの奥からなんか来るんだけど」
舞もその気配を察したようだ。舞自身の心の中から具現化されるあやかしの気配を。
「…………ナー」
出現したのは、一匹の小さな猫だった。ニホンネコだろうか。静かなたたずまいと美しい毛並みが、ほんのりと気品を感じさせる。
猫は教室の片隅におり、我関せずといった表情で、毛繕いをする。
「え? これが妖怪? 見た目かわいい、けど、こんなの……?」
廊下に面した教室の逆の隅から覗いていた舞は、大蜘蛛子蜘蛛に恐怖しながらも、出てきた猫を見て、いつくしむような、けれど小馬鹿にしたような半目をして、指さす。
猫は、まるで動かない。
「うまれたばかりの妖怪だ。まだ何の力もない」ツカサは舞に言う。
「チカラ、ないのぉ?」舞はさらに胡散臭げに、目を細めた。
「慌てるな。願え。ホンネの妖怪に名前をつけろ。それでホンネは新たな姿を得て、力を持って、動けるようになる」
「名前。え、猫の名前でしょ、なまえー……」
蜘蛛を見ていた舞の震えが突然止まった。何やら虚空を見つめて三秒考える。それから言った。
「じゃあ、ねーりん」
「ねー……りん?」
「昔飼ってた猫の名前なんだよ。猫の鈴と書いて、ねーりん」
「微妙に凝ってる名前だな」
「でしょ? お気に入り」
「わかった、猫鈴だな……しかし急に落ち着いたな、鈴乃音」
「え?」
「一瞬前まで蜘蛛にびびりまくってただろ」
「あれ? そうだっけ……そうだった!」すると舞は大袈裟に震えだした。そして喚く。「う……うわー! キャー!! でっかいバケモノの蜘蛛! ちょーコワイ! キモイ! はやく! はやくなんとかしてよー! たすけて! 助けて金髪葛葉クーン!!」
「ふざけてるのか?」
「マジだよ! マジ怖い! 見ての通りだって! ……こういう感じでいいのかな……」
豹変を繰り返す舞の態度を、なるべくツカサは気にしないように努めた。
ひとまず、女郎蜘蛛たちはツカサに敵意や関心を示してはいない。そこにいるだけだ。ただ、大蜘蛛は巨体と怪力を持て余しているらしく、蠢いているだけでも周囲の机や壁を大いに乱している。
仮にこれが暴れ出したなら、相当な被害が出るに違いない。
ツカサはホンネを操れるようにするため、美しい毛を持つ子猫に向け、祝詞を続けて繰る。そこで舞が横から、文句を言う。
「ねえ! その猫ちょーキレイだから傷つけたり汚したりしないでよ!」
「黙って見ていろ、鈴乃音」
「うええ、もうやめようよこんなの。あたしだってやる気ないし」
「……猫鈴よ、名を以て顕現せよ」ぺしっ。
途端、なんだか間の抜けた音がした。
「……なに……?」
おかしい。ツカサは扇子を見つめ、自分の術式を確かめる。
何も手順を間違えてはいない。だが、起こるべき正しい現象が起きない。
名を得て進化したホンネを操り、タテマエに対抗するはずが……。
ニホンネコは姿を変えることなく、あくびをして、そのままそこにいる。
まったくツカサの意図しない出来事だった。
「ナー」
猫鈴――ニホンネコが片方の前脚を振り上げ、ひと鳴きすると、その首についた鈴がみるみるうちに膨らんでいき、たちまち部屋を覆いつくさんばかりの大きさになる。
いや、その鈴に実体はない。そう見えるだけだ。直後、鈴はぐんぐんと縮んで元に戻っていく。
「なんだ……吸い込まれている?」
鈴の戻りにあわせるようにして、周辺に流れる雑音が、ノイズが、急速に小さくなっていく。女郎蜘蛛の姿も、子蜘蛛たちの姿も、縮小していく鈴の影の向こう側に、呑み込まれていく。
やがて、完全に見えなくなった。
蜘蛛は消えてしまったのだ。
「は……ははは。はははは……あはははは。な、なーんだ」
物陰にいた舞が、乾いた笑いを発した。
「バケモノ? 女郎蜘蛛? ぜんぜん怖くなぃじゃん。おどかさないでょ葛葉君。せっかく呼んだ妖怪猫鈴も何もしてないし、戦いっぽぃことも、特になんにもなく、終了ー☆ ……だょね?」
舞は無理矢理営業スマイル的な笑顔を作って見せ、そして徐々につまらなそうな真顔になり、ツカサに手を振って、それから背を向けた。
「ちょっと面白い催し物だったょ。また一緒に遊ぼう☆ じゃあねぇ、金髪君」
机の並びの乱れた空き教室から、歩き去っていく舞。
その後ろ姿を見送りながら、ツカサは内心、自分の混乱を抑えられない。
「馬鹿な」
何らの戦闘が行われないままタテマエが消失することは、これまでのツカサの記憶や経験上、あり得ないことだった。
蜘蛛の放つ極彩色の空間異常も、消えていた。
教室には、いつしか西日が差していた。
通常の時の流れから隔離され、旧校舎で女郎蜘蛛を前にしている間に、学園は放課後を迎えており、そろそろ下校時刻に近づいていた。
取り残された猫鈴は、美しい姿のまま部屋の片隅にいて、なんだかてしてしと、前脚で床をはたいている。
「まあ……帰るか」
ツカサは釈然としないまま、部屋を出ていく。
この場の脅威は何も無くなった。今ここで何かを続ける必然性は、もう、ない。
言ノ葉使いとしてのツカサの責務は、晴れていた。
けれど鈴乃音舞のタテマエとホンネとの戦いは、勿論、これで終わりではなかった。


