空威張りビヘイビア
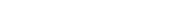
-
秋も半ばに差しかかって、日々だんだんと陽光も緩やかに変わる。
学園を含む付近一帯では最も有名な、地元の花火大会が本日、開催される。
鹿乃川律は一家総出でこの花火を見に行くのが年中行事だと言っていたが、今日の登校後にはじめて告知の張り紙を見て知ったツカサには、如何ともしがたい。
放課後のやや遅い時間、通学路の混雑を避け、ツカサはひとり、最寄り駅への長い坂道を下っていた。
そしてスマホの画面を、今一度眺める。『放課後、駅前商店街で。鈴乃音』
今朝早くに来たメールだった。
あいつは荷物持ちでも、俺にやらせる気か。ツカサは警戒した。が、それでも尚、やはり舞の指示通りに、現地に向かっている自分がいる。
我ながら、どういうつもりなのか。
嫌なら無視して行かないようにするのは簡単だ。けれど、そうしない。
しかし勿論、好んで付き合うつもりも、まったくない……。
どうも鈴乃音舞といると、己の建前と本音とはなんなのか、考えさせられる。学園の最寄り駅。その駅前から続く小さな商店街。そこではキヌがひとり、買い物にいそしんでいた。
「店主よ、こちらの乾物をひとつ頂きたいが」
「先生、さすがの目利きだね。こいつは年代物だ」
「若干くたびれているから年代物というより放出品だろう。事情は汲まなくもないが、多少、まからないかねえ」
「いやはや、まったくジャコウネコ先生の眼力にはかなわない」
キヌはすっかり店の常連となっている様子だが、言ノ葉の常識から考えれば非常識だ。どうしてホンネ妖怪であるキヌがうろうろと、町中を出歩いているのか。
「ネコ先生、うちの野菜も見ていっておくれよ」「いい茶葉があるんだ、先生どうだい」
先生、という呼ばれ方からして麝香猫キヌは、中堅の落語家か何かと間違われているように思える。間違われても納得の彼の言動ではあるが、どういう経緯でここまで町に馴染んだのか。
と、キヌが振り返った。キヌの真後ろにまで来ていたツカサは一歩引く。
「人のあとを尾行するとは、良い度胸と趣味だねえ葛葉」
「俺がとっくに来ているのに、お前は買い物に夢中だった」
「気づくように声を掛ければいいじゃないか」
「邪魔をしないようにと思っただけだ。鈴乃音はどうした?」
「我が主は多忙でね」
「また、本人不在で人を呼び出しか……」
確かに舞は、学園でも今週、あまり姿を見せなかった。何か事情があって、学外を飛び回っているらしい。
「麝香猫。まさか鈴乃音じゃなく、お前がメールを寄越してるんじゃないだろうな?」
「私は携帯電話のような文明の利器など持たないよ」
「どうだか」
「おっと、店主。今日は生魚はあいにく買えないんだ。良い物だがまた今度。さて」
「誤魔化すな。何処へ行く」
キヌが背を向けて去ろうとするので、ツカサはその肩口を捕まえる。
落ち着いて、さっとその手を払い、キヌはツカサへと笑んだ。
「葛葉よ、今宵は暇か」
「いや」
「暇があるな?」
「なくはないが」
「良し、では決まりだな」
「何がだ……」
「行こうか、特等席へ」元々、鈴乃音舞に呼び出されたとしてもその用事の終わりが見当もつかないため、ツカサは今日の予定を未定のままにしていた。
そこにキヌが妙な提案をしてくるから、結局駅前から通学路をさかのぼり、横道へ折れ、例の竹林にまで戻ってしまう。
夕暮れの中、足早に竹の群れを縫って行くキヌに従い、渋々とツカサはついていく。
先刻、突如キヌは言い出したのだ。
「我が主・鈴乃音舞の秘密について、葛葉と共有したい」と。
果たして秘密とは何か。
一応聞いてやろうと、ツカサは思った。
けれどキヌが茶会の広間を過ぎ、さらにその林の奥へ奥へと歩を進めていくに連れて、やはり怪しげなことに付き合うべきではなかったか、とツカサに後悔がよぎる。
キヌの行動の意志は、往々にしてその主・舞の意志である。だが夕闇迫るこの林の先に、いったい何があるというのか。
「おい、藪が深いぞ」
足元は暗く、見えづらい。ツカサは一歩一歩、確かめるように足を運ぶ。広間よりも奥の林の中は本当に手入れがなされていないようで、道の痕跡らしきものはあるが、枯れた葉や折れた茎が散らばり、滑りやすくなっている。
平然と、キヌは前を歩いていく。足取りは実に軽やかで、たまに振り返ってツカサに余裕を見せる。その様子はいつもより格段に愉快そうに思えた。
「竹と笹の違いはわかるか葛葉。一般的には縦に高く伸びるのが竹で、横に広がるのが笹だ。しかし、学問的にはタケノコの鞘が生育時に自然に剥がれるものを竹と定義する」
「どうでもいいだろう、そんなこと。どこに向かってるんだよ、これ」
「そうだな。では花火の鑑賞における注意点を教えてやろう。後程な」
「花火? もしや……」
「この道も、かつて我が主が見つけた抜け道だ」
「鈴乃音が昔、ここを?」
「だいぶ昔、幼いある一日のことのようだが」
「例の、俺に似た誰かと一緒に見つけたか」
「そのかつての一日が花火大会の日であったのは、ただの偶然ではあるまい」
大変回りくどいのでわかりづらいが、つまるところ、キヌは花火を見に行きたい、ということのようだった。それで、ツカサを道行きに招いたのだ。
……それならそうと素直に、最初からそのつもりを言えば良いものを。
いや。もしかしたら、舞ならば正直にツカサを誘ったかもしれない。
けれどあくまでもキヌはキヌ。ホンネの裏だ。舞の本心の奥底とは、表れ方が異なろう。
「麝香猫。お前は何事につけてもいちいち理窟や蘊蓄を語りたがる」
「語ることが、私の性分なのでね」
「それはわかっているから、そろそろ本題に入れ」
「本題か。確かに場繋ぎの小話など不要。世の中には真打ちを求めず、無粋を好む者もいるが、お前さんは別だな」
「またいちいち話を小難しく……」
「おっと、葛葉。進むな。止まれ。命が惜しければ」
「何?」
ようやく竹林を抜けると、そこは断崖だった。
知らぬうちに、ツカサはキヌを追い越していた。崖の手前にはごく低い柵というか、土塀が設けられていたが、周囲が暗いため見えず、ツカサはその土塀に引っ掛かってつんのめり、危うく、踏みとどまる。
キヌがすかさず手を差し伸べ、ツカサをこちら側に支え戻した。冷や汗を素知らぬ顔で拭って、数歩下がり、ツカサはキヌと並ぶ。
「改めて。見よ葛葉」キヌが指で示す。
「何があるんだ」ツカサも指を向けた。
夜の闇に混じり、遠い町明かりが眼前に広がっている。
そこに不意に光が上がった。高く、打ち上がる。そしてぱっと開いた。
花火の大輪が、まるで指先に乗せられたかのように、ふたりの目の前に輝く。
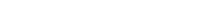
-
眼下には、瞬く町の灯り。眼前には、開く大玉の星。
ここから見る花火の展開は本当に間近だ。
指先を広げて手を伸ばせば、町の灯も、花火も、どちらもそのまま掴めそうなほど、ツカサには近く感じた。
「いやはや。絶景かな、絶景かな。まさしく特等席」
竹林を抜けなければ、この崖淵にはたどりつけない。周囲には誰もいなかった。
キヌは、土塀の上に小さな敷物を置いて座り出す。
ツカサもキヌから自分用の敷物を受け取り、そこに腰を下ろした。
「では葛葉、話の続きだ。こういう打ち上げの、割れ物の花火を見る時に見るべきはまず、玉の座り。上昇しきったところで破裂して均等に色が広がるかどうかが評点の対象だ。競技花火ではとにかくそこから見る。まあ、風流の面で言えばそれ以前に、誰がどう作った花火であるのか、職人の個性を感じるところから物事は始まり――」
「麝香猫、またずれてるぞ。本題に戻れ」
「……うむ」
打ち上がってくる花火玉の始終が見て取れる。
どうやら花火大会の裏手、立ち入り禁止区域の端にこの崖はあった。
「結局、これが秘密とやらなのか。この花火の光景が」
「そうでもあるが」
「他にもあるのか?」
「葛葉よ、我が主・鈴乃音舞のことが気に掛かるであろう?」
「いったい何がしたいんだ、という意味では確かに気になる」
「四六時中、気になるのか」
「そこまでではないが、まあまあな」
大きな花火が目の前に次々に上がるが、音はほぼ聞こえない。
打ち上げ場所と崖との位置関係や風向きのせいらしいけれど、奇妙だった。
「つまりそれは恋だな、葛葉」
「全然違うぞ麝香猫」
「だが主のほうも常々、お前さんのことを知りたがっている」
「……そうなのか?」
「殊にお前さんが何者であるのか、その正体を」
「俺のことを怪しい奴みたいに言うな」
「しかし言ノ葉の使い手。謎めいているのは間違いあるまい。気に掛かるさ」
「謎か……」
そう言われるとツカサには返す言葉がない。何しろツカサ自身にもわからないのだ。
自分の能力がどこからもたらされたのか。
言ノ葉使いは何故力を持ち、使役できるのか。
こうしてホンネの青年・キヌと語り合えている理由も、厳密に考えれば、謎だ。
けれど謎でありながら現実として、今ここで進行している。
「だからな。我が主も今日、本当はお前さんとここに来たかったのだよ」
空にまた花火。二発。続けて三発。時間差をつけ、盛大に、儚く、花開く。しかしやはり、音はない。代わりに、遠くから和の旋律、囃子のようなものが流れてくる。
「鈴乃音は、どうして来ないんだ」
「来るのは無理だった。いや、主自身、無理を選んだ」
「無理を、選んだ? 何故だ?」
「まさに今から、それを話そう」
無音の薄闇に広がる大輪の花々を眺めながら、キヌが語った。鈴乃音家は、茶道の家。
特に珍しい流派で、所謂『侘び茶』とはまったく正反対の対局にある。
豪華絢爛、華美にして、おもてなしに贅を尽くすことを至上とするという。
たとえば茶室は壁一面の金箔張り。さほど珍しくもない唐物茶器を仰々しく眺めて有り難がり、客人の綻びを見つけてもそれを咎めず、無理矢理都合良く解釈し、世辞を使い、小一時間その蘊蓄を語って褒め続ける。
実にくだらなく、つまらなく感じられるかもしれないが、しかしながら。
社交とは往々にして、形式によって他者との交流を成り立たせるために用いられるもの。
ならば本質を直截にあらわすは無粋。建前の羅列を結びつけるが粋。
それがこの流派の主義であり、礼儀なのだ。
昔々の権力者は、暴力的な無駄遣いや悪趣味を展開することで己の権威を誇示し、人々を従え、説き伏せた。この時、絢爛な流派の茶の湯は、大いに利用された。
現在に至っても変わらず一定数、どこかに、この手法の支持者がいる――。「おもてなしの精神ってのは、わかるかい? 他人を楽しませるために、自分を作って振る舞う……」
「大人だな。または芸の道なら、他人のために自分を演じるのは確かに常識だ」
「左様。我が主は茶の湯の家で育ち、芸事へ従事する人に馴染んでいる」
「なるほど……少し、わかってきた」
「だがまだひとつ。お前さんは恐らく大きく誤解している」
「誤解? 何をだ」
「今、鈴乃音舞はどこにいると思う」
キヌが訊いた途端、ひときわ眩しい光が辺りを覆った。天空に花開く大菊。ほんの数秒の間、その輝きが、崖下に広がる花火会場の観覧席全体をうっすらと照らす。
ツカサは崖から眼下を眺めた。
皆が上空を見上げている。が、ツカサは誰かと視線が合った気がした。
誰か……会場のただひとりだけが、打ち上がった花火ではなく、この仄暗い崖上を見つめている。ツカサとキヌがここに居ると知っている相手だ。それは煌めいて派手な、それでいてしとやかな和装をまとっていた。
やがて空の光がおとなしくなって、見えなくなり、消える。
辺りはまた暗く静かに戻る。
「……鈴乃音?」
ツカサが呟くと、キヌが頷く。
「会場の何処か、来賓席で要人のおもてなしをしているはずだよ。そういう役割だ」
「元々、そういう予定だったのか?」
「否。主は急遽、自らすすんでそうした。やってみたかった、やらせてくれ、と」
「実に鈴乃音らしいとは思うけれど、面倒な選択をしたんだな」
「お前さんが女郎蜘蛛を討伐したせいだ」
「とどめを刺したのはお前だ、キヌ」
「そうだな……私、自身だ」
それからキヌはさらに語った。
舞の母が当代の茶道の家元であり、だとすれば次の代は、舞が継ぐようである。
幼い頃から舞は、茶の湯の家の諸事をしなくてはならない立場にいた。
けれども。
「主は長いこと、家で芸の訓練を重ねず、外で遊び呆けていた。何故だと思う?」
「茶道が嫌だったからじゃないのか」
「それが逆だ。逆なんだ、葛葉」
「なんだと?」
「幼い主は茶に興味津々で、無断で茶室に入り浸っては怒られ、追い出されていた」
「どうして追い出すんだ。後継なんだろう?」
「先程も述べたが、この流派は建前重視だからね」――『コドモははいってはいけない』。
鑑識眼や作法は、オトナになってから身につく、身につけるもの。
コドモに茶の良し悪しがわかるわけがない。
わかるフリをしても、どうせそれはママゴト。
だから『あたし』は茶室から放逐された。
まだ早い。これはオトナになってからね、と言われて。
嫌ではなく、むしろやりたかったことなのに。
みんなに無理だろうと決めつけられて、禁じられた。
あきらめきれないけど、だったら今は外に出て遊ぶしかない。
だって『ワタシ』は、まだコドモだから――。キヌは続けて言う。
「つい先日まで、主は実家から幼子扱いされていた。外での行いに何の注意も受けない代わりに、家で学ぶ機会もなかなか与えられず、実力を見てもらう場や、意志を認めてもらうきっかけもなかった」
それが舞の中の『ワタシ』だった。
「家でやりたいことをやらせてもらえないから、主は一時、家から遠ざかっていた。だが、タテマエのバケモノは倒れた。主の気持ちを留める枷がなくなった。そして主はいよいよ、家に訴え、真剣に芸事を学び始めた」
舞は『あたし』を主張するようになった。相手の言い分に従うフリをやめ、自分のわがままを押し通し、苦労することを選んだ。
「だから、なのか……あいつが最近、忙しくなったのは」
ツカサは噛みしめるように言った。また花火が、目の前を照らした。ひとつ、ふたつ、今度は先程より小さいが豊かな、五色の星の瞬き。
「見放されたままでいれば気楽だったろうに、主はその気楽さを捨てて、戦いたがっているのだよ」とキヌ。
「戦うのは結構だが、それで周りを振り回す。勝手な奴だ」
そう口では言いながらも、ツカサに舞への非難の気持ちはなかった。
「主はお前さんと不器用なところが似ていると感じている」
「そうかな?」
「異端の存在で、多少非常識なところも」
「それはどうかな」
「無理解な世間から、得体の知れない奴だと思われやすい点では同類だ」
「そういう見方もあるか」
「そのわがままが、以前は歪んだ形で学園にて表明され、今は奔放に繰り広げられているだろう。鈴乃音舞は少しずつ、人との付き合い方を学んでいる最中だ」
「かもな」
「だから、あまり嫌わないでやってくれ」
隣のキヌが静かに横目で、ツカサをうかがう。
花火大会は、最終の一段に差しかかっていた。空に上がって均整に盆を広げ、星は薄く光り、光っては、消える。
「別に嫌ってはいないさ……」ツカサは言った。「それにしても、色々な花火があるものだな」
「花火のあの光の、消え口は職人の個性が一番強く現れるところだ。見る者の解釈が求められる――」
「喋っていると見所を見逃すぞ、麝香猫」
「ああ、わかっている」
「わかっている、か」
本当はよくわからない。わからないから、どこか不安だ。
それでも、本心で言ったのだと思う。
現実として受け止められるなら、自分のことも他人のことも、決して嫌ではなかった。× × ×
週明け。
月曜日の学園には珍しく、朝方から鈴乃音舞の姿があった。
まだ始業定刻の一時間以上前。
廊下でツカサを見つけるなり、舞はその肩を叩いて横に並ぶ。
「やあ、葛葉。早いね」
「あ、ああ。鈴乃音。お前も随分だな」
この時間、行き交う学生はまだ少ない。ふたりは揃い、並んで歩く。階段を下り、新校舎を出て、旧校舎との間の渡り廊下を行った。穏やかな朝陽が、屋根の隙間から注いでいる。
ツカサには、わずかなためらいがあった。先日の花火の際、キヌから鈴乃音家の事情を垣間見た、もとい、聞いたが、それはキヌ曰く『主の秘密』であるはずだ。
その秘密を知って、舞とどう応対したものか。何か、付き合い方を変えたほうがいいのではないか。ツカサは少し、考える。
「眠たそうな顔してるねー、ってあたしもだけど」
「眠いから、散歩で気を紛らわせてるんだ」
「あんたって朝の散歩なんか、趣味でやってたっけ?」
「別に趣味でも習慣でもない、たまたま偶然だ」
「なんでこんな早く来てんの?」
「やたら早く目が覚めたからだ」
「なんだー、あたしと同じだな」
「そうなのか」
「そうですよ」
ゆっくりとした歩みの中、他愛のない会話。
普段通り。何も変わらないのではないか。変わったとすればそれは、舞が何を考えているのか、余計に勘繰る必要がないこと。以前よりも自分が悩まず、困らないことだろう、とツカサは思う。
ならば気取らず、なるようになれ。成り行きにまかせようではないか。
「そうそう葛葉。こないだごめんねー、なんかうちの召使いというか、男衆が」
「え?」
「花火の日。キヌがさ、無理矢理、葛葉を竹藪の奥に連れてったらしいじゃん」
「そうだが、何か不都合があったか」
「ないの? ヤブ蚊がうるさかったりしなかった?」
「うるさいのは麝香猫本人だ。俺が花火の見方を知らないから、色々とな」
「そんだけ?」
「それだけだ」
「なら、いいかな……って、あれ?」
突然、舞は廊下の途中に立ち止まった。ツカサもそこで止まる。
「なんだ、鈴乃音」
「その背中。なに、それ、葛葉」
「背中?」
「上着の背中だよ。字が書いてある」
「字……」
ツカサは首を捻ってみたが、着たままでは勿論、見えはしない。
仕方なく、羽織っている上着を脱ぎ、その背を確認してみる。だが異状はない。
「何もないぞ。なんだよ、字って」
「だから、書いてあるんだって。あ! わかった、角度だ!」舞が言う。
「角度?」
ひらひらと、ツカサは上着を動かしてみる。そして見つけた。
「……なんだ、これ」
この朝の、斜めの陽光の中でなければ、気づかなかっただろう。
見事な刺繍。
ツカサの上着の背一面に、細かな縫い目が巧みに張り巡らされている。
縫い糸は、布地と微妙にキメが異なる。縫い目も微少な凹凸を持っているため、光の反射加減によって、縫い跡が浮き上がるようになっていた。
浮き彫りとなった文字は、大きくカタカナで、縦に三文字、こう書かれていた。『 マ ヌ ケ 』
「はは、あははは」舞は笑い出す。「あいつ、こういう冗談が得意よね」
「あいつ……あいつ、か」しばし唖然としたのち、ツカサは思い当たる。「縫い物上手の、おせっかい……」
親切の繕いのフリをして、あいつはこんな悪戯を仕込んでいたのだ。
それでいて、まるで素知らぬ様子をしていた。
では、あれもこれも、嘘か冗談だったのか。花火を見ながら話したことも、すべて。
それとも。
わからない。わからないが、ツカサは沸々とした気持ちで拳を自然と握っていた。
「おやおや、主。こんなところに。葛葉も――」
後ろから聞こえた声。ゆるりとこちらに近づいてくる、あいつの足音。きっと舞に渡す重箱を提げて現れただろう、そのあいつの何食わぬ澄まし顔に、この俺はいったい何を言って、どうしてやろうか。
ツカサは考えて、考えて、そして、考える。それから振り向き、上着を投げつけた。
「覚悟しろ、麝香猫」
追えば即座に、猫は逃げる。その逃げ足の素早さは、自明の事実だった。



