空威張りビヘイビア
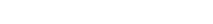
-
早朝。静けさの中に、虫の声が遠く響き始める。
グラウンドには、準備運動をする部員たちの声もこだまする。
通学路を行く者はまばらで、普段なら校門の番人として位置する風紀委員たちの姿も、まだそこにない。
けれど葛葉ツカサは、既に教室へ到着していた。
「さすがに、早く来すぎた……」
まさか、いつもの一時間以上前に登校するようなことがあるとは思わなかった。
この秋も恐らく残暑は酷暑で、午後から灼熱の陽光に悩まされそうであったが、今はどこかから涼やかな風が来て、室内を吹き抜けていく。
「散歩でもしておくか」
ツカサは、自分以外無人の教室を出る。上着は脱いで座席に置いていった。霊力蓄積で冷えやすい体質とはいえ、この時期ならマフラーだけあれば、他はあまり着込む必要はない。ただ学園の校則によって、上着を持参しなければならない季節が決められているのが、面倒といえば面倒である。
階段を下り、渡り廊下をツカサはゆっくりと行く。渡り廊下は旧校舎と新校舎の境にあり、長細く折れ曲がりながら、両建物を結んでいる。
歩きながら、思い出す。
ここから見える中庭では、三鹿ナルキがチョコレートの洪水を起こしかけたことがあったし、その奥にある階段は一度、餓鬼ちゃんの放出した飴玉で埋まったことがある。
ちょっとしたアクシデントで鹿乃川律が吊られたことのある旧校舎正面の窓の桟は、今も一箇所だけ曲がったまま放置されていた。
旧校舎にいくつかある空き部屋のひとつは元々は調理実習準備室で、そここそは先日、鈴乃音舞から現れた女郎蜘蛛との戦場になったところだった。
噂によれば、準備室の隅に忘れられていた古い小麦粉の大袋やベーキングパウダー、ドライイーストなどがごっそり消失したそうだが……それらは恐らく蜘蛛の出現と退治に伴い、消えてしまったのだろう。
これほど色々な騒動を引き起こしておきながら、ツカサへのお咎めはない。勿論、ツカサの言ノ葉能力が、学内のさまざまな謎の事件と関わりがあるとは、およそ誰にも想像も付かないことなのだけれど。
一巡して、渡り廊下を戻り、ツカサは教室に帰る。
早起きしすぎたので少し眠い。
時刻を見誤って家を出たのも要因ではあるが、ツカサが今朝早く登校することになったのは、純粋に普段より早く目が覚めたからだ。
スマホのメール着信音に、叩き起こされていた。
そのメール文面をもう一度確認しようと、履歴を繰る。『急ぎの用事があるから、なるべく早く学校に来なさーい☆』
……先程の散歩がてら探してみたものの、案の定、鈴乃音舞の姿は校内になかった。
いったい何の用だというのか。
さらには急ぎだと言いつつ、肝心の用件がわからない。
それなのに呼ばれて素直にやってくる自分も大概だ、と、ツカサは声に出さないまま、ぼやく。舞の普段の登校時間は遅めで、むしろ遅刻の常習犯だ、と律から最近聞かされたばかりだ。
が、
「なんで上着がないんだよ」
ツカサは異変に気づいた。座席に置いてあったはずの自分の上着が、消えている。
自分でも気づかないうちにカバンにしまったのだろうか、と一旦開けてみる。しかし、見あたらない。
机の下にもないし、椅子の陰にもない。幾度確認しようが同じことだ。室内から廊下にかけて吹いている風は微風であり、風に飛ばされたわけでもなさそうだった。
――俺の上着は、盗まれたのか?
何故。いったい誰が。いや、そんなことをしてなんになる。
廊下へと出て見回す。そして気配をうかがう。ツカサは何か違和を感じていた。この静まりかえった校内に漂う、ちりちりとした微弱な雑音の感触。
ツカサは、この感触に覚えがあった。
――『あいつ』か。
心当たり察して、廊下へとツカサは走り出す。あいつは和装である。それならば学内でも、畳張りの部屋を好みそうに感じた。「案外早く、私の居場所に気がついたな葛葉」
新校舎の隣、体育館に付随してある武道別館。その剣道場の只中で、麝香猫キヌは正座をし、縫い物をしている。
ツカサが駆けつけてきたのを見て、しれっと一瞥と薄笑いをくれ、縫う手は止めない。
手縫いで、せっせせっせと糸を繰り、針を潜らす。
「おい。返せよ、上着」ツカサは不機嫌そうに言った。
「そう慌てなさんな」
キヌが縫っていたのは、ツカサの上着の背。襟の小さなほつれだった。
「そんなもの、放っておいていいだろう。それを勝手に」
ツカサは歩き迫って上着を取り上げようとするが、キヌはくるりと身を翻して避ける。
「違うね。これは小さな親切などではないんだよ。日頃からのお前さんの身だしなみが、みっともないから、直しているんだ」
「大きなお世話だ麝香猫」
「世話になってる自覚はあるようだね葛葉」
「だいたい、なんでお前が学校にいるんだ。鈴乃音は来てないだろう」
「おや、我が主はまだ登校していないのかい? 私が先についちまったか。それは困ったねえ。主が忘れていったお手製弁当を届けに来たんだよ、私は。縫い物はついでだ」
「ついででやるくらいならやるなよ」
「しかし頼まれなくてもやっちまうんだねえ、これが。言っただろう、みっともないから直していると」
「今後も絶対に頼まないからな……弁当、だと?」
キヌの後ろ背に、重箱の包みらしきものが置かれてあった。結構大きい。三段重はあるだろう。
……そんなものを本当に、舞が平らげられるのだろうか。
「どうも嘘くさい」
「嘘なものか。ほれ葛葉」
キヌは手早く糸の末端を玉留めして仕上げ、ツカサに上着を突き出して寄越す。
引ったくるようにツカサは受け取った。
縫い口は見事で、ほとんど元の生地と見分けが付かず、また頑丈だった。
「一応ありがたいが、どういう魂胆なんだ?」
「礼は素直に言いたまえよ葛葉」
「ありがたい、が、何を企んでる、麝香猫」
「何も企んでなどいないさ。おっと、名誉のため釘を刺しておくが。これは私が私の判断でやったことであって、決して、主の鈴乃音舞の差し金ではないよ」
「わかった、わかった」
追求するのはやめ、ツカサは上着を提げて部屋を出る。
キヌはそのまましばらく、畳の上でたたずんでいるようだった。
あまりにしつこく回りくどい言い方をするキヌの様子に、ツカサは何か感じ取った。
キヌの行動は要するに、代理なのだ。
どういう思惑かは知らないが。鈴乃音舞が何かしようと考えるかわりに、キヌが朝から、単独で姿を現したのだろう。
ただし舞本人は不在。恐らくは後々、何食わぬ顔で堂々と遅刻してくる。
剣道場の外、学園の裏庭では笹の葉がざらざらと揺れていた。 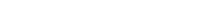
-
鈴乃音舞がその日登校してきたのは、よりにもよって昼休み直前。
やがてチャイムが鳴り、廊下に出てきたツカサを見つけると、舞は朗らかに挨拶する。
「あ、葛葉おはよー」
「お前な……結局、今朝のメールの件はいったい何だったんだ?」
「メールって何? 葛葉にメールなんて、あたし、したっけ?」
「えっ」
「それよりまた茶会をするわよ。今日の放課後。葛葉、逃げるなよー?」
ツカサに指を向け、きゃらきゃらと笑う舞。
そのうち、やってきた幾人かの取り巻き後輩女子たちに囲まれつつ、舞は昼食を取りに去って行く。
「さあ参りましょう、舞お姉様」「わたくしが食べさせてあげますわ」「あら、卵焼きは私と折半する約束ですのよ」――。
女子たち。どうして舞の取り巻きは男子から女子に変わっているのか。
いや、ツカサにはわかっていたが、それでも、ため息が出る。
舞は言動で人目を惹く。そこは以前と何ら変わりない。
かつての舞の、偽の性格を信奉していた大勢の男共は、離れていった。
代わりに、新たな舞のわがままで奔放な、堂々たる態度を支持する一部の女子が集まってきている。
女郎蜘蛛撃破以降、舞本人だけでなく、舞の周囲も明確に変化していたが……根本的なところは何も変わっていないのかも知れない。
舞を囲む人は、彼女の賑やかに飾り立てられた雰囲気を好んでいるのだ。
「しかし要するに、あれはみんなで食うつもりなんだな」
ツカサは気づいた。遠ざかっていく舞の手には、三段重が包まれた大きな風呂敷がさがっていた。それは今朝方、麝香猫キヌが持参していたものと同じものだった。
確かに、キヌが言ったとおり。嘘ではなかった。放課後になる。
舞は早々に取り巻き女子たちを置き去りにし、昇降口で発見したツカサを捕まえ、引っ立てるようにして通学路を行く。
「で、今日は俺をいったいどんな酷い目に逢わせる気なんだ?」
「失礼ねえ、ごちそうするって言ってるのに」
ツカサは舞に引っ張られ、竹林へと入った。通学路からひとつ横道に外れたところに、この竹林は存在した。その中を少し進むと、竹が少なく整った芝の生えた広間があり、それはさながら小さな公園のようで、しかし他の人間がここを訪れることはまずなく、貸切の気分が味わえる。
「そう言いながら、前回は雑巾の絞り汁みたいなものを飲ませようとしただろ」
「ちょっと濃い口のブレンドだっただけでしょ?」
「前々回は、草の出汁みたいなのが出てきた」
「摘みたての花のお茶はそういうものなんだってば……ああキヌ、準備いい?」
「では主、僭越ながら」
先んじて広間に到着していたキヌが宣言して番傘をひと振りすると、どこからともなく、とん、ととん、と小鼓を打つような音と共に椅子とテーブル、和洋の茶器一式が載ったワゴンが、場に整然と現れた。
同時に召喚されたポットには湯が満たされ、口から湯気が立っている。
手慣れた様子でキヌはカップをワゴントップに並べ、湯でひとしきり濯ぐ。
時勢を問わず、必要な道具を瞬時に用意し、さまざまな作法で茶を入れることができる――これがホンネ妖怪青年・麝香猫キヌの持つ特殊能力。女郎蜘蛛撃破後に判明した、能力だった。
「はい、着席ー」
舞に無理矢理勧められ、ツカサは椅子のひとつにつく。
「妙なものを出されても、俺は飲む気は」
ツカサの顔には困惑が浮かぶが、
「今日の一杯はもしも買ったら結構お高いのよ、希少品だからあらかじめキヌに調達を頼んで置いたんだけど」
隣に座る舞は、まったく意に介さない。
「無事に用意できて良かったよ。主」
対面にいるキヌも茶道具をいじりながら、涼しい顔をしている。
「だから何を用意したんだ」
「飲んでのお楽しみよ葛葉」
「楽しみだねえ、お前さん」
「俺はあまり楽しくないが」
企みの程度はわからないながら、相手が何かを企んでいるのは明らかなので、ツカサは渋い顔にならざるを得ない。
「それにしても鈴乃音、どうしてこんな場所を知ってるんだ」
座席から見上げれば、そこには丸く切り取られたように空がある。
ふとツカサは、薄く流れゆく雲が空の色を少しずつ夕闇に染めるかのような錯覚を感じた。心が落ち着くような、それでいてざわめくような、不思議な感覚だった。
「気のせいじゃないと思うから訊くんだけど」
テーブルのスティックシュガーを指先でくるくる回しながら、舞が唐突に切り出す。
「何の話だ?」
ツカサは半ば上の空の気分だが、それでも雲を眺めながら耳を傾ける。
「葛葉って、学園に来るよりも昔に、あたしに逢ったことないよね?」
「ない」
妙な質問だったが、ツカサは舞に即答した。
「だよね。ただまあ、思い出したんだ。あたしがまだちっちゃい頃にさ、知り合いに、葛葉に似た感じの子がいてさ」
「……俺に、似た?」
「この竹林の中の広間は、その子に教わったというか、一緒にたまたま発見したのよ」
「ほう」
「だいぶ前の話だよ。あたしが幼いお嬢ちゃんだった頃の」懐かしんでいるのか、舞も空の雲を見上げる。「印象的なお坊ちゃんだったなー。おとなしくてかわいらしくて、でも、なんというか、しゃんとしてるっていうか、きちんとしてて。なんかあれこれ色々詳しくて、物知りだった」
「でもそれ、どう考えても俺じゃないよな?」
「うん。もしあれが葛葉本人ならさすがにあたし、再会した瞬間に気づいてると思う」
「俺も事前にお前に逢ってたら、気づかないはずはないと思う」
舞はなかなか強烈な奴だし、ツカサも自分は平凡ではない存在と考えている。過去に接点があれば、恐らくお互い覚えていないはずはない。
「その子と葛葉、顔の造作以外は似てないから、あんた本人ではないはず。雰囲気も性格も違うし、何より髪の色が全然別だし」
「他人の空似か」
「だと思うねー」
「しかし、そいつは何者なんだ?」ツカサは少し、気に掛かって訊く。
「それがね。妙なことに、わからないのよ」舞は首を傾げた。
「わからない?」
「大事な来賓の子と聞いたんだけど、あたしもその日、一日だけしかその子と一緒にいなくて。それっきりだから。名前もわからない」
「ふむ……」
「ていうか、むしろ葛葉のほうが、その子に心当たりない? もしかして親戚とか」
「……ないな」
「そっか。知らないか。まあ、あたしが覚えてる限り、良い思い出だよ。相手のことが嫌なら、きっと忘れてる」
「かもな」
そのうちに匂い立ってきたのは、どうやらドリップされたコーヒーである。キヌがサーブの用意を調えていると、何やら電子音が聞こえてきた。
「ああゴメンあたしのケータイだー、もしもっしー☆」
舞がおどけた調子で携帯を胸ポケットから出し、通話する……が、徐々に舞の声のトーンが落ちていった。
「……仕方ないですね。でも、ここはあたしに対応させてください」
誰と話しているのだろうか。舞の口調はまた、ツカサが聞いたことがない調子になっている。以前の男共を従えていたものとも、最近の女子を喜ばせるものとも違う、真面目で固い印象を感じさせた。
通話が終わった。
「呼び出し食らったから、少し席を外します。んじゃキヌ、よろしく」
「御意」
舞は立ち上がり、キヌに場を預ける。通学鞄を鷲掴み、足早に竹林を出て表通りへと向かった。
ツカサはそのまま、竹林の中の席に残される。いや、まったく場に残る義理はなかったのだが、キヌがもう自分用のカップを目の前に置いて注ぎ始めているため、席を立ちにくい。
「主が戻るまで、ゆるりと話でもしようか葛葉」
キヌも、ツカサの差し向かいの席に着く。ふたりだけの茶会が開始された。
「…………」
コーヒーカップに控えめに注がれた琥珀色の液体は、濁り無く上品な輝きを放っていて、清廉な雰囲気を醸し出す。
しかし、ツカサの飲む手が進まない。カップを持ち上げたまま、液面を睨んでいる。
「仮に毒はあっても控えめだが」とキヌ。
「あるのかよ、毒」ツカサは呆れる。
「失礼な。無害だ。飲めばわかるだろう?」
「人にものを飲ませるなら、もう少し言い方を考えろ麝香猫」
まさしく渋々という渋い面構えのままツカサは、ぐいっとカップをひとあおりした。
本当に飲んで良いものなのか疑っていたし、コーヒーだし、苦かろう、と思っていた。
だが、ツカサの顔色が変わった。
「おや」
この一杯の飲み口はすっきり。存外さわやかであった。やや酸味の薄口なのに、複雑なコクが潜んでおり、じんわりと沁みる。
「なんかこのコーヒー……独特だな」
「ほほう。飲んだか葛葉。そして、その顔つきからして」
「いけるな……」ツカサの表情から、渋みや苦味が消えていた。「俺、コーヒーはそんなに得意じゃないほうなんだが、これは、うまい……気がする」
「その価値がわかるのか、お前さん」
「多少は」
「珈琲好きでもこれを飲む機会はなかなかない。至上の贅沢を楽しむがいい」
キヌは静かに笑んで、自分のカップに手をつける。微風が抜け、ざらざらと鳴る竹の葉の広場に、そのコーヒーの香りがうっすら立ちこめる。
「これってどういうコーヒーなんだ?」
「聞きたいか?」
「あ……いや……」
なにげなくキヌに質問してしまってから、ツカサはしまった、と後悔した。
素朴な疑問ではあったが、今聞くべきではなかった。
「そうだろう、知りたいだろう、ならば語らんでもない」
けれどキヌは待ってましたとばかり、いきなり饒舌の構えとなる。
思えば先日も、その前も、あの蜘蛛を倒した直後の最初の茶会からして、キヌはそうだった。茶の点て方、茶葉の種類、茶碗の変遷などなど、どうも蘊蓄語りが好きらしく、それもわざわざ、普段無いような奇妙な抑揚で、勿体付けて仰々しく語るのだ。
「お前さんがそいつを飲み干す前に、この珈琲、コピ・ルアクに用いられている特別な発酵豆の製法を教えてやる」
ああ、始まった。ツカサはだんだんと眠く、半目になりながらも一応聞く。キヌは澄ましているが、それでもやや得意顔だ。それほどまでに、話したかったのか。
「熱帯のインドネシアという国には野生のジャコウネコが住む。こいつの顔は細長くてまるでイタチだ。気性が荒くてほとんど人には懐かない生き物……だが香料を取る目的で、わざわざ飼育されることもある。さておき野生のジャコウネコは、珈琲の実を好んで食べる。野生の勘で、よく熟した実を嗅ぎ分けるようだ。きっと人の手で珈琲豆を選別するよりも、余程優れた嗅覚を持っているんだろうね……そしてジャコウネコの食後に落ちているフンから摘出された豆をよく洗って加工すると、ネコの腸内細菌で程良く発酵された、この珈琲豆になるというわけさ。さまざまな種類の豆が自然と程良くブレンドされていて、これもジャコウネコの高いセンスを感じさせるね。どうだい。手間が掛かってるだろう? だから残りもよく味わって飲むがいい」
「はあ」
やはり、とツカサは改めて思った。聞くべきでは、なかった。いくら良い物でも、こうまで語られたら続きを飲む気が失せる。
「ところでいっぽうジャコウネコからとれる香料は霊猫香、シベットとも呼ばれ我が主も好むところで、こちらの主な産地はアフリカ・エチオピアだ。そしてエチオピアの飲料といえば――」
キヌの話は続くようだが、ツカサの耳にはもう聞こえない。「ああ、間に合ったかな。ゴメンゴメン。どう葛葉、それ。おいしかった?」
日が暮れる少し前になって、竹林の卓に舞が戻ってきた。
急いできたようで、少し息が弾んでいる。
「飲んだが、味は思い出せない」
ツカサはカップの中の、残りわずかな液体を見つめていた。
「えっ、そんなに嫌だったの?」と舞。
「いや、まずくはなかった……」ツカサは肩をすくめる。
「む。申し訳ないが時間切れだ。片付けさせて頂く」
キヌが言った途端、茶器や卓、調度品一式が、宙に溶けるようにして消滅した。キヌの額に一滴、冷や汗が浮かんでいる。茶会を継続する能力には限界がある、ということだろう。ツカサが手に持っていたカップもその中身も消え、ついでに座っていた椅子も消えたが、幸いツカサが尻餅をつくことはなく、まるで誰かに丁重に案内されたかのように、自然と立ち姿勢になる。
今回の茶会は終了した。
「せっかく主に戻ってきて頂いたところで恐縮ながら、解散だ」
「いいよキヌ、気にしないで。例のコーヒー豆、元々量も少なかったし、日持ちもしないし」
「うむ。だが葛葉には堪能させた」
「だったら良し。じゃあ、帰るか」
そそくさと会場を去ろうとする舞。
けれどツカサは若干、腑に落ちない。
「鈴乃音、お前が飲みたかったんじゃないのか?」
「ん?」
「今日のコーヒーだよ。特別に、用意したやつなんだろ」
「そうだけど、いいじゃない。またの機会に期待よ期待」
くるりと背を向けて、キヌを連れ、舞の姿が竹林からまた遠ざかっていく。
ツカサはしばらく、薄闇の向こうへ見えなくなるまで、その後ろ姿を見送っていた。
まったく、どういう了見なのか。
自分の遊びに強引に人を付き合わせているかと思えば、我関せずとも取れる態度で。
どうしたいのか。今ひとつ掴みかねて、だから少々、気に掛かる。


