空威張りビヘイビア
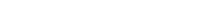
-
何を俺は迷っているんだ? 何をためらう?
遠慮も逡巡もする必要がない。他人のことなど知るものか。
俺には能力がある。今すぐ、己の術を使い、事態を解決すればいい。 そのはずだ。なのに。
深刻な状況にありながらも、ツカサはいっこうに手を出せずにいた。
異彩の毒霧によって、身体は痺れ、目が霞む。しかしツカサの視線の先に、霧を放つ奴の姿がある。
突如、この学園の自分の教室の只中に現れた、怪異。タテマエのバケモノ。
鬼カベ、と称すそのバケモノは、たちまちクラスメイトを毒に侵し、眠らせ、そして鬼カベ自身の生成する有刺鉄線の結界へと、クラスの皆は閉じ込められていった。
教室いっぱいに張り巡らされた、膨大な棘の鉄条網。
渦巻く網の中心に囚われているのは、狗谷愛だ。
狗谷愛の感情と言葉があのバケモノの由来だと、既にツカサはわかっている。毒気に満たされたこの悪しき空間を打破するためには、戦わねばならない。それもツカサは、熟知している。
戦うすべを、言ノ葉の術を、ツカサは体得している。
戦って勝てば、それで終わる。戦い慣れたツカサにとって、難しいことではない。
だが……
「ようやく出てくれたね、さあ、来て。私を捕らえて、そのまま連れて行って」
そう、狗谷愛の口からバケモノに対して、弱々しく発せられるつぶやきが、ツカサの判断を押しとどめていた。
愛は鬼カベに身を委ね、自ら進んで虜となり、鉄線に縛られ、絡め取られている。さながら鬼カベが、愛のことを人質を取っているかのよう……にもかかわらず、それは愛自身の望みだ。
だとしたら、『言ノ葉の術における法則』が乱れる。
人の建前と本音の区別がつかず、あるいは逆転してしまえば、言ノ葉は正しい効果をもたらさない。タテマエのバケモノを打ち破れるのは、同じ由来者を持つホンネの妖怪だけだ。
ツカサの呼び出しに応え、狗谷愛を由来として、少年妖怪・狗呂(クロ)は確かに現れた。けれども、
「どうすればいいの……ぼくは愛を助けたい、それなのにチカラが出ないんだ!」
狗呂少年は戸惑い、叫ぶ。
鬼カベは延々と教室を占拠し、そこに佇んでいた。こちらを積極的に襲ってくるわけではない。だが周囲に漂う毒気と鉄線は、ツカサと狗呂を追い詰め、眠るクラスメイトたちを苦しめ、そして何より、愛の寿命をも縮めている。
黙って指をくわえているわけにはいかない。
「落ち着け。できることがあるはずだ」
窮地のツカサはひたすらに考える。
敵に勝つための手立てを。状況を解決するための方法を。
囚われたあいつを救い出す手段を。
ほんのわずかでもいい。この場に光明をもたらすものが欲しかった。
そのために、今ここに至る経緯を思い出す―― 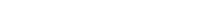
-
その日の朝、ツカサは窓の外を見ていた。
晩春の風が廊下を渡り、窓を吹き抜け、校庭へと流れていく。
学園での、代わり映えのない平穏な風景。
自身の存在を特段にひけらかさない、無愛想な転入生であったツカサも、既にすっかりとクラスに馴染みきっている。
ツカサが日々、年中を通してマフラーとヘッドフォンをつけたまま生活していても、いちいち気に留める者も、注意を勧告する者もおらず(風紀委員の律だけは相変わらずだが)、どういうわけか教師からも何の咎めも受けず、だから、自由を標榜する古い名門校などというものは案外といい加減なのだな、それが『自由』か、とツカサは思う。
ならば自由を謳歌しよう。
奇異な体質と能力を持つ自分でも、普通の学生生活を送れるなら、それでいい。
取り立てて言うまでのこともない、何の変哲もない学園の一日が、今またひとつ、始まろうとしている。そのはずだった。「おはよー葛葉」
隣の教室の窓から鈴乃音舞が顔を出した。
「おう」「眠そうだね」「お前もな」日課になりつつある、他愛のない挨拶。
「葛葉、放課後どうせ暇でしょ? あたしと、付き合ってよ」
舞はツカサに微笑みかける。企みを含んだ、いたずらな笑いだ。
「今度は俺にどんな酷いものを飲ませる気だ、鈴乃音?」
「違うって! 話、聞いて欲しいんだけど」と、舞の表情がふと変わる。「ねえ葛葉、ふたりで会えないかな」
「お前、茶道の修業で忙しいんじゃなかったのか」
「だから! 忙しい合間を縫いつつ、真面目に頼んでるつもりだけど?」
「話なら今言え、ここで聞く」
「まったく、もう! じゃあ、言うけど――」
聞けば最近、麝香猫キヌの様子がちょっと変、らしい。
舞が呼びつけても、何故か学校に現れない。確かにツカサも数日の間、彼の姿を見なかった。
もっともツカサに言わせれば、元々キヌは噺家気取りの変人、であるわけだが。
そうではない、そういう『変』ではない、と舞は言い募る。
普段の裁縫や弁当作りを休んで、毒舌も減り、家で寝ている、らしい。
「キヌにだって、調子悪い日があるんだろう。風邪みたいなものだ。そのうち治る」
ツカサがあっさりと返すと、些か不服ながらも舞は頷く。
「そう? ……なら、いいか」
「あんまり心配が続くようなら、後日改めて、相談に乗る」
「うん。葛葉。ありがと。お礼に今度、デートしよ☆」
「からかうな。なんでそう、お前は俺に構うんだ」
「バーカ。理由なんてないって。ただ、あたしがしたいだけ」予鈴が鳴った。舞は窓の向こうに引っ込み、ツカサも、自身の座席に戻った。
「なんか、匂わない?」「なんだろ」「ハンバーガー?」
クラスメイトの数人が、ひそひそと何事か話していた。
この時、異変の予兆に気がついておくべきだったな、とツカサは後に思い返す。

-
そして瞬く間に、学園の夕刻が訪れた。
臨時の、教員会議でも開かれているのだろうか。担任教師の到着が随分と遅れているようで、ホームルームはなかなか始まらない。教室はだんだんと騒がしくなり、そのうちに席を出歩く者や、終業を待たず早退する者も現れ始める。ツカサのクラスのみならず、隣のクラスも、別の学年でも、全校において、この日は同じ傾向のようだった。
「ツカサツカサツカサ、一緒におやつを食べよう」
鈴乃音舞とは逆隣のクラスから、今度は三鹿ナルキがツカサの座席にまで押し掛けてきていた。
「いいけど虫歯には気をつけろよナルキ、油断大敵。で、何を食わす気だ」
「ショートケーキ。ホールで」
「えっ?」思わずツカサは驚く。ホールサイズのケーキが食べきれないからではない。あの駄菓子マニアのナルキがケーキを食卓に上らせたことが、今まで果たしてあっただろうか? 意外に過ぎた。
「たまには、みんなで外に食べに行くほうがいいかな、って思ったんだよね」
「どういうことだ?」
「みんなだよ。仲間、仲間」
ツカサは怪訝な顔をしてしまうが、ナルキの周囲には、男子学生が幾人かついてきていた。そこにはかつての不良の輩の一部など、ツカサの見知った相手も混じっている。
鹿乃川律を由来とする妖怪のナルキにも、友達がいつの間にか増えているのか……
「さあ! ツカサもみんなも、虫歯仲間になろう! いいよね!」
芝居がかったナルキが高らかに宣言すると、
「いいよね!」「今すぐ出かけちゃおうぜ!」「ああ、出発だ!」
やんやと、これまたわざとらしい歓声をあげてみせる、愉快な仲間たち。
あんたたち、仲が良いんだな。本当に、やれやれだ。ツカサは呆れながらも、
「大勢でぞろぞろつるんでいくのは好きじゃないが、今日だけだぞ」
付き合ってみることにした。ツカサはすぐさま下校の支度をととのえ、一度首から外していたマフラーを手に取り直し、座席から立ち上がる。
けれど、ふと、普段は気にならないことが、突然、気に掛かった。教室を出て廊下に向かう、その途中。
斜め前の座席にいる、ややおとなしい感じの女学生。
教室の壁の時計を睨み、そしてその時計と自身のスマホ画像とを交互に見つめながら、何やら深刻な様子で顔をうつむけている、彼女。――これはいったい、誰だったか?
今まで、ツカサはこのクラスメイトの存在を気に留めたことはなかった。地味ではないが、目立たない人物だったと思う。
だが最近、この学園内ではない町中のどこかで姿を見かけたような覚えもあった。
「ま、ホームルームはサボりだな」「担任に見つかると面倒だ、さっさと行こう」
わらわらと、ナルキの仲間たちが先に進む。すると、
「痛っ」
仲間の誰かが机にぶつかった。件の彼女の机が、座席が、衝撃で、ずれた。
かしゃん、と冷たい音が床を叩いた。
彼女の手から、持っていたスマホが落ちたのだ。
「…………」
おもむろに、彼女が立ち上がっていた。
仲間たちはナルキとツカサを置いて、既に教室を出、廊下に向かっていた。
その仲間の後を追うナルキ、そしてツカサは、仲間の代わりに彼女から、非難の視線を浴びる。
伏せがちな目ながらも、彼女は鋭く、ふたりを睨みつけてくる。
態度は物静かではあったが、ふつふつとした怒りを湛えているのを感じさせた。
「ごめんね」と仲間の代わりにナルキが、彼女に軽く頭を下げる。
ツカサも……自身には本来関わりのないことだが、彼女の感情を落ち着かせたくて、言う。
「悪気はなかったんだ」
次の瞬間。
だん、と彼女の平手打ちがツカサの頬に飛んだ。
その平手は、ツカサの顔面にまともに当たりはしなかった。痛みなどなかった。
が、平手はツカサの身につけているヘッドフォンを掠め、マフラーを弾き飛ばした。
さらに突如、彼女が叫んだ。「いい加減にしてよ! 邪魔だと思ってんでしょ! でもそっちも邪魔なんだよ! どうせ誰も! お前も!」
教室の空気が凍り付く。ツカサの耳にも、その彼女の叫びが響く。
「ひゃああ!」ナルキが慌てふためき、廊下に走り去る。
だが、何故だ?
ツカサは彼女に殴られた理不尽よりも、この彼女の唐突さ、不自然さを思った。
こいつはどうして、いきなり、そんなに怒っている?
ただ今この場で不愉快を感じたからじゃない、何か他にも、以前から理由が――、
そう、ツカサが思ってしまった。
だから、だろうか。
即座にツカサの体質が、彼女の思念を、言葉を、強く感じ取り、反映する。
言ノ葉の陰の発動。負の顕現。
それまで表に現れることが決してなかった、彼女の心の奥底に宿っていた深い恨みとつらみ、つまりバケモノの気配が、ツカサの身体を通じて急激に膨らみ、たちまち、張り裂けた。
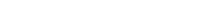
-
突如の出来事だった。
窓からの風が、びたり、と止まる。
学生ひしめく教室の真っ只中に、タテマエのバケモノは出現した。
放課後の楽しみにあれやこれやと思い巡らせていた皆は、一転、騒然となる。
天井を掠めんばかりの巨体。緑色の包帯をぐるぐると巻かれた、浮かぶダルマのようなバケモノ。
その威容と異様な迫力、それの放つ障気と毒気。
そこから伸び出した、幾つもの鋭い切っ先を持つ、触手、棘の鞭。
目にも止まらぬ速度で無数の鉄線が、教室いっぱいに広がり、満ちた。
割れんばかりの悲鳴と絶叫がこだまする。鉄条網が、有刺鉄線が、彼女を囲み、周りを阻む。
そしてツカサはようやく、彼女が誰なのかを思い出していた。
先日、町のハンバーガーショップの裏口で見かけた、作り笑いを練習していた、制服姿の彼女。
あいつだ。狗谷愛だ。
けれど、何故だ? 何故俺は気づかなかったのか?
怪異の気配をはらんだ狗谷が、これほどの傍にいても、まるで予兆を感じなかった。
もしや日常に埋もれている間に、怪異に対する勘が鈍ったか。
それとも。
これまで誰にも知られることもなく狗谷愛の中で強力に抑え込まれていたモノが、平手打ちというキッカケから、ひと息に形を得てしまった、ということなのか――
ツカサは、歯噛みした。
己の言ノ葉使いとしての、優れすぎた体質のことを。
言霊にて自在に妖怪を操る術を使える一方、害を為す隠れた怪異を呼び出してしまうこともある、この身を。
怪異に近しい人物への、直の接触は危険だ。だからこそツカサは普段から、マフラーとヘッドフォンを着込んでいた。それなのに。
「いや、考えるな。敵が現れたなら、戦うだけだ」
後悔はしまい。それより、この事態に挑まねばなるまい。
逃げ惑うクラスメイトをよそに、ツカサはバケモノを見据える。しかし。
教室のパニックは、ほんの十数秒ののちに、不気味なほどの静けさへと変わった。
無風の教室内へと充満された、怪異の毒気により、クラスのほぼ皆はその場に倒れていき、黙り、眠る。皆、バケモノの手により教室の片隅へと集められ、鉄線で造られた境界へと隔離され、次々に閉じ込められていく。
今、教室内で自由に動けるのはツカサと狗谷愛、ふたりのみ。
改めてツカサは、教室を支配占拠しているバケモノ――狗谷愛を由来者とするタテマエの怪異へと対峙する。
ご丁寧にもバケモノは、教室の机を綺麗に周囲に退け、戦いの場を設けるかのように広間を用意していた。
広間の中心に取り残されたようにして、狗谷愛が項垂れたまま、立っている。
「鬼カベ」と、愛がつぶやいた。「やっと出てきてくれたね」
バケモノがぴくりと反応する。由来者から、その名を呼ばれたのだ。鬼カベ。それが奴の名か。
続けて愛が、その鬼カベに向かい両手を広げ、差し伸べる。
「さあ、来てよ。私を捕らえて」
その言葉を聞き、まるで鬼カベは首肯したかのようであった。
無数の糸が、鬼カベから放たれる。すぐさま編まれて網目となり、組み合わさった板となり、渦と巻かれていく、鋭く光る鉄の糸。
ゆるりと、数々の有刺鉄線が蠢き、優しく、けれど確実に、愛の腕と足とを捉え、取り囲み、囚われの身としていく。
さながら未知の生き物の、繭のように。――だから、何故なんだ。
ツカサは鬼カベ退治の手段を考え始めるが、狗谷愛の様子がおかしいことにも気づいていた。
あの鬼カベ。由来者から出でた、タテマエのバケモノ。
由来者の建前の心情を元とするそれはつまり、由来である愛にとって望ましくないモノの象徴、自分を苦しめているモノの現れ、トラウマの実体化。そのはずだ。
それなのに――
「私を閉じ込めて。もう頑張らないから。もう、どこにも行かないから」
愛は鬼カベを自ら呼び、その行動を促す。
鬼カベは愛を鉄線で取り込み、包んでゆく。
結界の如くに厚く張られた鉄条は、愛の身を他者から守るためにあるようでもあり、だが、その尖った棘は明らかに、愛の身を蝕み、傷つける。
「マズいな、侵食を受けている……」
棘に刺され、やがて愛の体色が禍々しく変わっていく。
いや、よく見ればそれは、棘の傷を受けたからではない……むしろ鬼カベという怪異の放つ『毒によって癒され』ることで、狗谷愛は人ではない別の何かに少しずつ、だが、刻々と、変貌していた。
愛は、苦しんでいる。侵食の痛みは常人に耐えられるものではない。
けれど自らその苦を望み、受け入れ、あるいは、諦めているようだった。
どうして、自滅を求めるのか?
「くっ……せめて責めるなら俺を狙え、バケモノめ!」
ツカサは悪態をつき、挑発を試みる。
けれど鬼カベは黙々と結界を作り上げ、ただただ、ツカサの接近を阻む。
どうにか、ツカサは術を行使しようと思って扇子をかざしてみるも、思考は乱れ、集中が途切れる。手は震え、狙いは定まらない。
「いったい、どうしたんだ……俺自身も」
怪異の毒気にあてられているとはいえ、あまりに思うようにならない。ツカサは自らへの異変も感じていた。
手にした扇子が熱を持ち、しびれるような違和感。
何かが自分を、強力に押しとどめている。
「あいつの……狗谷愛の持っている、心の矛盾が大きすぎるのか」
ツカサは、自分の使う言ノ葉の術の弱点を意識する。
言ノ葉の術は、自他の言葉と言霊をもって力とするものだ。由来者の心からの意志を汲み、ホンネの妖怪を導き出してこそ、初めて、自在な戦闘ができる。
なれど逆に、もしもタテマエのバケモノの活躍を由来者が望んでいるなら、言ノ葉使いがホンネを使役して戦うことは、極めて難しい。
囚われとなった愛は、ぐったりとして、動かない。
愛の本意がわからないため、ツカサは迂闊に言ノ葉の術を駆使できない。
心の望みが呪いに変わるような、術の反作用、逆効果となる恐れがあった。
それでも。
「だからと言って、黙って見ていられるか」
タテマエのバケモノと融合してしまえば、人はもはや、この世の人ではいられなくなるのだ。このまま、事態を放っては置けない。
「手立てを見つけろ……何か、何かあるはずだ……!」
ツカサは、見えぬ答えを探す。


