空威張りビヘイビア

-
進みゆく侵食に身を委ね、磔となったように動かない愛。
風は未だ吹かず、鬼カベの教室占拠は続く。
毒気は室内にいよいよ濃く満ち、毒は、ツカサの思考を乱そうとする。
「ざわめくなよ、俺の心よ」
そう己に言い聞かせながら、ツカサは事態を打破する方法を、ひたすらに考える。
まず、鬼カベの弱点を推測した。
けれど封印の札をあちこちに貼られた、包帯ダルマのような鬼カベの、その姿。
全体が特徴的なフォルムではあるものの、取り立てて突飛な一部は見あたらない。
さらに不気味なことに……奴は先程から終始、黙り続けている。
無言なのだ。
タテマエのバケモノにありがちな、自らの主張を告げる咆吼というものが、鬼カベにはまるでまったく、皆無だった。
まさしく得体が知れない。
しかし毒のみならず、もはや教室中を埋めんばかりとなった鉄線の結界の密度。
ツカサは愛に接近することも、自ら身動きすることもままならない。
怪異の怨念を湛えた空気は重く、ツカサの身にのしかかる。息が詰まりそうだ。
だがツカサだけではない。眠ったままのクラスメイトたちも、愛も、皆、ただ口にしないだけで、同じ苦しみを受けている。
なんとか、しなければ……
鬼カベの動向を見据え続けていたツカサだが、その目も霞んでくる。
ここで観念してなるものか。
雑念と障気を払うように頭を振り、ふと、視線が愛の足元へと向いた。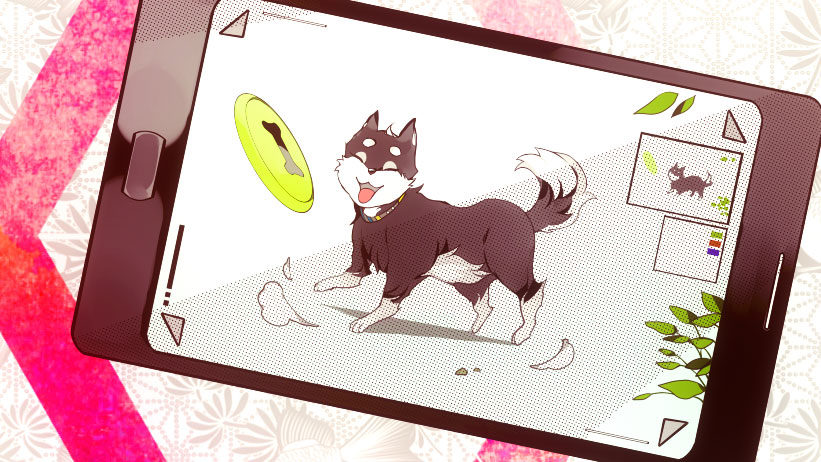
スマホが、床に落ちていた。狗谷愛が先程まで自席で見ていたものだ。その画面が光っていた。
黒い子犬の画像が映っている。
愛はさっき、どんな面持ちでスマホのその画を見ていただろう?
ツカサは思い起こす。ここで、ようやく手掛かりを感じた。
そして、
「迷ったままでは、何も変わらない」
扇子を持つ右手の震えを、ツカサは左手で抑えつけ、敵、鬼カベと愛へとその扇子の狙いを定め、かざす。
「あれなるはうつろなる言ノ葉、鬼カベ。抗すべく力、由来者はいずれ求めん。あやかしにはあやかしを、言には言を」
イチかバチかだが、行動せずに後悔するよりはずっといい。
「我は言ノ葉使い、タテマエ由来の代言者として命ずる。呼び声に答えよ、かの画像に籠められし想いと共に……そこなバイト女の眠れるホンネ姿現せ!」
召喚の祝詞をいささか捩り、願いを込め、念を込める。すると鬼カベが怯んだ。
愛への侵食が、ひととき止まる。
ばちりと、火花のような音と匂いがした。
床のスマホの画面が鈍く瞬き、電池切れなのか、すぐに消えた。
だが刹那。緑色の淡い、丸い光の塊がどこからか――窓の外、空の向こう、ずっと遠いところから――素早く、けれども柔らかく、教室の中に飛来して、ツカサとの間、鬼カベの目前へと、盾となって現れる。
一度床に落ちたその光は、黒い犬のシルエットへと姿を変えた。
黒い子犬。
愛のスマホにあった画像とそっくりな……ただ目の輝きの色と、マントを翻していることが大きな違いだった。
「わん!」
犬がひと吼えする。ハッとなって、愛は顔を上げ、犬を見つめた。
「クロ……!?」驚きで、愛の瞳が見開かれる。「クロなの!?」
「わんわん、わんわん!」
答えるように犬が叫び、その場で小さくくるくると、走り回ってみせる。
「どうして、ここに……!」
枯れた、愛の声。けれど抑えきれない気持ちが、宿っていた。
「うおん!!」
そして黒犬は、さらに緑の衣装を纏った少年の姿へと変わって、すっくと立った。
「愛! ぼくだよ! わかる!?」
少年が、囚われの愛に向かって、盛んに叫ぶ。おとなしくも利発な雰囲気を感じさせる少年。手には小さなニッパー(金属ハサミ)が握られていた。
これが彼女のホンネ妖怪か……愛の心の奥底から、呼び出されたのか。
ならば、とツカサは確信する。
狗谷愛は本当はやはり、バケモノから離れたい、助かりたいのだ。
そうでなければ、ここに少年が現れるはずはなかった。
「本当に……お前は、クロ……なのね?」
「そうだよ! ぼくは狗呂、あの野良犬だった『クロ』だ! ああ、逢いたかった!」
「わ、私も……また逢いたいって、ずっと思ってた。クロ、うれしい。でも……」
「待ってて、すぐに助けてあげる」
言いながら少年は、躊躇わず鬼カベの結界へと近づいていき、愛を取り巻く鉄線を、けなげにも、ニッパーでぱちぱちと、切り始めた。
「頑張れ、手を貸してやるぞ、少年」
狗呂少年の意図を汲んで、ツカサはその妖怪としての力を増やしてやろうと、扇子を振るう。
けれども。
「うっ……か、かたい」
鉄線は強固に、何重にも巻かれている。とても少年の手で切り裂けるようなものではなかった。
「うんせ、うんせ……ちょきちょき」
幾度も切断を試みる少年。ぎごちなくも懸命に、うんうんと唸りつつ、こまかい棘から順次退けようとする。
だが全力で千切ろうとしても、枝はともかく主線はまるで切れず、ニッパーの歯はこぼれていき、少年の手はだんだんと腫れ上がる。
ついにはニッパーを握っていられず、少年は床に落としてしまう。拾い直して挑戦を続けるが、うまくはいかない。
「ああ、あああ」
少年の焦りが重なり、その不安は、扇子を通じてツカサにも伝わってくる。
震えている。力を奮いたいのに、それが足りないのだ。力不足を自覚しているからこその、不安。
さらには。
「お願い、クロ。私の邪魔、しないで……」
愛が言った。愛の身体への、怪異の侵食は再び進みが速くなる。
赤黒い闇がじわじわと染みていく。
何故だ。ホンネを呼び出しても尚、何故、侵食を止められないのか。
ツカサは苦悩する。何故、あの愛は痛みを望み、自ら呼んだ助けを拒む。
「どうしてだよ、愛!」
狗呂少年もまた、叫んでいた。ニッパーが壊れかけている。
「私はこのままどこかに行く。戻れないところに。そうなることを、なんとなく、わかってたし、望んでた」
愛がゆっくりと目を閉じていき、
「同情とか、思いやりとか、そんな言葉は、いらない……」
がくりと首を垂れる。
すると鬼カベを取り巻く毒霧が、瞬時に増した。そしてそこから、暴威の一閃。
「ぐっ……!」「ああっ!」
避ける暇などなかった。ツカサと狗呂少年は、繰り出された無数の鉄線によって鞭打たれる。何度も、何度も。
鬼カベは、怒りを露わにしていた。何に対するでもない、ただただ周囲への、無情な怒り。怒りは毒霧の圧となり、棘の鋭さとなり、無差別に、あらゆるものを傷つける。
猛攻に耐えきれず、膝をつき、床に這い、ツカサは突っ伏す。扇子を握り直し、どうにか身を起こし、鬼カベを睨みつけてやるが、敵には怯みも油断もない。
立ちはだかる鉄条の渦。結界。まさしく鉄の、絶対防壁。
「ぼくは、どうすれば……」
狗呂少年は、ぼろぼろの手でニッパーを握りしめたまま、立ち尽くしている。
少年が動けないのは、敵への恐怖や疲れからではない。
愛が「助けるな」と、自分の言葉で、自分のホンネへと命じたからだ。
「落ち着け、少年」
ツカサは言いながら、呼吸を整え、また考える。
鉄線と鉄条網が、頑なに、ツカサと狗呂の接近を拒み続けている。
鬼カベの鉄線との融合が進んでいく愛の、痛々しい姿。
もはや、打つ手はないのか?
ジレンマ。やはり由来者の許諾がなければ、言ノ葉使いは、本来の術式の効力を発揮することはできないのか?
――いや。本当にそうなのか。そうなのだろうか。
ツカサは強く疑う。
狗谷愛は自ら絶望して、自ら世を去りたいのか。そんなはずはない。
もしも救いを拒絶しているとしても、それはただの、口先に過ぎない。
表向きの言葉など信じない。必ず、真実を引き出してみせる。
ツカサは、心に決めた。 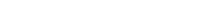
-
鬼カベの作り出した鉄条網に、ツカサはいきなり、手を伸ばした。
愛を取り巻くそれへと、素手で思い切り、掴み掛かる。
「何をするの……なんのつもりなの!」
それを見て、愛が怯えたように首を振る。
だが、ツカサの手は止まらない。
「見ていろ」
鉄線の棘を厭わず、ツカサはしっかりと、それを握りしめる。
途端、火花が散った。
「……!」
痛み。鬼カベの出す有刺鉄線は、尖り、毒に塗れている。
が、痛いのはそれのためだけではない。
ツカサは、思い出していた。言ノ葉使いとして、己の禁じ手とされていた方法を。
『他人のタテマエへと、直接触れてはならない』
忘れてしまった誰かの、忠告の声。
『触れれば、お前も侵食を受ける――』
心が割れんばかりの苦痛。
ツカサの特異体質は、そもそも怪異との親和性が高すぎるのだ。ゆえに従来、自身が直に敵と交戦することはまかりならなかった。なのに、今。
バケモノを通して由来者の負の感情が、ツカサの頭へ、気持ちへと、流れ込む。――痛い。苦しい。このままじゃいけないと知っている。
でも、どうすることができる?
『私』は『私』にできることをする以外、何も知らない。
できることを決めてかからなければ、何も実現することはできない。
だって『私』以外に『私』への、救いの手はないから。
ここで立ち止まってしまえば、すべてに絶望してしまいそうだから――別の声が聞こえた。こちらは忠告ではない。恐らくは、狗谷愛の心だ。
痛く、苦しいと言っていた。けれど。
絶望しきってはいない。自ら望みを捨てたわけではない。
最後の断崖の淵で、抗い、踏みとどまっている。「……やってみせる。他に手段があるものか」
格闘する。ツカサは鉄線を掴み、強引に千切り、裂こうとする。ばきばきと激しく、嫌な音が鳴った。帯電。さらなる火花。怪異の力と、言ノ葉の力が干渉する。
ツカサは思う。
鉄製の編み糸だ。こんなものが手で切れるものか。常識ならば、あり得ない。
だが、考えても見よ。矛盾に溢れた由来者から産まれたバケモノのすることだ。
感情と言霊が生み出したものであるなら、感情と言葉で対抗できるのではないか。
忌避される手段こそが、最も通じるのではないか。
近づくな、と言われるならば、近づくことが解決への一歩だ、と。
果たして……
ほんのわずかずつではあるものの、ニッパーで切ることもままならなかったはずの、堅固に編み込まれた銀の線は、ほぐれ、細く分かれていき、だんだんと崩れ……
ついにその数千本のうちの一本が、ツカサの手によって切られた。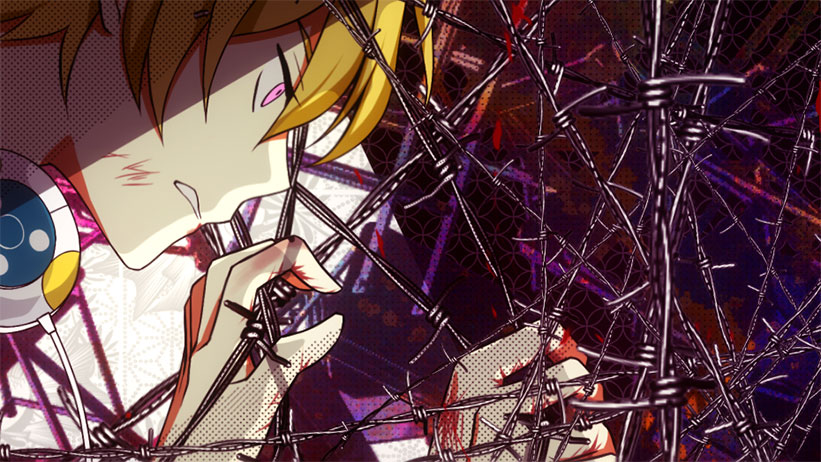
「なんなの……情けないし、かっこ悪い……」
愛が微かに目を開き、ツカサの有り様を見た。
ツカサは続けて、数本の鉄線を、素手で排除する。無論、手は傷だらけだった。血と汗に濡れ、破れ、疲れていた。
「どうして、そっとしておいてくれないの……」
愛はつぶやく。
「何故だろうな。俺も知りたい」ツカサも、独り言のようにつぶやいた。「わからないんだ……あんたと俺は、別に親しくも何ともない。義理も、思い入れもない。こうまでして助ける理由は、ない」
「だったら――」
愛が言いかけて、しかしツカサは遮る。
「それでも、したいだけだ。ためらいは後悔しか産まない」
行動しなければ、と思っていた。同時に、ツカサは思い出せない何か、過去にあった何かを脳裏に思い浮かべていた。
その出来事が何なのか、それもハッキリとは、今、思い出せない。
ただ、あんな気持ちになるのは嫌だ、ということだけは明白だった。もう、『あの時』のような遺恨は、残すまい。「気持ち悪い……もう、やめて……お願いだから」
愛は言うが、がむしゃらなまでにツカサは、鉄線に挑みかかる。
「無謀を笑いたければ、笑ってくれ」
言いながら、ツカサ自身も自嘲する。それでも。鉄線をしりぞけていくごとに、ツカサは己の手を通して、何かがわかるような、そんな気がしていた。
愛の隠された本心、その傷ついた日常の心。
日々のつらみを隠しながら生活してきた、その心。
その心の内が聞こえてくる。
我慢しなくてはならないのだ。努力しなければならないのだ。しかし、悟られてはいけないのだ……ひたすら、己に言い聞かせる声。
まるで己自身への、洗脳、のような。
そこまで愛が己を追い詰める、その事情はわからない。
わからないが、わからないまま、愛の気持ちは絡まっていた鉄線と共に、少しずつ、少しずつ、ほぐれていく。
「葛葉……馬鹿、なの……?」
「かもな」
応えつつも手つきは止まらず、鉄線除去をツカサは続ける。
「まったく面倒で、迷惑極まりないな、狗谷」
「そんなの、私が頼んだわけじゃない」
続けていく。
「これ以上、手間を掛けさせるな」
「こっちの台詞だよ、葛葉……」
いつしか、数滴のしずくが床を塗らした。愛の瞳から、涙がこぼれる。「ツカサ、愛……ぼくにも、何か、わかるよ」
その床の水滴が光り、続いてゆるりと宙に浮かんだ。仄かな灯になる。その灯火が、狗呂少年を、暖かく照らす。
「うん。わかる。愛、本当は……」
想いが伝わったのか。少年に、変化が起こる。
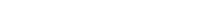
-
愛の祈りをともした小さな灯を、少年の手が掴み取った。
すると瞬時に少年の背が伸び、青年の格好となる。
すっとした、スマートな立ち姿。利発そうで賢明そうなのは変わらず、身体の線は細いながらも、しっかりとどこか、芯の強さ、逞しさをも湛えているように感じさせた。
ざっくりとシャツを着こなし、青年は無造作に髪をかき上げる。
この場の毒と緊張にも、まったく怖じるところがない。
不思議な雰囲気を持った青年だった。
「また、ぼくのことを心の中で呼んでくれたね、愛」と青年。
「くろ……?」
反応して、愛がつぶやく。
「そして、この姿。あのクロ犬が人として、立派に成長したら……君は想像したことがあるだろう?」
「そうね……」
「鉄の棘には、鉄の刃を。愛のために仕える走狗」
「黒い、鉄……クロガネ」
「そう。ぼくの名は、クロガネ。黒鉄、そうく」
青年は名乗った。
愛の背後では相変わらず鬼カベが蠢いているが、青年の出現に驚いたか、些か動きが鈍っている。
「ぼくは、愛のリクエストに応えたまでだ。さてツカサ、どうする」
「え、俺に訊くのか?」ツカサも少々面食らった。使役する術師を促す妖怪、というのも珍しかろう。
「勿論。望みを叶える。ぼくはそのために、ここにいるんだ」
そうく青年は柔らかく自然に、微笑んだ。
「……すべきことは決まってる。言うまでもない。が」ツカサも肩の力が抜け、思わず笑む。「俺も言ノ葉使いとして、黒鉄、お前に命じよう」
「ああ。なんなりと」そうくは何処からか、自らの身長ほどにまで巨大に成長した新品のニッパーを取り出す。「ならば行け。黒鉄。進んで敵を打ち砕け」
ツカサが、掲げた扇子を一振りすれば。
「まかせてくれ」
そうくの持つニッパーの刃は、鬼カベの本体の正中を突き通し、一撃にて両断した。
あまりに、あっけなく。あっさりと。
雄叫びも断末魔も一切あげることなく、敵・鬼カベは、敗れ去り、崩れ、塵と化して消えていく。
どうやら鬼カベ自身は、他のタテマエの怪異と違い、さしたる主張を持たないタテマエだった。愛の望みが排他と自縛であるならば、それを愚直に叶える、それだけの怪異だった。たったそれだけの、タテマエ。
タテマエの反転の存在であるホンネ・黒鉄そうくの前では、鬼カベの抱える虚ろな願いなど、実に、無力。
ツカサの握る扇子の震えもいつしか完全に、治まっていた。
あの鉄の棘を掴んだときに受けた負の感情が、すっかりと消えていた。
だが――
あるいは、先頃までの愛の束縛の願望が、強すぎたせいなのか。
わずかにこの場に違和感があった。
「くっ……何故、鉄線が残ってる?」
ツカサはうろたえる。鬼カベから放たれていた毒気は急激に薄れつつあるが、教室中には鉄条が張り巡らされたままだ。
怪異からの攻撃の残滓が留まるなど、言ノ葉の常識ではあり得ない。
バケモノめ、死に際に結界を生じる能力を暴走させたか。
「確かに。変だね。でも、どうにかすればいい。そうだろう?」
「……その通りだな」
「さあ、指示を」
「切り裂け、この黒き鎖を!」
深く考えるのはやめ、息を吸う。心の落ち着きが戻ってくる。ツカサは再び扇子をかざし、術を奮う。
そうくが、ニッパーを操る。繰り出される鋭利な斬撃は、みるみるうちに鉄線の包囲を打ち破り、解き放っていく。
「いいぞ、そのまま断ち切れ!」
「嬉しいね。自在に動ける。ぼくは自由だ……」
もはやツカサも、術が思い通りに使える。のびのびと扇子を振るい、そうくも無駄のない、美しい動きで、愛への囲みを切り飛ばしていく。
この鉄の網を解きほぐしていくたび、そうくは、何事からか解放されたような様子を徐々に見せていた。
ホンネの妖怪として、活躍でき、己の力の使い方が馴染んできたからか。
それとも。
心の底で自分の出現を願ってくれた由来者、愛の本心に、やや近づくことができただろう、その気持ちからなのか。
ともかくも。
室内に充満していた怪異の不穏は、多くの鉄条網と共に撤去され、失せていく。
やがて、
「どうぞ」
ツカサへと、そうくが手振りで示す。
有刺鉄線はあとわずか、狗谷愛の身体を直にぐるりと巻いて覆っている、それのみとなっていた。
ツカサは、磔の格好のままの愛へと、歩み寄った。
その身に染みていた毒の色は既に褪せ、侵食の眠りから、愛が目覚める。
そして、ツカサを見つめた。
「ねえ、どうして? やめてって言ったのに」愛が問うた。「なのに何故、来るの。どうして、私に構うの」
「どうもこうもあるか。あきらめろ、狗谷」
「…………」
愛は、もう抵抗しなかった。愛の纏う最後の鉄線を、ツカサはぎりりと乱雑に掴み、手で退ける。
鉄の鎖の囲みはもう、すべてなくなった。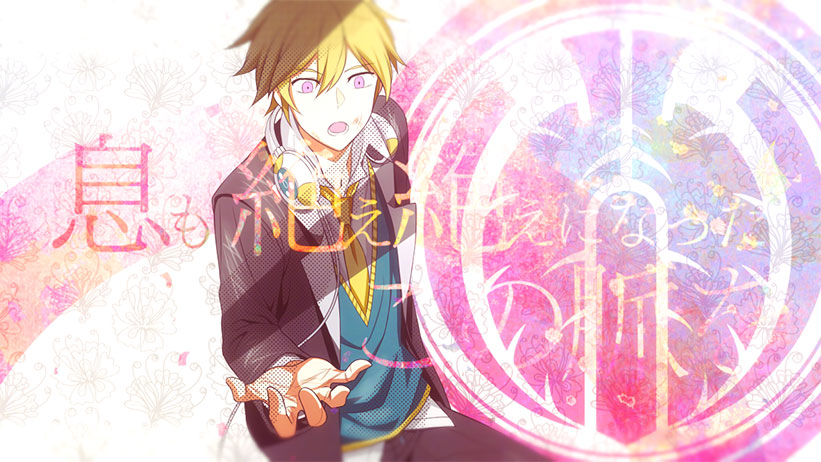
ツカサは自然と、愛へと手を差し伸べていた。
「お前の事情は知らない。けれど俺は、ここに居合わせた」
「それだけ?」
「そうだ。俺はただ、ここにいる。ここにいたかっただけだ」
それ以上の理由は、ツカサには思い浮かばなかった。
言ノ葉使いとしての、自分の存在意義。
他者から与えられた使命や任務ではなく、自らの意志――力が使えるなら、それによって人は、救われて欲しい。それだけだ。
「ごめんな、驚かせて」
ツカサはもう一度、愛へと声を掛ける。
「もう、いいから。これ以上、びっくりさせないで」
観念したようにツカサの手を取り、愛は頷いた。
その時。
窓から一陣の風が吹いた。緑色の風のように、ツカサには思えた。
直後。教室は、元の平穏な空気へと戻っていた。
すべての毒気や破壊の跡は修復されていた。
まるで何事も起こらなかったかのように。忘れられたように。
遅い教師の到着を待ちながら、ホームルームを迎える前の、ざわざわと浮き立つようなクラスの喧噪が蘇っていた。
ツカサは、クラスの自身の座席にいた。いつの間に着席したのだろう。
壁の時計の時刻を眺める。
時間が……戻っていた。鬼カベが出現する、その前へと。
思わず「今、何時だ?」とツカサは、後ろの席の奴にも訊いてしまう。
自分のスマホ見ろよ、と言われながらも、現在時刻を教えられる。
そんな馬鹿な、とツカサは心の中で呟く。
皆の時計の時刻が止まり、または、ずれている。そうとしか、考えられない。
それとも本当に、時間を遡ったのか。
いったい、何があった?<けれど、ふと、廊下を見やれば、そこには――黒鉄そうく青年が、学園に通う子女を迎えに来た一保護者の装いで、立っている。
目が合って、そうくはツカサへと軽く会釈をしてみせた。
ツカサの掌にも、ほんのわずかだが、細かな傷が残っていた。
その傷を受けた感触を、ツカサは覚えている。
先の戦いは、確かに起こった。周囲の皆に認識されていないだけだ。
夢や幻ではない。「ツカサツカサツカサ、一緒におやつを食べよう」
隣のクラスから、三鹿ナルキがツカサの座席にまで押し掛けてきていた。数名の男子学生を引き連れている。これから、遊びに行くのだろう。ツカサはそれを、知っていた。
「虫歯に気をつけろよナルキ、油断大敵」
「わかってるって」
「で、今日はショートケーキだろ。珍しいな」
「えっ?」ナルキは驚く。「なんでわかるの」
「ただの勘だ」
「そうなの? たまには、みんなで外に食べに行くのもいいかなって思って」
「なら仕方ない、俺も付き合ってやるか」
「うん!」
ナルキは明るく頷き、仲間たちも同意する。
「大勢でぞろぞろつるんでいくのは好きじゃないが、今日だけだぞ」
ツカサはすぐさま下校の支度をととのえ、マフラーを掴み、座席から立ち上がる。
そして。廊下に向かう途中。
「じゃあな、狗谷」
斜め前の席へと、ツカサは声を掛ける。
「…………」
狗谷愛は自分のスマホの画面を見つめたまま、ツカサへ視線を返さない。
けれど無視しているわけではなかった。
無言の会話が、そこにあった。
「お先に」
ツカサはナルキと仲間の後を追い、教室を出る。
「さよなら、葛葉」
既にツカサが去ったあとで、ようやく、小さく、誰にも聞こえないくらい小さく、愛は言った。そして、スマホで通話する。
「すみません店長、今日はバイト遅れます。ホームルーム、長引いて――」「どうしたの、ツカサ」「なんでもない。行こう。ホールケーキが待ってる」 愛は微かに笑んでいた。顔をうつむけて、見えなくともわかった。教室へと一度振り返りながら、ツカサはそう思う。



