空威張りビヘイビア
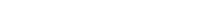
-
夏の訪れを待つ、ある日の暮れ。
薄闇の中、街灯の輝きがふわりと霞んでいる。霧のような小雨が降っていた。
傘が不要な程度の雨というのは、少々悩ましい。濡れていくのか、防いでいくのか。
もっとも今日のツカサには、傘がなかった。
それでも黒鉄そうくに誘われ、町の片隅にあるハンバーガーショップにまで出向き、今はその室内の座席にいた。
マフラーについた微細な雨粒を手で払う。
小さなテーブル席の対面には、そうくがいて、ツカサの面持ちを眺めていた。見つめてくる。先程からずっと数分間、その調子だ。
「なんなんだよ、黒鉄」
ツカサは憤慨するが、
「いや、どうしてだろうなって。考えていたんだ」
そうくは掴みどころのない仄かな笑みを浮かべつつ、さらりと言う。
「考える? 何を?」
「どうしてぼくは、この店にツカサを連れてきたんだろうね、と」
「お前が誘ったんじゃないか」
「そうじゃない。今日のことじゃないよ。もっと前の話」
「……何を言ってる」
ツカサはいよいよいぶかしむが、そこに、
「16番でお待ちのお客様、お待たせいたしました」
どん、とドリンク2本と山盛りのポテトを載せたトレーが、テーブルに置かれる。
トレーを持ってきたのは、バイト制服姿の狗谷愛だった。
愛は作り笑顔でそうくに軽く手を振り、それからツカサを一瞥して、あからさまにげんなりとしてみせた。
「また来てる……ねえ、クロ。なんで葛葉を連れてくるのよ……」
「ぼくはツカサに用があるんだ、愛」
「ここじゃなくても。よそに行きなさいよ。ほら、別の……喫茶店とか」
「ぼくはこの店が好きなんだ」
「それは、わからないでもないけど」
「愛の顔も見たかったし」
「……そうかもしれないけど」
「ほら。それに特に今日はお店、静かだし」
「今日は雨だから、お客さん少ないのよ……」
「君の邪魔はしないよ。ゆっくりしても、構わないかな?」
「……良くは、ないけど……」
そうくの落ち着いた弁明にも、愛は不服そうだ。不満の目はひたすら、ツカサにだけ注がれていたが。
「葛葉」眉を曲げたまま、愛はいきなりツカサへと声を掛ける。
「なんだよ、狗谷」喧嘩腰の愛に、ツカサも屈折した目線で応える。
「これあげるから……食べ終わったら、とっとと消えて。目障り」
愛は制服のエプロンのポケットから何か掴み、ばらばらとツカサへ投げて寄越した。
いくつかの、ぼろぼろの小さな紙片だ。テーブルの周辺の床に、それが散らばる。
「それが客に対して言う言葉か」
ツカサは身を屈めて紙切れを拾いながら、悪態をつく。
「席に座ってるだけなら、客じゃないし」仁王立ちの愛は言い募った。「どうせクロのおごりなんでしょ。自分で払ってよ、ポテト代くらい」
「言い掛かりだ」
「おごるから店に来てくれといったのは、ぼくなんだけどな、愛」そうくが言う。
「だとしてもよ……とにかく」愛はツカサに背を向け、そうくに振り返り、大仰に溜息をついてみせた。「ああ、ムカツク。お店いつもより暇なのに、いつもより疲れる。もう、休憩しよ……」
「あ、休憩時間なんだ。裏口でいつもの練習するの、愛?」
「今日はやらないよ。だって雨だし……」
言いながらエプロンを外し、愛は店の奥隅の空席に行って、乱雑に腰を下ろす。
そのテーブルに突っ伏したまま、エプロンを頭に被って自身を覆い、やがて……小さく寝息を立て始めた。
無防備にも。眠っているのか。こんなところで。
半ば呆れてツカサが見ていると、
「バイト、愛は週5から週6に増やしたいらしいね」
そうくがつぶやいた。
「え、週6?」
「それも毎日6時間ずつを希望してる、店長と交渉中だ」
「多いぞ……」
ツカサは面食らう。狗谷愛がマメに働いていることは、なんとなく知ってはいたが、これでは学生のバイトの域を超えている。
「でも無理かな、他にもシフトを入れたい子がいるだろうし」
「そういう問題なのか」
「愛自身、そんなに仕事ばかりしてられないはずだね。学校に通っていられなくなる」
「だろう? そもそもバイト週5がおかしい」
「けれど現状、彼女はそうせざるを得なくて」
「どうして」
「うん。そこだ。そのことなんだけど」
そうくは涼しい顔をしたままだが、やや視線を泳がせ、逡巡する。
それから突然、そうくはツカサの手を、両の手で握った。
まだ先日の、鉄線を掴んだ傷痕がわずかに残るツカサの掌。
その傷を、そうくの指先が、すっとなぞり、包む。
「話すと長いけど、その話をやっぱり、ぼくは君にする」
「なんで急に俺の手を取るんだよ、黒鉄」
「全部を言葉にするよりは、わかりやすいと思うから」
「どういうことだ?」
「考えない。感じればいい。目を閉じて」
怪しげなそうくの物言いに抵抗を覚えつつ、ツカサは、目をつぶる。
途端、意識は宙に飛ぶ。ばちり、と、小さな火花がマフラーから散った。
何かが、走ってくる――いや、走っている。
俺の気持ちは、その走っているものに一体化する。
どこかに向かっている。速度と共に息が上がり、けれども、胸が躍る。
これは、誰かの体験だ。いつかの過去の想い出だ。
もやもやとした、霧雨に煙った光の中を駆けていくと、そこには町の裏側があった。
確かに、この日も雨だったな……
水に濡れた自分の足元を見る。
裸足だ。小さく若く、黒い毛並み。
そう。これは、幼いぼくの記憶。まだ名前を、彼女から貰う以前の。 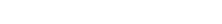
-
わん。ぼくは、その頃まだ、小さく黒い犬で。
前はどこかに飼われてたけど、昔の名前は忘れてしまった。
けっこう長い間、ひとりぼっちになってて、どこをどう来たのか、わからないけど、いつの間にか、この町の中をさまよう。
一匹でうろうろと、寝るところや、ごはんを探す日々だった、わん。毎日毎日、大変だった……
雨が降っていた。ある日のこと。歩き疲れて、おなかがへった。
お肉のニオイに釣られ、ぼくは裏路地に迷い込んだ、わん。
金網に囲われた、暗い川沿いにある、せまくて、殺風景なところだった。
……入っちゃいけない道だったらしい。
そこをナワバリにしてた他のノラ犬が、ぼくを見つけるなり、猛然と怒って、ほえて、噛みつこうとする。
相手の犬は、大きいおとなだ! 襲われたらぼくは、ひとたまりもない!
逃げなくちゃ。だけど足はぬかるみにとられて、ぼくは、転ぶ。追い詰められる。
ぜったいぜつめい、大ピンチ。
そしたら、そこに愛ちゃんがやって来たんだ。
愛ちゃんはすごくキゲンが悪く、コワイ顔をしてたので、「わっ!」とおどかしたら、あっちの犬はすぐどこかに行ってしまった。
あとで聞いたけどそのノラ犬がごみをよくあさるので、愛ちゃんのバイト先の店がずっと迷惑してたのだそうだ。
とにかく、ぼくは助かった。愛ちゃんのそばに行って、お礼をいったわん。
でも犬語だからわかんないかな?
「お前、黒いね」と、愛ちゃんはなんだかアワレそうにぼくを見て、それから店の中に帰った……それからしばらく経って。まだ長雨の季節は続いてたけど。
元いたノラ犬が、どこかにいなくなって。
ぼくはバーガー屋のあたりを、新しいねぐらにした。
雨つゆがしのげるし、ごはんがある。とてもいい。
それにしても、前いたノラを嫌ってたのに、なぜか愛ちゃんはぼくに、残りのバーガーをくれる。
「だってお前、黒すぎるから。あと、小さいし」
確かにぼくの体は黒いし、だいぶおさなくて、小さい感じ。くうーん。
やっぱりアワレに思ってエサをくれるのかな。
「黒すぎだから、クロって呼んじゃうけど」
名前をつけられた。さらに、愛ちゃんはぼくに向かって、お説教。
「勝手に他のものを食べてはダメよ、クロ。このへんのお店の残飯には、タマネギとかチョコとか、犬にとっての猛毒も混じってるんだから。ね?」
怒る愛ちゃん。でもそれって、正直うれしいよ。ぼく。
ごはんをくれる。かまってくれる。見ててくれる。
キミの叱咤のおかげで、ぼくは成長できるんだ。わん。
「いらっしゃいませ、いらっしゃいませ」
けれど、どうしてなんだろう。
愛ちゃんはバーガー店の裏口で、よく接客マニュアルを見ながら、笑う練習してた。
ほとんど毎日、毎日。作り笑いを。
表通りには、たくさんの人が楽しそうに遊んでるのに。どうして愛ちゃんは、いつもひとりでバイトなの。
「私のスマイルは無料なんだ」愛ちゃんは言った。「でも、バイト代は貰えるから。週末も連休も、学校が休みのときも、笑顔で稼がなきゃ」
お金のため? ただそれだけなの?
「それに私と出かけても……たぶん、みんな面白くない。私、普通の笑い方、忘れちゃったから……」
忘れた、っていうのは、どういうことなんだろう。気になった。とにかく、そのうちに愛ちゃんのニオイを覚えてしまった、ぼく。
ちょっとイケナイかなと思いつつ、愛ちゃんがいつもどこからバーガー店に働きにきているのか知ろうと思う。
雨の晴れ間を見つけたある日、地面のニオイをたどってみた。
そしたら大きな、学校ってところにたどりついた。
ここに普段、愛ちゃんがいるのかー。
そのうち鐘の音がして、人がたくさん学校から出てきた。ぼくは、そのたくさんの中から愛ちゃんを見つけて、しっぽを振って、近づく。
そしたら、
「クロ、お前、何やってんの?」
と、思い切りあきれられた……
だけど愛ちゃんはその日も、ひとりだった。ぼくだけがそばにいた。
愛ちゃんの行き先は、バーガー屋の裏口だ……
「まあ、今日もバイトだし。明日も。仕方ないね」
愛ちゃんは言う。
けれど、ためいきが聞こえた。
仕事、つまらないのかな。ユーウツなのかな。
サボっちゃえばいいのに。やめちゃえばいいのに。
ぼくは愛ちゃんの服のすそをぐいぐい引っ張る。
「こらクロ。やめなさい。私、仕事。邪魔しないで」
どうしてだか、ぼくは愛ちゃんに怒られる。そして愛ちゃんは店の中に、とぼとぼと入ってく。ちょっとわからない。ぼくがコドモだからか。わん。また少し後の、別の日。この時は特に、雨が強くて。
もうシフト時間は終わっているというのに、バーガー屋の愛ちゃんは学校の制服姿のまま、お店の周囲を掃きしめていた。
そこにぼくが現れた。いつものように、愛ちゃんに逢いに。
けれど……ぼくは、ケガをしていた。
いつも建物の影から影へ隠れるように生活しているぼくは、うっかり、商店街で飛び出してきた自転車にはねられかけたのだった。
といっても、たいしたことない。
少々すりむいて、少々毛が抜けて、ほんのちょっとだけ血が出たくらいで。見た目はアブナイけど、舐めてればそのうちなおるかな? って程度のケガだったんだけど……
「クロ! お前、どうしたのよ!!」
愛ちゃんはぼくを見るなり大慌てで、掃除用具を放り出して、水たまりをばちゃばちゃと踏み越えて、走ってきて……
そして雨に打たれながら、びしょ濡れになっていたぼくのからだを、抱き上げた。
「だいじょうぶ? だいじょうぶ?」
愛ちゃん、あたたかい。ぬくもりに包まれ、ぼくの中から、さっきの自転車への驚きが消えていって、とても落ち着く。
けれど。ぎゅっとぼくを抱きしめる、愛ちゃんは、ひどく震えていて。
「クロ、まさか、まさか……事故に……」
目から、大粒の涙が出ていた。次々に。どうしてそんなに泣いてるの、愛ちゃん。
「おかあさん……おかあさん……」
……おかあさん?
途端。ぼくと愛ちゃんが触れ合っている、そのぼくの前足のところが、びびっ、とすごくしびれて。
何かの気持ちと、想いが、強く、ぼくの中に流れ込んできた――――
――『愛』。私の名前。
仲睦まじかったお父さんとお母さんの、気持ちがこもった名前。
でも、私のお母さんは、今はいない。
ある日、いなくなった。交通事故だった。
その日。お母さんは何の前触れもなく、この世を去った。
お母さんは事故の一方的な被害者で、何の落ち度もなかった。なのに。
もう永久に戻ってこない、帰らぬ人となってしまった。
悲しかった。でも、それだけじゃなかった。
折悪しく、お父さんの作った会社はひとつの困難に当たっていた。
お母さんという最大の理解者、かつ、最愛の人を突然に失ったお父さんは、経営者としても、ひとりの人間としても、この上なく、苦しむ。
けれど、お母さんの実家の、お父さんに対する態度は一変した。
「お前のせいだ」「お前が悪い」「お前があいつを殺したようなもの」「無能」「所詮は山師」「娘だけでなく我々の名前にまで傷をつけた」「こんな奴を入り婿にしてしまったなど、一族の恥」……
私とお父さんは、お母さんと同じ苗字を、取り上げられた。
お父さんは会社を奪われ、職を失い、私もそれまで住んでいた部屋と家を失った。
お父さんと私は、寂れたアパートに移り住む。
「だいじょうぶだ、だいじょうぶだからな、愛。心配するな」
懸命に、慣れない下働き仕事をし、汗を垂らして、お父さんは言う。
「誰が何を言おうが、お父さんが必ず、愛を守ってやる」
でも、そのお父さん自身の表情があまりに暗く、寂しく、不安げで、力ない。
そのうちに……
働きづめで、無理がたたって、お父さんは身体を壊し、アパートで横になっている時間が増える。
激しく咳き込んで、布団から出られず、けれどやがて、酒瓶を手にすることも多くなっていった。
「くそくらえだ! 誰もわかっちゃくれない! 世間に希望など、ありゃしない!」
お父さんは荒れていた。ひとしきり暴れて、叫び、それから眠る。その繰り返し。
少しして目覚めると、いつも、お父さんは泣いていた。
「すまない……すまない、愛……だけど、お父さんももう、疲れたんだ……」
私も疲れていた。
お父さんが熱意を持って、さまざまに挑み、なのに侮られ、騙され、裏切られていくのを見て、私は思い知らされていた。
誰も信じられない。人の優しさや同情なんて、うわべだけの嘘っぱち。
でも。それでも。
なんとか、生きていかなくちゃ。
でないと、いざというとき、私はお母さんに会わせる顔がない。
ただ、ひたすら、やれることをしなくちゃ。
たとえつらくても、悲しくても、マニュアル通りに、笑ってみせる――――――ほんのわずかな時間のあいだだったと思うけど、ぼくにはそれが、気の遠くなるような永遠にも思えた。
「クロ。守ってあげる。私がお前を、守ってあげる……」
愛ちゃん。ぼくには人間の言葉はわからない。
でも気持ちはわかった。理解できる。
やれることをやろう。できることをしなければ、生きていけないんだ。ぼくたちは。
ぼくは抱きしめられながら、身をよじって、それで少しでもいいから愛ちゃんをあたためることができないかな、と思う。それから、また何日かが経つ。ぽつぽつと、こまかい雨が降り続く日々。
バイトがとても忙しいからかな。愛ちゃんがそっけなくなり、ぼくにあまり話しかけなくなった。
くうーん……ちょっと、さびしいわん。
でもこれ、たぶん、愛ちゃんもさびしいと思う。
あいかわらず、仕事、仕事と、裏口に出てくるたびにひとりごとをいってるけど。
いつもつまらなそうに、笑っているから。どうすればいいだろう。
そうだ。ぼくは少し考え、雨上がりの隙間を縫い、いつもと違う時間に、学校に向かってみることにした。
愛ちゃんはもうバイト先にいるはず……だけど、ぼくは通学路で、鼻を鳴らす。
すると……あるひとりの人物から、特別なニオイを嗅ぎつけたんだ。
ああ、見つけた! と、ぼくは思った。
愛ちゃんがひそかに、探していたモノのニオイ。
ずっと見つめていたモノのニオイ。
それはとても、ひとりぼっちで、けれど絶望に折れることがない。
孤独と戦うことのできるモノのニオイ。
出逢いたいモノのニオイだ……ぼくは、運命を感じちゃっていた。奇妙な長ーいマフラーを身につけた、その人物。
そのマフラーに食らいつき、無理矢理引く。引っ張る。ぐいぐい、ぐいぐいと。ぼくは彼を、愛ちゃんのところへと連れて行くんだ。
「なんなんだ、この犬は……! おい! このマフラー、おろしたてなんだぞ!」
何事か彼が叫んでいるけど、ぼくは知らんぷり。マフラーを咥えて、ずんずん、引っ張って、引き摺って行く。
疾走。ぼくは走る、走る、彼もつられて、走る、走る……
決して転ばないように、足元をしっかり見る。視える。路面が前から後ろへと、滑り流れる。まるで、飛んでいるみたい。水たまりがやがて乾いて、雨の名残をすっかり忘れていくように。さあ。目的地に着いた。彼をここに導くことができたんだ。引き合わせることが。
バーガー屋の裏口を見あげる、彼とぼく。
これから店に入ろうとしていた愛ちゃんが、ちょうど、そこにいた。
「うおん!」
勝ち誇ったような顔でぼくは、大きく声を上げた。
愛ちゃんは、ぼくの帰りを待っていてくれた……けど、ぼくの隣の彼を見て、ひどく眉を曲げて、怪訝な表情。
「なんなの……なんで連れてきちゃうの、クロ……」
愛ちゃんの顔が、なんだか赤い。恥ずかしいのかな。それとも、怒ってるの。
「…………」
彼もうさんくさげに、愛ちゃんを見た。
いったい誰なんだ? という顔をしている……
「いらっしゃいませご注文は、用がないなら消えて」
まるで愛想のない愛想笑いを浮かべて、彼に向かって愛ちゃんが言って、そしてすぐさま、店内へといなくなる。
あれれ……なんで。どうして。
「まあ、用はないな……お互いに」
彼も踵を返し、通学路へと帰っていく。うーん。おかしいな。
ねえ? 逢いたいんじゃ、なかったの?
ぼくのカン、間違いはなかったハズだけど。
……このあとでぼくは、愛ちゃんにお説教されてしまった。
「クロ、変な奴を連れてこないで。あいつムカツクし」
うう、ごめんなさい。ニガテなニオイだったのかな?
「苦手な奴ってわけじゃないけど、だけどあいつは……葛葉は、裏切り者、だから」
裏切り者?
「以前はひとりで平気だったはずなのに。今はちやほやされて、いい気になってる」
そうなの?
「……周りに持ち上げられていることに気づかないと、いつかきっと、不幸になる」
そうなんだ?
「って! い、言っておくけどクロ、あいつを心配なんてしてないからね……私は」
うん。わかってるよ。
だけど……だけど……ぼく、予感がするんだ。
あれはきっと、仲間だよ。仲間だ。わん。とはいえ、犬であるぼくのつぶやきが、愛ちゃんに全部伝わるはずもなく。
愛ちゃんはいつものように、バーガー屋の裏口から店内へと、消えていった。
同時に、新たに降ってきた霧雨が、ぼくの歩いてきた足跡を消していた。
このもうしばらく後、ぼくの記憶が、一旦途絶える。
どうやら人間に捕まって、どこかに連れて行かれたらしい。わん。
どこなのかはよくわからないけど、とても気が遠くなってしまって……
再び目覚めたときには、知らない遠い土地にいた。
それでも。
その知らない場所から、愛ちゃんのことを、君の孤独のことを、ぼくはずっとずっと、気にかけていて、そして見守っている。
もしも君が危機に陥ったなら、ぼくは絶対駆けつけよう。
だから君は、ぼくの名前を呼んで。言葉にならなくとも。心の中で。
きっと、ぼくは飛んでいくよ。マントを羽織って。どんな遠いところからでも。もしも身体が行けなくとも、ぼくはぼくの気持ちを風に乗せ、君のところに向かうから。 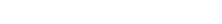
-
「ぼくからの話は、以上だよ。ツカサ」
ハンバーガーショップのテーブルの対面、ツカサの手を自分の両手で握ったまま、冷静なはにかみ笑いを浮かべて、黒鉄そうくは言った。
ツカサは慌てて払うように、己の手を引っ込める。
なんで急に、妙に立ち入った話をするんだ、こいつは……
「それを知って、俺はどうなる」
「どうとでも。ただ、知ることは仲良くなることへの一歩だ。それだけでいい」
「まったく」ツカサはひとつ、長い溜息をつく。「同情はしないぞ、黒鉄」
「彼女もきっと、同情など求めないよ」
「……かもしれないが」
「理解してくれれば、それでいい」
そうくの顔色は変わらない。淡々と、仄かに笑うだけだ。
「それにツカサ、君も同類だ」
「何のことだ、同類って?」
「君には、家族がいない」
「いないわけじゃない。ちょっと事情が――いや、お前には関係ないだろう?」
「語れない事情? なら、聞かない」
「それより少しは食え、ポテト。冷めるぞ」
「そうだね。君がそう言うなら」
そうくがゆったりとした、まるで気の無いような様子でポテトをつまみ始める。
ツカサも自分のドリンクに手をやり、ストローを吸う。アイスティーの氷は既にだいぶ溶けていて、飲み味が薄い。味気なかった。
麝香猫キヌとは別の意味で、黒鉄は掴めない奴だ、とツカサは思う。もっとも三鹿ナルキも何を考えているか、人のメンタルでは量れない部分があるから、ホンネ妖怪全般がそうであるのかもしれないが。
それにしても。落ち着き払って、それでいて、人を惑わす。その無邪気さよ。
ツカサはそうくをひと睨みしてみるが、やはり、彼に怯みはない。
「気に障ったかな?」と、そうく。
「そうじゃない……もう、いい」
追求をやめる。
そうくは周囲への気配りに長けているようだが、そのあらゆる配慮は巡り巡って、主たる狗谷愛に向けられているのだろう。
忠犬の賢さ。
そう単純に考えれば、納得がいった。「葛葉、まだ居たの……」
バイト服にエプロンを着け直した愛が、いつの間にかツカサの隣から、座席を見下ろしていた。
「悪かったな。だが用は済んだ。帰る」
ぬるいアイスティーを飲み尽くして、空の紙カップを持ち、ツカサは席を立つ。
「早く、どいてよ。このへんの座席、掃除するから」
「わかってる。ほら、黒鉄もどいてやれ」
何故か食べかけのポテトを指につまんだまま、テーブルに突っ伏しているそうくの肩をツカサは軽く揺すった。
……起きない。
ポテトを持つ指に、ツカサは手を触れてみた……冷たく、ひんやりとしていた。
かすかな笑顔を浮かべたまま、目を閉じて、そうくは動かない。
「まさか――」愛が青ざめる。
「いや。眠っているだけだ」
店内に、わずかな風が吹いた。黒鉄そうくの身体から、その風は出る。風が、ふわりとした草色の、緑の塊となって浮かび、漂って、窓を突き抜け、そのまま外の空の彼方へと飛んでいく。
魂は元の場所、元のクロ犬のところに、一度戻るのだろう。
「仕方ないな……早めにこっちに帰ってきてよね」
眠るそうくの冷たい手の甲をそっと、優しく撫でながら、愛は言う。
「黒鉄は、しばらくそっとしておくか」
「うん。そうしておく」
セルフのダストシュートに紙カップと紙くずを突っ込み、ツカサは愛に背を向けた。
「どうもごちそうさま」
「さようなら、女の敵」
「いきなり何言ってるんだ」
「こないだ、葛葉は私を泣かせたでしょ。鬼。悪魔」
「タテマエ退治のことなら、とばっちりだ」
「血まみれの手で私に微笑みかける変態」
「お前なあ……」
「またのご来店を待ってないから」
「接客マニュアル読み直せ」
「うるさいな。あっ、何やってんのよ……やめなさい、バカ」
「え?」
思わず、ツカサは振り返った。
眉を吊り上げて怒り、睨み、けれど残念であるような、複雑な……愛はツカサに視線を突きつける。
「捨てないでよ、それ」
「紙カップを捨てただけだ。リサイクルか?」
「違う。今、一緒にクーポン捨てたでしょ」
「クーポン……」
捨てきれなくてダストシュートの周りの床に舞い散らかった紙くずを、拾い上げて、ツカサは見る。
紙くず。
先刻、テーブルでツカサがそうくと面談していたとき、トレーを持ってきた愛がツカサへと投げて寄越した、あの紙切れだった。
印刷がヨレヨレでよく読めない。だが、ざっと10枚はあった。
古ぼけて見えるが、期限は切れていなかった。
「すまないな。クーポンだよな。間違えたんだ」
すべて、ツカサは集め、自分の制服のポケットにねじ込む。
「なら、いいけど」と愛。「うっかりしないでよね。期限内に、ちゃんと使って」
「わかった、わかった」
背後へ手を振り、ツカサは退店する。
「……ありがとう、ございました」
愛の声を、背に聞いた。自動ドアが開き、そして、閉まった。
歩き去りつつ、どうしてだか、次第に笑みがこぼれた。
自動ドアのガラス面に映っていた愛の、自分を見送るときの、かすかな笑顔。
それは『無料のスマイル』ではなかった。
不器用な、おせっかい。
理由はハッキリしなくとも、構いたいから相手に構うのだ。それでいい。
次はいつ、店に来ようか、とツカサは考え始める。


