空威張りビヘイビア
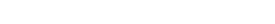
-
「……これはどうしたもんかな」
ツカサは校庭のグラウンドに放置されていたコンクリートブロックに腰かけながら独り言を漏らした。
ふと見上げると、そこには毒々しく安っぽい色合いで光る、ネオン色の夜空が広がっていて、これまたちゃちな電飾のような輝きをする雲が点滅しながら浮かんでいた。
(このカクカクしたデザイン、『ドット絵』って言ったっけ? ……まるでゲームの世界に入りこんだみたいだ)
ネオン色なのは空だけではない。ツカサが通う高校の学園の校庭はいまや丸ごと異界化していた。少し離れた場所にあるサッカーゴールも、今こうして彼が腰かけているコンクリートブロックもやたらカクカクで薄っぺらい。
薄っぺらい癖に、ツカサが座ってもビクともしないという『矛盾』があちらこちらに散らばっていた。
(そう……この空間は、酷く薄っぺらくて、安っぽくて、空々しくて……嘘臭い)
そんな『嘘臭い』存在代表なのが、校庭の桜の樹の上でニヤニヤと嫌らしい笑みを浮かべているタテマエ……『クチサケザル』だ。
頭には大きなシルクハット、首元はたっぷりとした襞襟に包まれていて、ご丁寧にステッキまで持っている。ちょっとした王侯貴族の装いだ。
だがその一方で、身体はつぎはぎだらけ。破れた足先からは綿がボロボロと零れ落ちていてみすぼらしいことこの上ない。
三日月型に歪めた唇は、その名の通りに細く頬まで裂けていて、ガラスをひっかいたような耳障りな笑い声をあげている。
そのくせボタンで出来ているらしい瞳からは、いまいち感情を読み取ることが出来ない。
なにより矛盾しているのがクチサケザルの行動だ。さっきから、こちらが逃げれば追ってくるし、逆に追って攻撃をしかければ、一目散に逃げていく。
タテマエの化け物であるにも関わらず、ツカサを襲ってくることもしない。それでいて、校庭のフェンス……もちろんカクカクで頑丈なそれを一撃で吹っ飛ばすようなパワーを、意味もなく見せつけてきたりもする。
こちらが何もしなければ、クチサケザルも何もしない。何もしないで、樹の上からこちらを嘲笑っているだけなのだ。
(クチサケザルの目的が分からない……勿論、タテマエの化け物である以上、俺と由来者にとって『敵』であることは間違いないんだが……)
ツカサは先ほどから樹上のクチサケザルに向かって、大声出しながら飛び跳ねている今回の由来者である少女に目をやった。
「こらー! そんなとこに上ってないでサッサと降りてきなさいよぉー!」
「HAHAHA☆ YOU ARE 凡人☆」
「ワ、ワタシが凡人!? 天才のこのワタシが!? ふ、ふざけんな! 今すぐぶっ飛ばしてやるから、降りてこーい!」
少女の罵声にもクチサケザルは、ニヤニヤした笑みを返すだけだ。そんな光景を見てツカサは思わず肩を落とした。が、その場から動こうともしなかった。
もちろんあの少女が『ただの少女』であれば、ツカサはあれほどタテマエと接近することを許さなかっただろう。少女は『ただの少女』でも『普通の由来者』でもなかった。その証拠に……。
「ねえ、空! そんなとこで怒鳴ってたって仕方がないよ! 一回離れてさ……」
「うっさい! 元はと言えばカラス丸! あんたが力不足なのがいけないんでしょ!? なんで『カラス』なのに満足に飛べないのよ!」
「あー! ひどーい! 言っておくけどね? ボクの力が足りてないっていうのは、空が未熟ってことなんだからね!? ボクは空の『ホンネ』なんだから!」
「なっ!?」
空の隣にはアクセサリーにしか見えない小さな羽をはやしたカラス天狗の少年の姿がある。空のホンネ妖怪『カラス丸』だ。
だがカラス丸はツカサが呼び出したものではない。空が自分で呼び出したものである。
――『言ノ葉』の力を使って。
「もう! イヤ! なんでイメトレ通りにいかないの!? それもこれもカラス丸が上手く動いてくれないのがいけないんだ!」
空は怒りのあまり、手にした扇子……言ノ葉使いの証でもある扇子をブルブルと震わせている。
だがカラス丸の方も黙ってはいなかった。
「ボクだって! あんなサル、イメトレ通りにズバババーン! とかっこよくやっつけてやりたいよ! でもさ、空の指示がトンチンカンなんだっての!」
「なによ!」
「なんだよ!」
戦闘を放り出して真正面からにらみ合う2人を、頭上からクチサケザルと、それに従う一つ目子ザルたちが嘲笑う。
「HAHAHA☆ YOU ARE短絡☆」
「「うっさーーいッ!!」」
(……こんなにぶつかる由来者とホンネってのは初めて見たな)
潮時かなとツカサは思った。
「あー……空、カラス丸? そろそろ俺も一緒に戦おうか?」
ツカサの提案にカラス丸は目を輝かせて頷いた。
「うん! 頼むよ、ツカサー! 空、分からず屋だからさ」
だが、肝心の空はツカサをきつくにらみつけると首を横に振った。
「お兄ちゃんは黙ってて! っていうか、そこで大人しくしてて! ……こんなタテマエ、ワタシ一人で倒せるんだから!」
「『お兄ちゃん』……ねえ?」
一回浮かせた腰を再び下ろして、ツカサは溜息をついた。
「……これは本当にどうしたもんかな」
ツカサは嵐のような少女が自分の前に姿を現した時を思い出していた――。 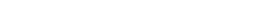
-
前回の『鬼カベ』事件から季節は流れて、通学路ではどこからか気の早い金木犀が香るようになっていた。
ツカサはいつものようにヘッドフォンとマフラーで身を固め、いつものように登校をする。すると。
「おはようございます。ツカサさん」
「ああ、おはよう鹿乃川」
「あら、珍しくきちんとネクタイを締めていらっしゃるんですね」
「そうじゃないとうるさい風紀委員に怒られるからな」
「むぅ」
校門前で交わされる鹿乃川 律との恒例の挨拶をした後、ツカサは玄関で上履きに履き替えていた。そんな彼の背中を後ろから華やかな少女が思い切りひっぱたく。
「おっはよー! 葛葉!」
「……痛いぞ、鈴乃音」
「いや、相変わらず眠そうな顔してるからさ、一発気合いを入れてあげよーかと思ったのよ」
と、ちっとも悪びれない様子で笑うのは、隣のクラスの鈴乃音 舞だ。最近は朝の茶道の修行もあるため麝香猫のキヌに決まった時刻に起こされているらしく、遅刻の回数は見違えるほど減った。
「ねー、葛葉? 今日の放課後ヒマ? また、お茶会しよーかなーって思ってんだけど」
「お前、茶道の修行が忙しいんじゃなかったのか?」
「これも修行だって。うちの流派は『おもてなし』が重要なんだから。今回は特別にあたしが、愛情っぽいもん入れてもて
なしてあげる☆」
「……そのわけのわかんないもんが入ってなければ、付き合ってもいいぞ」
「もー、つれないなー」
「……っと、待てよ。今日はナルキたちと『クッキー食べ比べパーティー』だったか?」
「そうなの? でもいいじゃん。クッキーと日本茶って結構合うし、あたしがナルキたちもまとめておもてなししてあげるよ」
「そういうことなら、問題ないか」
「問題ない☆ ない☆ ……んじゃ、放課後またねー!」
「ああ」
以前は『ミスター不愛想』の名を欲しいままにしていたツカサだったが、驚くべきことに最近では同級生や彼女らのホンネたちと休み時間や放課後を共にするようになっていた。
ともに弁当を食べたり、ともにハンバーガーショップでだべったり……同級生たちとともに放課後に何をするわけでもなくダラダラと過ごしていた。
まるで『普通』の高校生である。
もっともツカサから彼らを誘うということは滅多になく、彼らがツカサにちょっかいを出してくるのが常ではあるのだが……。
(……でも嫌な気分はしない)と思うのはツカサ自身不思議なことだった。
最近は『言ノ葉』の力を使うことがほとんど無かったことも彼の変化に影響があったのかもしれない。
だが彼は忘れていなかった。自分はどこまでも『普通』の高校生ではないということを。
よって彼はこんな平凡な日常だからこそ、周囲の異変に敏感であろうと思った。
(備えあれば患いなしってことだな)
そんな心がけをしていた状態のツカサだったから、その気配に気がついたのだろう。
――自分に向けられる矢のような気配を。
(――なんだ? この気配は? ……もしかして、タテマエ?)
一瞬、ツカサはこの気配をタテマエ出現の予兆かと思ったが、それにしてはあの特有の精神にやすりをかけられるような違和感……雑音がない。
試しにそっとヘッドフォンをずらしてみるも、やはりタテマエの出現を感じさせる雑音は感じられなかった。
(――タテマエじゃない、な。これは『視線』か?)
自分を射る気配の正体に気がついた所で、ふいにその気配は霧散した。
だが、それ以降その視線は、頻繁に付きまとうようになったのである。
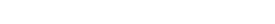
-
「めっずらしーこともあるもんだね。葛葉があたしたちに相談なんて」
「……相談というか確認なんだがな」
「健全な高校生が、あまり放課後に寄り道をするのはよろしくないと思うのですが……」
「固いこと言うな! ほれ!」
「むぐっ!?」
舞にアップルパイを口の中に突っ込まれて律は、ただでさえ丸い目をさらに丸くしている。
「……あら、美味しいですね。このアップルパイ」
「だよねー! チェーン店のハンバーガー屋にしては味がいい!」
律のホンネであるナルキもバニラシェークを満面の笑みですすっている。
「……なんでアンタたちうちの店で毎日だべってんの?」
黄色い声を出して騒いでいる女子たちを冷ややかな目で見つめているのはツカサや律と同じクラスの狗谷 愛だ。バイトの制服に身を包み、ツカサが注文したチーズバーガーを持ってきた彼女の表情は、とてもスマイルを0円で売ってくれるとは思えない。
「え? 葛葉。この騒ぎはどういうことよ」
「俺に聞くなよ」
「馬鹿馬鹿しくて、いい加減なことの原因は大体アンタだって決まってる」
「客に対して随分な言葉だな。狗谷」
「ごめんね。ツカサ。愛、本当は同級生と仲良くしたいけど、きっかけがつかめないだけだから」
そう言いながら余裕の笑みを浮かべるのは、ツカサたちと同じテーブルでポテトを口にしている愛のホンネ妖怪である黒鉄 そうくだ。
「ちょっ! 余計なこと言わないで! クロ!」
「なんだー、狗谷、あたしたちと仲良くしたいのか! ほれほれ! 近う寄れ☆」
「……え!? あ、ちょ、ちょっと!?」
突然舞に抱きしめられて、愛は顔を赤くしたり青くしたりと忙しい。
そんなじゃれ合いを楽しむ主たちの姿を見てキヌは薄く笑うと、ツカサに切り出した。
「……さて葛葉よ。私たちまで呼び出したというからには、何か用があるんだろう? 私はお前さんたちと違って忙しいんだ。さっさと教えてくれないかね?」
「ああ……用っていうか、さっきも言った通り確認なんだが」
ツカサは数日前から感じている謎の視線について、打ち明けた。
「謎の視線、ですか?」
「それってストーカーじゃない? 葛葉、見た目だけはまあまあイケてるし」
「でも、葛葉が『怪しい』と感じてるってことは……またあの化け物が生まれるっていうわけ?」
「タテマエが生まれる気配とはちょっと違う気もするんだが……それも含めて考えた方がいいと思ってな。お前たちにも確認しておきたかったんだ。何か最近、違和感や不審なことはなかった?」
一度、タテマエに触れてホンネと向き合うことを選んだ彼女たちは、基本的に怪異に引かれやすくなるし、そもそも怪異そのものであるホンネたちは自分以外の怪異に敏感なはずだ。
「……些細なことで構わないんだが」
「些細なこと、ねぇ」
「うーん」
考え込んでしまった主たちとは別に、ホンネたちはなんだか苦笑いを浮かべているようだ。
「どうした? 何か心当たりでもあるのか?」
「……タテマエには心当たりがないけど」
「視線の正体なら心当たりがあるかもねえ?」
「え?」
「あれ☆」
ホンネたちが同時に指さした方角には、店内の隅っこに置いてある観葉植物の陰に隠れて、双眼鏡でこちらを監視している少女の姿があった。
大きな双眼鏡のせいで顔はよく確認できないが、明るいピンク色の髪の毛が印象的な少女だ。
少女はツカサたちが同時に自分の存在に気がついたと知ると、観葉植物の鉢植えを派手に倒し、勢い余って机と椅子に激突してひっくり返しながら、慌てて走って店を飛び出していった。
店内は嵐が過ぎ去ったような気配に包まれた。あまりの唐突さに、店員である愛も言葉を失ったぐらいだ。
ようやく落ち着きを取り戻した頃、ツカサがポツリと呟いた。
「……なんだあれは」
「その、制服を見る限り、うちの学校の中等部のように思えましたが……」
「年下の女の子にこんな熱烈にストーカーされるとか……やるじゃん。葛葉」
「熱烈っていうのか? この状況は」
「……不潔」
愛の地の底から響くような声を聞きながら、ツカサは新たな面倒ごとの予感を抱いたのだった。 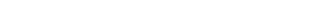
-
それから2、3日の間、ツカサに向けられる視線はかなり露骨なものになってきた。
放課後だけではなく体育の時や休み時間……流石に授業中は無かったが、それ以外の至る所であのピンクの髪色をした少女の気配を感じるようになっていた。
(相手の思惑がなんであれ、いい加減こっちからアクションを起こすべきか?)
放課後になって、一人で校門をくぐる途中のツカサがそんなことを考えていると……妙な引っかかりを感じた。
「ん……なんだ?」
振り返ってみると、水色のサッカーのユニフォームに身を包んだ小柄の少女が自分のマフラーの先をちょこんと引っ張っていたのである。
「……って、お前は」
服装こそ異なっていたものの、目の前にいる少女はまぎれもなく、前にハンバーガーショップで見かけたピンク色の髪の少女だ。
シャギーが入ったボブカットは毛先が軽快に揺れている。あの時は分からなかったが、眉毛よりも高い位置で切られた前髪からは綺麗な形の額が覗いていた。アーモンド型をした瞳はアメジストの輝きをしていて少女の利発さを、微笑んだ口元から覗く小粒の真珠に似た歯は少女の活発さ、そして健康さを現しているようだ。
一見すればただの愛らしいスポーツ少女だったが、次の瞬間、彼女は驚くべき言葉を口にする。
「ワタシ『葛葉 空』だよ! ……初めまして! お兄ちゃん!」
「……はぁ?」
少女はこぼれんばかりの笑みを浮かべて、ツカサのことを『兄』と呼んだのである。 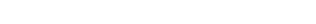
-
「……それで、またあたしたちが呼ばれたってワケ?」
「ああ……とりあえず『人違いだ』と言っておいたが」
愛がバイトをするハンバーガーショップにはバイト休憩中の愛、律、舞が集まっていた。いつもはツカサが来るたびに文句を言ってくる愛も、ツカサの家族構成に興味があるのか、険しい表情を浮かべるだけにとどまっている。
「『お兄ちゃん』ですか……」
「……心当たりあるの? 葛葉」
「全くない。俺はあんな娘に出会ったことはない」
「ではなぜ彼女はツカサさんのことを兄と呼ぶのでしょう?」
「……見当もつかない」
ツカサの話を聞きながら、ずっとスマホをいじっていた舞が、おっという声をあげた。
「葛葉 空……確かにうちの中等部にいるみたいねー。2学期の頭に転校してきたみたい。女子サッカー部所属」
「鈴乃音さん、どうしてそんなことがすぐに分かるんですか?」
「んー? あたしの『可愛い妹ちゃん』たちに教えてもらったから☆」
自分に素直で我がままな……良い捉え方をすればさばさばしていて堂々とした振る舞いをする舞は、ある種の女子に人気が高い。恐らく彼女を崇拝する中等部の女子から情報を集めたのだろう。
「鈴乃音、他にも何か情報はないか?」
「ちょーっと待ってねー……へー、空ちゃん、編入試験はほぼ満点、おまけに体育テストも全国レベルの成績だってさ。サッカー部でも選抜チームに選ばれてるみたいだし、ブンブリョードーってやつ?」
「……あの娘、とても『ブンブリョードー』には見えなかったけどな」
先日、ここで起こった騒動を思い出してツカサは肩をすくめた。
「……ってことは、『葛葉』っていうのは本名か」
「偶然の一致にしては出来過ぎって感じがする」と愛が首をかしげる。
「その……お父様かお母様が異なる妹さんがいらっしゃるという可能性は?」ツカサのプライベートに踏み込んだ質問を、やや気まずそうに律が質問をした。
「ない……はずだ。だって、俺の両親は……」
――オレノリョウシンハ? オレノリョウシンダッテ?
その瞬間……ツカサの意識は急に遠のき、過去の情景が砂嵐交じりに再生される。
黒く不吉な大人たちに囲まれる少年。そんな大人たちよりも遥かに不吉で暗い瞳をした少年がゆっくり口元を吊り上げる……すると次の瞬間、大人たちは地面に倒れ伏していた。
「皆、死んじゃえばいいんだ」
少年が呟くと、周囲は炎に包まれる。
――あれは一体いつ、どこで見た光景だったのか? ツカサが自分の過去にあと少しで手が届くと思った瞬間……。
「見つけたぁーー! お兄ちゃん!」
場違いな大声で、ツカサの意識は現実へと引き戻されていった。
大声の主である少女……空は目を三角にして大股でツカサの元にやってくる。どうやらサッカーのユニフォームから着替えてきたようだ。中等部の薄いグレーのセーラー服の上に、奇妙なデザインのフードがついたパーカーを被っている。
「酷いよ! こーんな可愛い妹がわざわざお兄ちゃんに会いに来たっていうのに! 無視するなんて!」
空が猛烈な勢いでテーブルを叩く度に、ツカサたちが食べていたポテトフライの山とドリンクが奇妙なダンスを踊り、空の右手につけた手作りらしいミサンガも揺れていた。
「……そーいう態度、ちょっとクール過ぎるよ! お兄ちゃん!」
「……テーブル叩かないで。他のお客さんの迷惑になるから」
愛から注意を受けた空はテーブルを叩くのを止めると、愛と律、それに舞をじっと見比べている。
「……お兄ちゃん、この中の誰がお兄ちゃんの彼女なの?」
「は、はぁッ!?」
「か、か、か!? かの、かの、かの!?」
空の言葉を聞いた愛と律は目を見開いて動揺していたが、舞だけはイタズラな子猫のように笑った。
「ふふふ……空ちゃん、誰が葛葉と付き合ってるのか、気になるの?」
「そりゃあ、妹としては自分の兄がどんな女の人と付き合ってるのか知るのはマストっていうか必須項目っていうか、当然の権利じゃない?」
(……頭が痛くなってきた)
ツカサは頭をぐしゃぐしゃに掻きむしって唸りながら空をにらみつけた。
「……こいつらは別に俺の『彼女』じゃない」
「えー、そうなの? ま、本人が言うなら確かかな」
ツカサの言葉を聞いた女性陣は、ほっとしたようながっかりしたような、実に複雑な表情を浮かべている。
「……そして、もし俺に彼女が出来たとしても、お前が知る権利はない……お前は俺の妹じゃないからだ」
「それは確かじゃない! さっきも言ったでしょ! ワタシは『葛葉 空』! お兄ちゃんの妹なの!」
「さっきも言ったが、人違いだ。葛葉の家にお前みたいな娘は……」
『いない』と言いかけたところで、ツカサの意識は再び遠のきかける。
そんな頭を振って、ツカサは目の前の問題に集中した。
「……葛葉の家にお前みたいな娘はいない」
「むきーー! いいもん! ワタシには『葛葉の家の娘』っていう確かな証があるんだから!」
「証だと? おい、それはどういう……」
ツカサが質問には答えずに空は右腕を高く上げた。するとその手の中には一本の扇子が現れる。
(あれは? ま、まさか! や、やばい!)
ツカサが空を止めようとする前に、彼女は祝詞を口にした。
――言ノ葉使いにしか使えないはずの祝詞を。
「……我は言ノ葉使い、我が呼び声に応えよ! 我がホンネよ、姿を現せ!」
「バ、バカ! こんなところでホンネを呼び出したり……した、ら……?」
ツカサたちはハンバーガーショップに突如怪異が出現するという最悪の状況を想像して息を呑んだが……彼らの予想に反して、目の前に姿を現したのは、クリッとした大きな目と、頭に一本だけ逆立って生えた毛が特徴のなんとも間の抜けたデザインのミニペンギンだった。
「カー!」
ミニペンギンはテーブルの上に立つとツカサに向かって、ぴっと翼を拡げる。どうやら挨拶をしているようだ。
「まぁ! 可愛らしい!」
「ふっふーん! どうだ! この勇ましいホンネを呼び出せる、ワタシは天才言ノ葉使い! つまりは葛葉の家の娘! ってこと!」
「……勇ましいっていうか」
「ゆるキャラって感じだよね」
「カー(怒り)!」
好き勝手に言う舞たちの言葉を聞いて、ミニペンギンは怒っているようだ。なるほど、怒る様子は確かに空に似ている気がしなくもない。
ツカサは自分の扇子を取り出すと念のため確認してみた。
「……確かに目の前のコイツは、ホンネ妖怪だ」
「そうだよ! 名前は『カラス丸』って言うの!」
「カー(得意)!」
「こいつ、カラスだったのか……」
人の心が真に望む願いから生まれるホンネ。そのホンネを具現化できる空は、どうやら紛れもなく言ノ葉使いのようだ。しかもそれだけではない。
(この娘……ホンネを擬態化させていたというのか?)
今の空はグレーの中等部の制服姿になっていた。どうやら空は、自分のホンネをパーカーに擬態化させて身にまとっていたようだ。そのことは空が言ノ葉使いとしての能力に優れていることを示していた。
「……どうやらお前が言ノ葉使いというのは真実らしいな」
「さっきからそう言っているじゃない! お兄ちゃん!」
「だがその『お兄ちゃん』というのには納得出来ないな……俺にはやはり『妹』なんていない」
「そんなーッ! あんまりだーッ!!」
「カー(怒り)!」
空は大声でわめきながら、再びテーブルをメタルバンドのドラマーのような勢いで叩き始める。するとそれに合わせたかのようにカラス丸が甲高い鳴き声と共に羽を辺りに撒き散らす。
結局その騒動は、眉間の青筋を震わせる愛によって空が店内からつまみだされるまで続いたのだった。 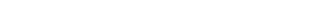
-
それからというもの空は毎日ツカサに付きまとうようになった。
朝は通学路でツカサを待ち伏せして、一緒に校門までくっついて歩く。お昼休みになればこっそり高等部にやってきて、ツカサたちと一緒に弁当を食べたり、ナルキからお菓子をもらって食べている。
クラスメイトたちは突然現れた『中等部の女子』『葛葉 ツカサの妹』に最初は驚いていたようだが、適応力が高い彼らはすぐに彼女を日常の風景の一部として受け入れるようになっていた。
そして空は放課後、ツカサが帰ろうと玄関から姿を現すと、例えサッカーの練習中でも休憩を入れて、必ずツカサの元にやってくるのだった。
ハンバーガーショップでの騒動があった後に、空から改めて聞いた話だと、彼女が所属する中等部の女子サッカー部の選抜メンバーは、高等部に交じって練習をすることもあるため、特別に高等部のグラウンドを使用することが許されているらしい。
空はそこでエースストライカー(自称)として練習している最中に、偶然ツカサを発見して『彼こそ生き別れになっていた自分の兄!』と直感で感じたと語った。
「直感って……どうしてそんな大事なことが感覚で分かるんだよ」
そうツカサが尋ねると
「なんでって言われても……ほら、ワタシ天才だし? 直感も天才的っていうか」
「答えになってないだろう」
「でもでも! ビビッと来たのは本当だもん! 結果的に、お兄ちゃんは葛葉の家の言ノ葉使いだったワケだし、何にも問題はないでしょ!」
というのが本人の弁だった。その日の放課後も空はいつもと同じようにツカサの周りに子犬のようにまとわりついてきた。

「お兄ちゃん! ワタシ、今日サッカーの練習試合があるの! ワタシのパーフェクトなプレイ、絶対見にきてよね!」
「……別にいいけどな」
相変わらず『妹』だと認めることは出来ないが、この奇妙で破天荒な少女の存在をツカサは理解し、それなりに受け入れることが出来るようになっていた。
つまり『慣れた』のだ。
そして『慣れた』が故に、空のパーソナルな部分に一歩踏み込んだ。
「……お前ってさ、毎日俺に付きまとってていいのか?」
「ほえ? どーいう意味?」
「クラスメイトやチームメイトと付き合わなくていいのかってことだよ。中学や高校の女子って、友達付き合い大切なんだろう?」
他人に関わらないように避けて生きてきたツカサでさえ、最近では『友達っぽい』代わりの利かない存在が出来た。
ならば目の前にいる、他者と積極的に触れあいを持って巻き込もうとする台風の目のような少女にとって友人付き合いはさぞ大事なのではないか? ツカサはそう考えていたのだ。
だが彼の予想に反して空はぷいっと顔を背けてしまった。
「……友達なんかいらない」
「……空?」
「だって! クラスメイトもサッカーのチームメイトもみんなレベルが低いんだもん! 知能指数低い馬鹿ばっかだし、くだらない話には真剣になるくせに、サッカーではまともにパス出しも出来ない……みんなワタシの足を引っ張ってばかりのお子様ばっかり! あんな奴らと一緒にいてもつまんない! 友達なんてくだらない! ワタシにはお兄ちゃんがいればいいもん!」
空は一気に言うと、両頬を大きく膨らませている。
まるで餌を頬張ったハムスターのようだな。とツカサは思った。
「……お子様ばっかりって……実際にお子様だろう。お前も、そいつらも」
「なっ!? なんてこと言うの!? 信じらんないッ!」
「事実だろう」
沸騰寸前のヤカンのような勢いと熱で怒る空を前にしても、ツカサは軽く肩をすくめるだけだった。
「馬鹿! 馬鹿! 馬鹿! お兄ちゃんの馬鹿ぁーーッ! 冷血金髪マフラー男ーー!」
という謎の罵声を浴びせると、サッカーで鍛えた自慢の脚力を生かし、もの凄いスピードで走り去ってしまったのだった。
「金髪マフラー男って……なんつーボキャブラリーだよ。アイツ、頭良かったんじゃないのか? ……はぁ」
ツカサが思い切り脱力していると、背後からクスクスと笑い声が聞こえてくる。
「なかなかユニークな悪口じゃん? 葛葉」
「鈴乃音か……」
舞はしなやかな猫のようにツカサに近づき、腕を取るとこう言った。
「ねー、葛葉? 空ちゃんには振られちゃったみたいだし、今日はあたしとデートしよ☆」
「デートはしない。だが……お前に聞きたいことがある」
「なぁーに? ワタシのスリーサイズとか?」
「そんなもん聞くか……その、前にお前と仲のいい中等部の奴らから、空のことを聞いてたよな?」
「聞いてたね」
「その時、そいつらは空のこと、どんな風に言ってた?」
「……気になる?」
「……まあな」
「じゃあ……」
舞はにんまりと笑うとツカサの腕を強く引っ張った。
「とりあえず、立ち話もなんだから……お茶でも行こ☆」


