空威張りビヘイビア
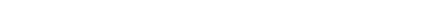
(――ここは?)
ツカサが目を開くとそこは辺り一面赤が支配する世界だった。
炎の赤。
血の赤。
そして憎悪の赤。
(一体、ここはどこなんだ? 俺は何故こんなところにいる?)
一歩足を踏み出すと、ぴしゃりと赤い液体がしぶきを上げる。
(これは……まさか……)
ふと自分の両手を見ると、真っ赤に濡れていた。
妙に粘りつき、錆びた鉄のような匂いのするそれは、確認するまでもなく生き物の血液だった。
「――っ!」
思わず息を呑み、後ずさるツカサの足に何かがぶつかる。
それはかつて人間だったものの欠片だった。
引き裂かれ、蹂躙され、もはや人間の尊厳すらも剥がされたような無残な欠片。
よく見ると一面に広がる血の海の中には、そんな肉の塊が、ぷかぷかとうきのように浮かんでいる。
その数は、10や20ですむものではない。
一体、どれだけの命が踏みにじられたというのだろうか?
(一体……何が起こったんだ!?)
ツカサの疑問に答えるものは、この濃厚な死が漂うこの世界には存在しない。
地は血の赤に。
天は炎の赤に染められている。
唯一、夜空にある大きな丸い満月だけは青白く冷たい死の輝きを放っていた。
恐らく地獄とはこのような光景なのだろう。
この世界では生あるものの方が異常なのだ。
――そんなことをツカサが考えていた、その時……。
「……皆、死んじゃえばいいんだ」
「! 誰だ!?」
声が聞こえた方向に振り向くと、そこにはいつの間にか幼い少年の姿があった。
夜空に浮かぶ月の光を写し取ったような、色を失った銀色の髪。
血の赤よりも炎の赤よりも、深い真紅の瞳。
「……お前は一体……?」
ツカサの質問に少年は答えない。
ただ壊れた人形のように同じ言葉を繰り返す。
「……皆、死んじゃえばいいんだ」
だが少年の瞳は、人形のような虚ろなものではなかった。
その瞳は憎悪の炎で鈍く輝いていた。
「……お前は誰なんだ?」
幾度か目のツカサの問いかけに、少年はようやくツカサの方に目を向けた。
「……ツカサ」
「えっ……? どうして俺の名を?」
「……ツカサ、君は僕の……」
少年の瞳から憎悪の炎が消えている。
だがその代わりに彼の瞳は光を失い、底のない井戸のような暗い絶望の影で覆われていた。
「……お前は一体誰なんだ! 何故俺の名前を知っている!?」
「……ツカサ。さようなら」
少年の顔が歪む。
その表情は笑ったようにも、泣いたようにも見えるものだった。
「教えてくれ! お前は一体俺の何なんだ!?」
ツカサは、驚き思わず彼に向かって手を伸ばした……。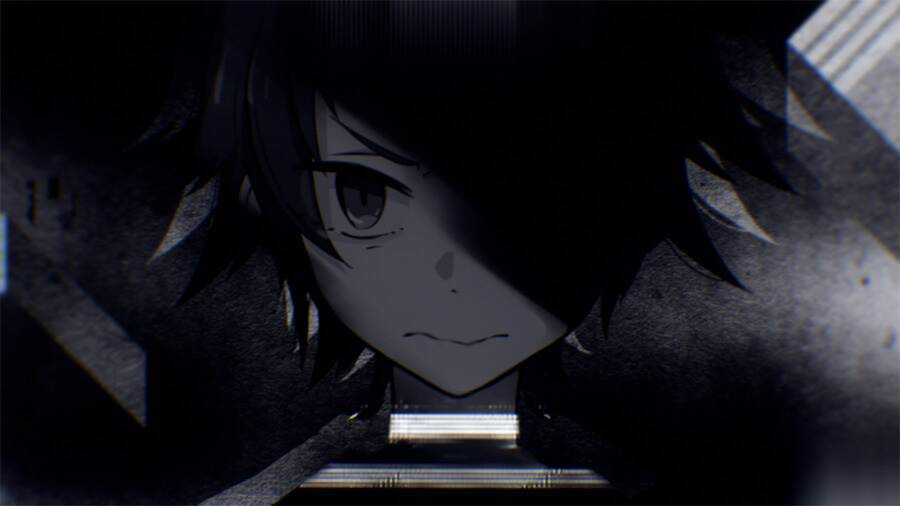
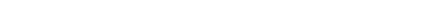
「――はっ!? 夢……か」
ツカサは荒く呼吸をしながら、ベッドから身を起こした。
辺りを見回すと、いつもと変わらぬ6畳1間の安アパートの風景が目に入る。もちろん周囲に血も流れていないし、無残な遺体も存在しない。
そして……あの少年の姿もない。
(一体……あいつは誰なんだ? あの光景は何を意味しているんだ?)
ツカサは額に浮かんだ汗を手で拭いながら、先ほど見た夢のことを考えた。
この頃、毎日のように見るあの赤い死の夢……。
(……空たちに出会った頃から見るようになったんだよな)
最初はぼんやりと赤い空間にいるとしか認識できなかったが、夢を重ねるごとに、段々と凄惨な情景を感じ取れるようになっていた。
そして今日の夢では、初めてあの少年の姿を確認することが出来たのだ。
(あれは……一体誰なんだ?)
いくら考えても、あの景色にも少年にも心当たりはない。
思わずツカサが溜息をついていると……。
「……おや。なんて冴えない顔をしているんだ。葛葉」
「麝香猫……なんでお前がここに?」
ツカサの部屋の扉を開け、姿を現したのは麝香猫のキヌだった。
「……っていうか、なんでお前、俺の部屋のドアを開けられるんだ?」
「この程度の錠前を破るなど、異形の身である私には造作のないこと……とはいえ、今回はここの大家に鍵を貸してもらったんだがね」
「そんなほいほい鍵って借りられるもんなのかよ……セキュリティはどうなっているんだ?」
「なに、『親戚の子の具合が悪いと聞いて、駆けつけてきた』と言ったら、快く貸してくれたよ」
「この詐欺師め」
「なに、私は『麝香猫』……人前で猫の一つや二つは被るのは朝飯前さ……それに、あながち嘘とは言い切れない。私は主にお前の様子を見に行けと言われたのだからね」
「……鈴乃音に?」
「ああ。『最近、葛葉の調子が悪そうだからモーニングコーヒーを淹れにいってあげて☆』……と言いつかってね。こうしてわざわざ出向いてやったわけさ」
キヌはいかにも『面倒だ』と言わんばかりの表情で、手にしたコーヒー豆の入った袋を揺らしている。
「ほら、とっとと顔を洗ってきな……その間に気分がしゃんとするような珈琲を淹れておいてやるから」
「……分かった」
ツカサはキヌに言われるがまま、洗面台に向かう。
(なるほど……これは確かに酷い顔だな)
目の周りには青黒い隈が浮かび、冷や汗で顔はべたついている。
赤く充血した両の目は、ツカサに先ほどの赤い夢を思い出させた。
思わず自分の手の匂いを嗅ぐと、濃厚な血の香りが漂う気がする。
(……馬鹿な。あれは夢なんだ……錯覚に決まっている)
それでもツカサは指先が冷えて真っ赤になるまで手を洗うことを止めることが出来なかった。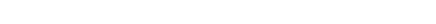
キヌの淹れた珈琲はいつもよりも深い香りで渋みが強く感じられ、確かに頭がクリアになる味わいだった。
「……それで葛葉、お前さん何だってそんな死神みたいな辛気臭い顔をしてたんだ?」
「……酷い言われようだな」
「フン……誰だってさっきのお前さんの顔を見たら、そう言うだろうよ……現に、私の主以外の娘さんたちも、お前さんの様子には気がついているようだ」
「……そうなのか?」
「ああ。口には出さないが、お前さんのことを案じているのが伝わってくるよ……女子に心配をさせるのはいただけないね? 葛葉」
「……悪かったよ」
「私に謝っても仕方がないだろう。謝るなら、お前さんの身を心配している主たちに言いな……ん?」
「どうかしたのか?」
キヌは珈琲カップをソーサーに戻すと、皮肉な笑みを浮かべた。
「……どうやら、お前さんの不調にも気がつかず、また気も使わないような暴風娘がやってきたようだよ?」
「えっ?」
次の瞬間……。
「お兄ちゃん! ちょっと! 聞いてよー! カラス丸のおバカがねー!」
「なんだよー! ボクがバカなら、空は間抜けだ!」
「な、なんですってーー!?」
アパートのドアを破るような勢いで開け、中に飛び込んできたのは、空と彼女のホンネであるカラス丸だった。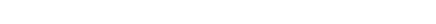
「――それでカラス丸さんが成長しないことを、空さんは悩んでいるんですね?」
「うん……」
狗谷 愛の働くファーストフード店では、いつものようにいつものメンバーが1番奥のテーブル席を陣取って、空の悩みを聞いていた。
テーブルの上には『天才☆空ちゃんのお悩み相談室』と書かれた厚紙が置かれている。
いうまでもなく空自身が用意したものだ。
これだと空がツカサたちの悩みを解決するように見えるが、真実は真逆だった。
「……カラス丸、『クチサケザル』を倒した時は、すっごくカッコイイ大人になったのに……またこんなチンチクリンになっちゃった」
「チンチクリンってなんだよ! ボクより空の方が背、ビミョーにちっちゃいじゃない!」
「なっ……!? ひ、人が気にしていることをーー!? ムキーーッ!!」
「……これ以上騒ぐなら、店を出ていって」
「はいはい♪ 2人とも喧嘩しないの☆」
鈴乃音 舞や愛に注意をされた空は、深呼吸を繰り返し、気を落ち着けると、再び話し始めた。
「と、とにかく! いくら念じてもカラス丸が大きくならないの……これってどういうことなのかな? お兄ちゃんも分からないって言うし……」
「そうなんですか? 葛葉さん?」
「ああ。正確には『カラス丸を改めて変化させる方法が分からない』ということだな……空のタテマエである『クチサケザル』を倒したときは、確かにカラス丸は熊野烏丸へと成長した。だが……それは恐らく、俺と空の力が合わさったのと『場』の特殊な力によるものだったんじゃないかと思う」
「ああ……なるほどね」
「『場』の力……何、それ?」
愛のホンネである黒鉄 そうくはツカサの言葉に頷いているが、主である愛は、理解が出来なかったらしい。
そうくは穏やかな笑みを浮かべ語る。
「……『クチサケザル』は空さんのタテマエで、2人が戦っていたのは、そのタテマエが作り上げた結界内……つまり、空さんの精神世界と言えなくない。空さんが元から持っている豊かな想像力こそが結界を作り上げるため必要不可欠な要素(ファクター)だったはずだ」
そうくの言葉にキヌが続ける。
「……だから葛葉たちは想像力が物を言う世界で、強さを発揮することが出来たんだ。未来の自分の能力をイメージすることで、その力を前借するなんていう大技が使えたのは『場』の力によるというのはそういうことさ」
「……それじゃあ、現段階では空さんは熊野烏丸さんを呼ぶことは難しいということですね」
「ホンネは20歳になってから! ってね☆」
「…………」
鹿乃川 律と彼女のホンネ、三鹿 ナルキの言葉を聞いた空はうつむいて餌を頬張ったリスのように頬を膨らませている。
だが律たちの意見が正しいと、自分でも薄っすら気がついていたのだろう。
空はむくれるだけで、特に反論をしてこようとはしなかった。
(ここまでは、俺も予想していたことなんだが……)
「……なぁ、鹿乃川、鈴乃音、狗谷……お前たちもホンネは最初、別の姿をしていただろう? そこから一気に成長した……何かコツみたいなのはないのか?」
ナルキは空よりも幼い童子、キヌは愛らしいが何の役にも立たない御稚児さん、そうくは儚い少年の姿をしていた。
それが主の成長と共に、心身ともに急速な成長を遂げ、今の姿へと変化したのだ。
もしその変化を促すきっかけのようなものがあれば、空に学ばせてやりたいとツカサは考え、今回彼女たちに声をかけたのだが……。
「コツって言われてもねぇ~?」
「……あの時は夢中だったから、良く覚えてない」
「私の場合、餓鬼ちゃんが大人になったタイミングは遅かったですが……それでも何か特別にしたということはありませんね」
「そうか……」
ツカサはやっぱりダメだったかと、軽い溜息をついた。
(それでもタテマエとの戦闘時よりも後でホンネが変化した鹿乃川には、少しだけ期待していたんだが……そう上手いことはいかないか)
ツカサは主たちにしたのと同じような質問をホンネたちに投げかけるが、彼らの答えもはっきりしないものだった。
「……そもそもさ、なんで空ちゃんはそんな急に成長したいワケ?」
生クリームがてんこ盛りになったコーヒーをストローでつつきながら舞が尋ねる。
「確かにイケメンで頼りになる相棒に会いたいって気持ちは分かるけどさぁ、そっちのカラス丸くんだって素直で可愛いじゃん……葛葉から聞いた話だと、熊野烏丸には将来会えるんだし、今は頑張ってしゅぎょーしてればいいんじゃない?」
「……そうだけど、それじゃ遅いの」
「遅い? 何がだ?」
この時のツカサはてっきり『天才のワタシにこんな中途半端なホンネは相応しくない』『もっと本当の自分は強いんだ』……そんな背伸びをしたいという意見から空が成長を急いでいるのかと思っていた。
だがツカサの予想に反して空はちらりとこちらを伺うような視線を向けると、やや気まずそうに口を開いた。
「……ワタシ、早くツカサお兄ちゃんが、ワタシの本当のお兄ちゃんか知りたい。だから熊野烏丸に会いたいの……アイツなら、きっと真実を知っているはずだから」
「……なるほどな」
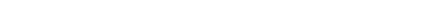
――熊野烏丸との別れの時に話は戻る。
易々とクチサケザルを撃破した熊野烏丸は、それから優雅に世界へと旅立っていった。
そして自分が言った刻限きっかりに、空の元に帰ってきた熊野烏丸は、ひとしきりの間、世界旅行の感想を2人に聞かせた。
「……この世界は我の翼にはいささか狭かったな。それでも諸外国の怪たちとの会話は、なかなか胸躍るものであったよ」
「えっ!? 熊野烏丸、外国の言葉、分かるの!?」
「然り。我は天才だぞ! 言語の壁なぞ無いに等しいわ!」
「すごーい! ね、お兄ちゃんもそう思うよね?」
「ああ」
「……『お兄ちゃん』とな?」
今まで得意満面の笑みを浮かべていた熊野烏丸が、実に珍妙な表情を浮かべる。
「どうかしたの?」
「我が主よ。主が言う『兄』というのは、同じ親から生まれた年上の男のことか? それとも目上で敬意を払う男のことか?」
「えっ!? も、もちろん、同じ父上と母上から生まれたお兄ちゃんってことだよ?」
「……なるほどなぁ」
熊野烏丸は1人で何かに納得し、しきりに頷いている。
「……言ノ葉の繰る力とは、即ち人の心を操る力……こういうこともあるのだろうよ」
「……おい、熊野烏丸。さっきから一体何を言っているんだ?」
「そうだよ! お兄ちゃんとワタシがどんな関係だって言うの!?」
熊野烏丸はツカサたちの質問には答えずに、いつもの自信に満ちた笑みを浮かべると空をギュッと抱きしめ、自分の腕の中に閉じ込めてしまった。
「むぎゃっ!?」
「あー、よいよい。何も案じることはないぞ。我が主よ……其方は花のように笑って日々精進をすればよい」
熊野烏丸は空を抱きしめながら、彼女に聞こえないように、そっとツカサに耳打ちをする。
「……葛葉 ツカサよ。其方は己が根源(ルーツ)をどう心得ておる?」
「はっ?」
「生きとし生けるものには父があり、母があり、祖先がある。脈々と受け継がれてきた遺伝子の織物(タペストリー)、同じ根源(ルーツ)を持つ者たちの強い絆の物語……つまり歴史があるのだ。それ故にか弱き身でも滅びを免れる法を自然と知ることが出来る……それと比べ我ら言ノ葉の怪は、主はあれども、歴史を持たぬ。だが歴史の代わりに生まれながらにして我らは己が使命を知っているのだ。それ故に主と自身を守るため、強大な力を持つことが必要とされ、また力を有することが出来る……我の言うことは理解が出来るか?」
「……まぁなんとなくは」
「そうか……ならば己が根源(ルーツ)を探せ。葛葉 ツカサよ……己に至る物語を知らず、それでいて巨大な力を持つ其方は、ある意味我が主より不安定で危険な存在よ」
「……俺が?」
「然り。例えるならば、今の其方は限界まで満たされた盃のようなもの……このままでは、いつ中のモノが溢れ出てくるとも限らない……その時中から溢れ出てくるモノに、其方は飲まれてしまうやもしれん……そうなれば我が主は泣くだろう……我が主を悲嘆に暮れさせるような真似をすることは罷りならんと知れ」
「……分かったよ」
「ふむ……それでは」
熊野烏丸は空を開放すると、その頭を撫でた。
「ひと時の別れだ。我が主よ……我に至る織物をその男を道しるべとして、辿て来るがいい……さらばだ!」
そう言い残すと、熊野烏丸は再びカラス丸へと変化してしまったのだった。


