空威張りビヘイビア
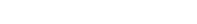
-
朝。
あれから何週間かが過ぎたが、校門消失事件は、不思議なくらい話題にならなかった。
数日後に控えたバレンタインの祭事のほうが余程盛り上がっている。
対外的にお堅い学舎を気取って見せても結局、学生の興味向きはそういうものだ。
誰彼となく、なんとなくそわそわとした感じと、妙なやる気が入り交じった空気が漂う。
「おはようございます。おはようございます。ああ、そこのあなたネクタイが曲がっています。おはようございます」
今年ばかりは、風紀委員たる鹿乃川律も例外ではなかった。
生徒たちに次々挨拶と服装チェックをする、朝の門番たる委員の務めをこなしながら、遅刻寸前にいつも来るその顔を待つ。
現れた。
律は微笑みを極力隠しながら、彼の前に立つ。耳に蓋をしている彼に聞こえるよう、なるべく近づいて言う。
「おはようございます、葛葉ツカサさん」
「ああ、おはよう鹿乃川」
「またヘッドフォンで外界を遮断していますね」
「今朝は特に耳が寒いしな」
「言い訳が上手です」
「違反切符、切らないのか」
「耳にしもやけが出来る人がいる、と上に掛け合ったら、耳当てには特例のお許しが出ました」
「それは幸いだ」
「予鈴二分前です。急いでくださいね」
手を軽く挙げて昇降口に向かうその後ろ姿を、律は見送る。
ツカサの被るヘッドフォンのコードは、今はどこにも繋げていない。そうすることで今のところ、看過されていた。「どうして戦えたのですか、葛葉ツカサさん。あんな怪物と」
先日。あのコトワレとの戦闘を経た放課後、当然の質問が律からツカサへとぶつけられた。
「どうしてって言われてもな。これが俺の能力だ」
「餓鬼ちゃんを操ってバケモノと戦うことが、あなたの能力ですか?」
「そうだ」
「だけど巨大なバケモノが私から出たのも、あなたのせいだと、あなたの口から聞きましたが」
「そうでもある……」
「マッチポンプ、と言います。自分で火をつけて自分で消すのは、嘘の英雄です。いけませんよ?」
「……あんた、時々指摘が真面目すぎて友達から嫌がられるタイプだろ」
「む。そういう本当のことを言う人、嫌いです」
そのつもりはなかったのだが、人気のない廊下の突き当たりで、互いにやんわり、睨み合う。
ツカサのほうから、表情を緩めた。別に、ケンカをしたいわけじゃない。
「無粋を承知で言うが……俺なりに、責任を果たしたかったんだ」
「あ――」
「たとえ、あんたや俺自身が望んだことでなかったとしても。出てきたものには、片をつけたかった」
律が由来となり、ツカサが呼び出してしまったバケモノ。
律の隠された本心、隠していたかった気持ち。コトワレはそれを勝手に汲んで、暴れ出した。
あの時ヘッドフォンが取れて隙が出来ていたとは言え、ツカサは自身の能力による、責任を感じた。
とめなくては、と思ったのだ。
「ええと……すみません。理解しました。ごめんなさい」
律は頭を下げる。ツカサ自身の蒔いた種でもあるが、同時にツカサは、律のためにも戦ってくれたのだ。
「いや、まあ。説明もなしにあんなバトルが始まったら普通は困るよな」
「実際、困りました。何事かと」
「正直だな」
「……けど、ちょっとだけ、すっきりしました」
律も表情を解す。奇妙だが、救われた気持ちになれたのは本当だった。
壊したい。法規法則など無視して暴れたい。でも、誰も傷つけたくはない。守りたい。自分の中に眠っていたそんな矛盾が、あの戦いでほどけたように、律は思っていた。
「すっきりしましたので……お礼を言いたいのです。葛葉ツカサさん」
「礼などいらない。さっきも言ったが、俺は自分の責任を全うしただけだ。他は、ついでだ」
「ついで呼ばわりはひどいです。私だって、一定の解決を体験しました。あなたが戦ったおかげで、楽になれたんです、私。ですから」
「ですから?」
「ありがとう、ございました」
「……いや。だから。お礼とかは、不要でだな」
「いいえ。お礼にお菓子をあげます。校則では校内で無闇な間食をしてはならないことになっていますが、実は私はお菓子が好きなのです。こっそり食べるのが大好きなのです。ですので、ツカサさんに、おすそわけをします」
律は言い募った。
「お菓子?」と訊くツカサ。
「はい……ああっ、今は持ち合わせがありません。ロッカーの奥に隠しているものならあるかも……」
「いや、待て。気持ちはわかった。気持ちは嬉しいが」
「なら是非。気持ちを受け取ってください。すぐに探して持ってきますので」
意外な律の強引さにツカサはたじろぐ。と、そのとき。
ぼふん、と軽い音がして、子鹿姿の餓鬼ちゃんが中空に現れた。
「――え?」
意図したことではない。驚いた律が捕まえようとするが、餓鬼ちゃん鹿はぴゃらぴゃら笑いながら浮いて踊っている。そして、
「何?」
それはツカサの操りでも律の命令でもなく、餓鬼ちゃん本人(?)のパワーの迸りだった。魔法と形容しても良い。何かが空で光った。廊下の突き当たりの天井が、ぱかっと開いた。
ざらざらざらざららー。
そこから大量の小さな包みが、律とツカサの前に降り注いだ。
「飴玉!?」
「らしいな」
唖然。呆然。
「ヘェーイ!! ナニ馬鹿面してんだッ☆」いつの間に変わったのか、餓鬼ちゃんが毒舌童子姿だ。「あんぐりしたそのオオグチに・ちょっぱちゅっぷすきゃんでぃーを・しこたま・詰め込んでやろうかッ☆」
「おい」ツカサは言うと扇子を取り出し、餓鬼ちゃんに振り向ける。「お前の仕業か?」
「ふへへ☆ ご名答☆」餓鬼ちゃんが返事をすると、天井が何事もなく閉じた。
何十個だろう、ぶちまけられた飴玉は無造作に廊下に広がって、そのうち隣の階段まで落ちていきそうである。
律は他の生徒や教師に見つからないだろうかときょろきょろ見回し、
「そ、そうだ。ホウキとチリトリ」
と掃除用具置きへ走り出す。
ツカサは呆れながらも笑って、
「どうせなら俺の好きなチョコレートでも寄越してくれよ」
餓鬼ちゃんの頭をなでなでしてやる。
「なんだい・欲しい物があるなら・先に言えッ☆」
ぽいっと、餓鬼ちゃんは無造作にチョコレート・バーを投げてくる。ツカサはすかさずキャッチして、ポケットにしまった。
「なかなか便利な奴だ」
開いた扇子をぱちんと閉じる。
「ぴゃはははは☆」
と笑いの響きを残しながら、餓鬼ちゃんはすぐさま鹿になり、さらに、ぽふっとその場で消えた。
廊下の隅の出来事、今のところは他の誰にも気づかれていない。
戻ってきた律は散らばった飴玉の包みを丹念に箒でかき集め、ちり取りにしまっている。
「もったいない」
ツカサは屈んで、床の飴玉を幾つか拾い上げ、包みをひとつ開いた。それを口に含んで、律に言う。
「結構うまいな。いつも食ってるの、これなのか?」
「えっ? あっ、この飴の種類、確かによく私が舐める奴です」
「ほら」飴を一個、律に差し出す。「あんたもひとつ」
「は、はあ……」律は渋々といった風に受け取り、包みを開いて食べる。「もぐもぐ」
「これも願望だ」とツカサは悪戯に微笑む。
「願望」と律。
「あんたが飴を欲しいと思ったから、餓鬼ちゃんが出してくれたんだ。鹿乃川。便利じゃないか」
「わわっ!」途端に律は赤面した。「私、こんなにたくさん飴、いりません!!」
「そうだよな。多すぎる。こんなにいっぺんに食えない」
「そうでしょう、そうでしょう。ですからおすそわけを」
「ひとりでこんなに食べたら、太るし、虫歯にもなるし」
「むむ」
ぽすっ。
律はつま先立ちをして、ツカサの後頭部を軽く、あくまでもかるーく、ひっぱたいた。話は戻る。バレンタインを数日後に控えた、ある日。
休み時間、廊下の隅で律は急に言い出した。
「ツカサさん、私は近日中に特製なお菓子を持参します」
「へえ。特製」
「ハンドメイドです。たぶん」
「手作り。豪勢だな。誰が作るんだろ」
「……少しだけ、ツカサさんにもおすそわけしたいと思います」
「それはどうも。しかしなあ」
「何か問題が」
「お菓子なら最近、鹿乃川からいつもごちそうになってるから」
そうなのである。
先日の飴玉以来、小腹が減るとツカサは律に依頼して餓鬼ちゃんを呼び、適度に菓子類を召喚してもらうという、謂わば横着をしていた。
「あ、あれは餓鬼ちゃんが出しているのであって、私がご馳走しているのとは違うのでは」律はうろたえる。
「意味合い的には一緒だ。俺、日々おごられっぱなしだな」
「ううっ、迂闊でした。特別感が薄れる」
「何が」
「……なんでもありません。ともあれ、そういうことで」
「よくわからないけどわかったよ。さて」
ツカサは中空から扇子を出して握った。
「今日は弁当を忘れたんだ。鹿乃川、餓鬼ちゃんを貸してくれ」
「ああ、もう。ツカサさん、お菓子はごはんの代わりにはなりませんよ」
「そこをなんとか」
「ええー」
「鹿乃川も食べたいだろ、甘いもの」
「食べたいですけど」
「そら見ろ」
「ちょっとだけですよ。廊下を埋め尽くすようなのはダメですよ」
「俺が扇子を振れば、期待通りの物が適量で出る。かもしれない」
「……仕方ないですね。餓鬼ちゃん。いらっしゃい」
律がそう言うと餓鬼ちゃん鹿が即座に、ぽぽん、と現れる――のが、このところのいつもの通例だった。
ツカサは餓鬼ちゃん制御のため、扇子を開く。律の許諾さえあれば、しばらくそのホンネを操ることは可能だ。
律は度の過ぎた召喚で溢れるであろうお菓子を処理すべく、身構える。
が、しかし。
出ない。子鹿が出てこない。
「あれ?」
ツカサは間違えたのかと思う。律も首をかしげた。
「扇子の振り方が足りないのではないのですか」
「打ち出の小槌じゃないんだから」
「餓鬼ちゃんを便利に使っていたのはツカサさんです」
「そうではあるけどな」
しかし扇子をいかに開こうが振ろうが鳴らそうが、やっぱり餓鬼ちゃんは現れなかった。
「おかしいな、家出か」とツカサが呟くと、
「そんな!」と律は本気で心配げだ。
「ああ、いや。原則的にはあり得ない。鹿乃川の意思に反してホンネが勝手に出歩いたりは」
「けれど現に何か変ですよ。私にもなんというか、餓鬼ちゃんがここにいる感触がない」
律は自分の胸の前で虚空を掴むゼスチュアをしてみせる。そこに居れば抱きかかえられるはずのものが、居ないのである。
「だがひとつ確証がある」ツカサは言う。
「確証? なんです?」律は怪訝そうだ。
「餓鬼ちゃんは消えちゃいない。何故なら」
「何故なら?」
「鹿乃川、のど渇いてないか?」
ツカサは指さした。律はそちらを見た。そこは壁面の小さな扉であり、消火用ホースが仕舞われている。
扉が開いた。
ホースの先から、オレンジジュースがちょろちょろ出ていた。
「ああ……ちょうど飲みたいとは思っていたのですけど、そんなところからどうして」
律はそこまで言って、はたと気づいた。
「なるほど、どうしてだか姿は見えませんが」
「近くにいる」
律とツカサは、顔を見合わせて頷く。
だが何を理由に餓鬼ちゃんが見えなくなったのか、ツカサにも見当がつかない。はじめてだった。
「にしても腹、減ったな……」
ホースのジュースはそのうち、止まった。それ以上何も出なかった。遠く草むらに伏せて隠れて、遠眼鏡を使って、ふたりの様子を窺っている青年がいた。
彼は律とツカサの困惑を見て、くつくつと笑った。
それから数日。
餓鬼ちゃんは、律のところには戻ってこなかった。ツカサが呼んでみても、やはり餓鬼ちゃんは現れなかった。
気掛かりで。ただ気掛かりで。とにかく気掛かりで。
そのうちに律は、特製なお菓子を持ってくることをすっかりと忘れたまま。
今年の二月十四日が終わっていた。 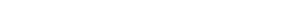
-
春先になって突如隣のクラスに現れた転校生の青年は、たちまち人気者になってしまった。
いつも甘い匂いを漂わせている、いたずらっぽい笑顔が特徴の爽やか男子だ。
「誰だよ、あれ」
基本的に他者に干渉しない主義のツカサだが、あまりに目立つ存在の転校生のことが気になり、周囲の噂話に耳を立ててみる。
ナルキ、という名らしい。彼がどこから来たのかは、皆が別々のことを言う。
有名ケーキ店の引越に伴ってこの地にやってきたのだと言う者もいる。
ああ見えて凄腕のパティシエなのだと言う者もいる。
実は大手製菓メーカーの御曹司かもしれないという説まで出た。
真相はまったくの不明だ。ナルキ自身も、それについてはノーコメントのようだ。
ただ、春の少し浮ついた学内の雰囲気に、明るく軽いナルキの言動は不思議と似合っていた。
キザで気取ったようでいて、どこか間が抜けているようにも感じられる、奇妙な軽さ。
まるでウェハースやムースのように軽かった。
「僕はね、葛葉くん」ある放課後、訊いてもいないのに急にやってきたナルキはツカサに言う。「いたずらが好きなんだ」
ナルキはその甘い匂いのせいか、いつも幾人かの取り巻きの女子をはべらせていたように思う。
だが、今は誰もいない。
夕日差し込む、無人の昇降口。
運動系の部活が頑張っているはずのグラウンドも、人の気配が無く、静まりかえっている。
不自然だった。
「なんだ、唐突に」
ツカサはうさんくさそうに顔をしかめてみせたが、ナルキは笑顔を崩さない。
「お菓子をくれないと、いたずらをするよ」
「季節外れのハロウィンか、お前は」
「僕はカボチャじゃない」
会話は噛み合わない。ツカサは頭を抱えながら、ナルキを追い払おうと考える。
「じゃあ煎餅をプレゼントしてやるから、消えてくれ」
「ありがとう。あ、このお煎餅って鹿乃川律から貰ったのかな?」
「お前、鹿乃川のこと知ってるのか」
「うん。熟知してる。ふふ」
「…………」
にこにこ笑うナルキが、なんだかツカサには、苛立たしい。
「で。菓子を受け取ったら、お前はどうするんだ?」
「そうだね~。やっぱり、僕はキミにいたずらをするよ!」
「おい!!」
ツカサは叫んだが、ナルキの姿は既に無い。
「ちっ、本当になんなのか」
いい加減もう帰ろうと、ツカサは下駄箱の扉に手を掛ける。途端、
ぼとぼとぼとぼと……。
「うえっ、まさかあいつが」
包み紙のない剥き出しのキャンディーがそこから次々に降ってきた。
しかも、だいたい溶けていた。ベタベタする……。
西日で昇降口は暑かった。甘すぎる香りが充満して、ツカサは頭痛を覚える。「結局、何者だよ」
ナルキの正体が掴めないまま、彼のいたずらなる犯行の始終を、思い余ってツカサは風紀委員の律に喋ってしまう。
証拠はないが本人が『いたずらをする』と言った直後に起こったことならば、犯人は間違いなかろう。
けれど律は意に介さないというか、別のことを気にしている。
「ツカサさん。これはきっと転校生個人の犯行ではありません。事件です」
「事件?」
「同時多発事件」
「え、俺以外にも被害者がいるのか」
「被害というか、目撃者というか……その」
律が言うに、ツカサの知らない場所でも学内のあちこちで同時期に、廊下にチョコレートが転がってきたり、蛇口からゼリーがぽろぽろ流れ出たりしていたらしい。
だとすればツカサ個人を狙ったいたずらではないし、単独の人間がどうこうできるものではない。
「そして大変遺憾ながら、この鹿乃川律には、犯人に心当たりが」
「俺も察しがついた」
「導き出される推論は」
「……餓鬼ちゃんか」
「餓鬼ちゃんです。ええと、すみません。どうすれば……」
「違うぞ鹿乃川、あんたのせいじゃない。コントロールを離れて勝手にやっていることだから」
「暴走的な何かですか?」
「そうだな。暴走。そう呼ぼう。どうしてホンネが鹿乃川から出て行ったのかはサッパリわからないが、現象を鑑みれば、そう言う他ない」
ううー、と律が唸る。
「私には餓鬼ちゃんの由来としての責任があります。なんとかしたいです」
「俺もなんとかしたい」
が、ツカサもこんなことは経験がない。
「いや待てよ」
「何か妙案が」
「ひとつある」
考え、ツカサは手を打った。「おはようございます。おはようござい……いえ、これはただのウェポン、じゃなくて飾りですから気にしないでください。おはようございます」
朝。新調された校門前でいつもの服装チェックに勤しんでいる、風紀委員の律。
片手に虫取り網を持って、仁王立ちの格好だ。
普段通りギリギリの時間に登校したツカサは、それを見て吹き出した。率直なところ、律のそれは他の生徒たちからも違和を持って迎えられている様子だ。
「おはよ……ぷっ、朝もそれ持ってるのか、鹿乃川」
「笑わないでください! ツカサさん、これも『あれ』を捕まえるためです」
「知ってる」
「知ってて笑うのはひどいですよ」
「悪い悪い」
一見して何の変哲もない、古ぼけたその虫取り網は、ツカサが見繕ったホンネ捕獲用のものだった。
ホンネの由来である律自身の意思が働けば、網は半ば自動的に、隠れている(またはどこかを彷徨っている)律のホンネ・餓鬼ちゃんを捜し出し、捕まえることが出来る。
なので律はいつ餓鬼ちゃんの気配を察知しても動けるよう、網を握りしめたまま、立っていたのだ。
けれどその朝、ついに餓鬼ちゃんを見つけることはできなかった。
「生徒や職員の誰かの中に、餓鬼ちゃんが紛れ込んでいるかも知れないと思ったのですが」
「いい推理だ」
「でも、いませんでした」
「うまく隠れているのか……それとも別の場所で寝て休んでいるのか」
「ふむ、休んで……」
「学校で分かれたなら、近くにいるままだろう。ホンネ単体ではそう遠くへは行けないはずだ」
「では学舎のどこかにいるのでしょうか。由来から離れたままのホンネは、どうなってしまうのです?」
「わからないな。力が弱まれば消えてしまうかも」
「それは嫌です」
ホンネは文字通りの自分の本音、その心の姿であり、自分の気持ちの自信を支えるものだ。分身でもあり、なかったら寂しい。律にも、餓鬼ちゃんに対する愛着と思い入れができはじめていたのだろう。
「見つけ出してやるさ」
ツカサも呟いた。奇妙な日常を招いた一端は、ツカサにもある。 
-
一時期、学舎内では餓鬼ちゃんの暴走と思われる、お菓子が自然に大量発生する謎の現象が見受けられていた。
壁伝いにこんこんとわき出るコーラ、勃発するプレッツェル、飛来するポテトチップス。
食べても無害であり、食べずともいつの間にか消えて無くなる。
最初は珍しさから生徒の歓迎を受けた現象だが、徐々に気味悪がられ、迷惑がられ、敬遠されて……。
けれどこの一週間ほど、その現象の噂をついぞ聞かない。
もう沈静化したのだろうか。
だが依然として餓鬼ちゃんは見つからず、捕まらない。気配も手掛かりも皆目見当ない。やがて律も虫取り網を持ち歩くことを忘れ、教室の片隅に放置してしまっていた。
沈静といえば、例の転校生・ナルキも騒がれることがなくなっていた。
取り巻きだった女子たちもほぼ消え、むしろあまり周囲に構う奴がいなくて、忘れられているのではなかろうか、というほどの薄い存在になっていた。
もっともナルキの場合、モテ期が過ぎたよりは、モテ過ぎて当人が飽きたか。
暇を持て余したらしきナルキは、今度はツカサに付きまとい始めた。
ツカサは無視しようかと考えたが、お構いなしにナルキはついて来る。その口の全土を占拠しそうな程の大きさのビッグペロキャンディーを舐めながら、やたら明るいスマイルを浮かべて、ナルキは話し掛けてくる。
「やあやあ、葛葉ツカサくん」
「なんだよ?」
「ツカサ! って呼んでいいかな」
「思った以上に馴れ馴れしい奴だな、お前……」
ダメだと言ってもナルキは聞きそうにないので、ツカサは見過ごし、聞き過ごしながら、廊下を行く。
「ツカサツカサツカサ、ツカサは鹿乃川律とどういう関係なの」
「どうって」
「付き合ってるんだろ」
「違う」
「なんだ違うのか、つまらない」
「ご期待に添えず悪かったな」
「でも、だいぶ仲良しだ、律とツカサ」
「そうか?」
「ふたりでいること、多いし……」
別段多くはないだろう、とツカサは思い返してみる。
毎朝顔を合わせる機会があるが、これは単に律が門番、いや風紀委員として校門に立っているからだろう。
餓鬼ちゃん絡みの相談は確かに内密でふたりですることはあるが、これも昼休みや放課後のほんの数分ずつのことだ。
それほど頻繁ではない。
「うーらーやまーしーい」ナルキは変な節をつけて、間延びしたように言う。「羨まーしいー羨ましいー」
「ナルキお前、律と親しくなりたいのか」ツカサはつい訊く。
「違うよ」ナルキは口をとがらせた。「わかってないなー」
「じゃあ、なんだ」
「僕はツカサと仲良くしたいんだ」
「はあ?」
「ツカサと仲良くしたいんだよ」
「意味がわからないが」
「親しくしたいんだよ!」
「いや、なんでだよ」
「理由が必要かな? たとえばほら」
どこからともなく、手品みたいに器用に手指を動かして、ナルキはツカサへお菓子を差し出す。
「おなかが減ったらチョコバーだ。食べることに理由はなくてもOK」
「え」
「あげるよ。いらないの?」
「寄越せ」
ツカサはナルキの手からチョコレート・バーをひったくった。
「お前、俺の好物を良く知ってたな」
「偶然だよ」
「まあ、いただく」喜ばしくも笑えず、ツカサはふてくされたような変な表情をしながら、ぱくつく。
「律もそのチョコ好きなんだよね」とナルキはにこやかに言う。
「……鹿乃川の話題、まだ続くのか」
「嫌かい」
「くどい」
「やれやれ……」
大袈裟に呆れた様子を作るナルキ。それを見てツカサのほうがため息をつく。
「なんでそんなに鹿乃川にご執心なんだ」
「ちがうよー」ナルキはあどけなくもきりりとした顔に似合わず、急に駄々を捏ねるように言う。「確かに僕は律ととっても仲良しだったけど、そうじゃなくて、ツカサと友達になりたいんだ!」
じたばたしながら、ナルキは続ける。
「律とツカサは仲良い! くやしい! 僕もツカサと仲良くしたい!」
「案外、子どもみたいな奴だな」チョコを食べながら、ストレートな感想がツカサの口から出た。
「あ、それだ! そうそう。そうなんだ。僕はね、子どもなんだよ」
「なんだって?」
「子どもだからモノを知らない。だからツカサに色々教えて欲しい。ねーねー、キミに好かれるには僕はどうしたらいいんだい?」
ナルキはにじり寄ってきた。「おい、くっつくな」ツカサは構わずに廊下を延々歩いてきたつもりだったが、いつの間にか通路は終端だ。「ねーねー」迫るナルキ。腕が伸びて、ツカサに絡みつこうとする。「離れろって」行き止まりに追い詰められるのは、なんだか宜しくない。
どん。
力を入れてはいないが、思わずつい、ツカサは手で突き放してしまう。
よろよろと数歩後ずさってやっと止まったナルキに、まくし立てた。
「俺はお節介をされるのも、するのも嫌いだ。やりたければ、俺に構わず勝手にやっていてくれ」
「ううー」不服そうながらもそこから一歩ずつ下がり、ゆっくりゆっくり、ナルキは離れる。
「わかった。勝手にする……勝手にするよ」
突然ナルキは後ろ向きのまま、走り出した。異様なほどのスピードで、バックしていく。
「勝手にしよう、そうしよう」
あまつさえ、ナルキはツカサにあかんべえをして寄越した。
「……あの、馬鹿……」
ツカサは追わざるを得ない。あいつは、ふざけすぎる。
逆向きのまま通路の終端を折れ、別の道にナルキは入る。
だがそこで、異音がした。
何かあったのか?
ツカサが駆けつけると、ナルキは当惑したように立ち尽くし、左右を見回していた。
ここは新校舎と旧校舎とを繋いでいたはずの廃止通路の果てだ。そしてこの縄張りの主たち、この学舎では実に珍しい、着崩した制服にいかめしく険しい顔つきの――古めかしく言えば所謂不良な風体の――輩が、ナルキを囲んでいた。
ナルキは、輩の主格らしき彼らのひとりにぶち当たり、大きくよろめかせてしまっていた。
体制を直しつつ、こちらを睨みつけ、大仰に身のホコリを払いながら彼が言う。
「よう。ぶつかっといて、挨拶無しかい」
「こんにちは!」とすかさずナルキ。
「ふざけてるのか?」と輩の二。
「真面目だよ。キミたちとは違うからね」
「なんだと、何様だ、てめえ?」と輩の三。
「え、僕のこと知らないの。僕はねえ~」
「「知ったことかよ!」」輩たちがいきり立った。
「ルールのわからねえ奴だな。痛い目見せてやろうか」
輩の中でも特に体格の良いひとりが進み出て、ナルキの襟首を掴んだ。
「あ……」
ナルキは固まって動けない。本当にわからないのだ。何故こんな目に遭っているのか、ナルキは理解できていない。
「……なあ。あんたたち。待ってくれよ。こいつ転入して日が浅いから――」
ツカサは、輩たちの主格とナルキの間に割って入った。
「――日が浅いから、ルールを知らない。だからこれから教えないとなんだ」
「教える?」輩の主格が首をかしげ、顔をしかめつつツカサに近づく。「お前はこいつの保護者か何かか?」
「……そんなところだ」
そう答えてみてから、おかしいな、何か我ながら随分柄にもないことをしているな、とツカサはふと思った。
ナルキを助けてやろうとか、輩たちの機嫌を取ろうとか、そういうことは特に考えになかった。
ただ気づいたら、自然と身体が動いていた。
何故だろう?
急に、ナルキのことが他人に思えなくなった。
この飴舐め野郎は確かに子どもだなあ、と思いもしたが。
「やめてやってくれないか」
ツカサは目をそらさず、輩の主格に向かい合った。互いの様子を窺うかのように、しばし睨み合う。
「放してやれ」主格が言い、大男の手がナルキから退く。その目をツカサを見つめたままだ。「で、何をどう教えるんだ、少年」
「それは、つまり……」
自分でも説明がつかないまま、ツカサはあれこれと言葉を尽くしてみる。
人にはそれぞれ、領分がある。
本来ツカサは誰に対しても立ち入らず、誰にも立ち入って欲しくはなかった。そのはずだった。
それなのに。
俺は何をしているんだ?
よくわからないもやもやが、ツカサの胸の内に漂った。
昔。だいぶ昔。似たようなことがあった気がするが、思い出せない。
不安を隠すべく、ツカサはヘッドフォンに触れる。じっとりと、手が汗に塗れていた。
バケモノ相手の戦いならばともかく、自分以外の人間のために世話を焼くなど、現実と格闘することには不慣れなツカサだった。
だが苦慮しながらも、その場は和解する。
「邪魔して悪かったな」
輩たちに向かい、ツカサはナルキの頭を無理矢理下げさせる。
「次から、気をつけな」
主格に苦笑されつつ、肩をどんと押され、いかつい輩たちに見送られながら、ツカサとナルキは共に、そこを去った。


